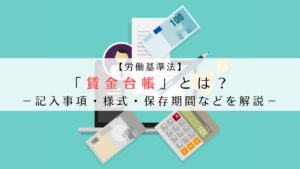【労働基準法】法定四帳簿(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・年次有給休暇管理簿)の記入事項、様式、保存期間などを解説

はじめに
労働基準法に基づき、使用者に対して作成が義務付けられている代表的な4つの帳簿のことを、一般に、「法定四帳簿」といいます。
法定四帳簿には、「労働者名簿」、「出勤簿」、「賃金台帳」および「年次有給休暇管理簿」の4つがあります。
本稿では、法定四帳簿について、それぞれ、帳簿の記入事項、様式、保存期間などを解説します。
労働者名簿
労働者名簿とは
「労働者名簿」とは、労働者ごとに、氏名や入退社などに関する情報が記入された名簿をいいます。
労働基準法では、使用者は、各事業場ごとに、労働者名簿を、各労働者について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならないと定められています(労働基準法第107条第1項)。
また、労働者名簿の記入事項に変更があった場合には、遅滞なく訂正しなければならないとされています(労働基準法第107条第2項)。
労働者名簿は、事業の種類、規模(従業員数)に関係なく、また、労働者の雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)に関わらず、すべての労働者について作成する義務があります。
ただし、日雇いの労働者については、労働者名簿を作成する義務はありません。
労働者名簿の記入事項
労働者名簿に記入しなければならない内容は、労働基準法によって次のとおり定められています(労働基準法施行規則第53条第1項)。
労働者名簿の記入事項
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類(※)
- 雇入れの年月日
- 退職の年月日およびその事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
- 死亡の年月日およびその原因
(※)常時30人未満の労働者を使用する事業では、6.の「従事する業務の種類」については、記入する必要がありません(労働基準法施行規則第53条第2項)。
なお、以前は労働者名簿に本籍を記入する必要がありましたが、平成9(1997)年の法改正により記入項目から削除されました。
労働者名簿の様式
労働者名簿の様式(書式)としては、「様式第19号」があります。
ただし、必ずしも当該様式を使用する必要はなく、法定の記入事項が満たされていれば、使用者が任意に作成したもので構いません。
また、当該様式は必要な事項の最低限度を定めるものであって、横書き、縦書き、その他異なる様式を用いることを妨げるものではありません(労働基準法施行規則第59条の2)。
なお、帳簿の名称について、例えば、「社員名簿」や「従業員名簿」などの名称で調整されていることがありますが、法定の記入事項が満たされていれば問題ありません。
労働者名簿の保存期間
会社は、労働者名簿を3年間保存しておく義務があります(労働基準法第109条、附則第143条第1項)。
この3年間の起算日は、「労働者の死亡、退職または解雇の日」と定められています(労働基準法施行規則第56条第1項第一号)。
罰則
労働者名簿の作成義務について違反があった場合の罰則として、30万円以下の罰金が定められています(労働基準法第120条第一号)。
違反とは、労働者名簿を作成していない場合、労働者名簿の記入事項に不足がある場合、労働者名簿に虚偽の内容を記入した場合などが該当するものと解されます。
出勤簿
出勤簿とは
「出勤簿」とは、労働者の出退勤や遅刻・早退など、勤怠の情報を記録した帳簿をいいます。
労働基準法では、出勤簿の作成を義務付ける定めはありません。
ただし、出勤簿は、適切な労働時間管理や賃金支払いの前提として、不可欠なものです。
厚生労働省のガイドライン「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」では、出勤簿やタイムカードなどの労働時間の記録に関する書類については、労働基準法が保存を義務付けている「労働関係に関する重要な書類」に該当するものとしています(労働基準法第109条)。
出勤簿の記入事項(例)
出勤簿の記入事項(例)
- 氏名
- 出勤日
- 出勤日ごとの始業・終業時間(※)
- 休憩時間
- 残業時間
- 遅刻・早退・欠勤時間など
(※)例えば、押印など出退勤の確認のみで、始業・終業時間が記録されていない場合は、適切に記入されているとはいえません。
また、出勤簿に関連して、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード・タイムレコーダーなどの記録、残業命令書およびその報告書、労働者が自ら労働時間を記録した労働時間報告書などがある場合には、保存しておく必要があります。
出勤簿の保存期間
会社は、出勤簿を3年間保存しておく義務があります(労働基準法第109条、附則第143条第1項)。
この3年間の起算日は、「労働者の最後の出勤日」(条文上は「その完結の日」)と解されます(労働基準法施行規則第56条第1項第五号)。
賃金台帳
賃金台帳とは
「賃金台帳」とは、労働者の賃金計算および賃金支払いの基となる帳簿をいいます。
労働基準法では、使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を、賃金を支払う都度、遅滞なく記入しなければならないと定められています(労働基準法第108条)。
賃金台帳は、事業の種類、規模(従業員数)に関係なく、また、労働者の雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)に関わらず、すべての労働者について作成する義務があります。
なお、労働者名簿と異なり、日雇いの労働者についても賃金台帳を作成する義務があります。
また、賃金台帳は、労働者名簿、年次有給休暇管理簿と併せて作成することが認められています(労働基準法施行規則第55条の2)。
賃金台帳と給与明細書の違い
給与明細書は、一般に、使用者が労働者に対し、賃金(給与)を支払う都度、その給与の内訳などを通知するために交付するものです。
給与明細書の作成・交付は、労働基準法で義務付けられているものではなく、賃金から社会保険料や税金を控除したことを証明することを目的に行われるものです(健康保険法第167条、所得税法第231条など)。
給与明細書は、その内容が賃金台帳と重複することがあるため、給与明細書が賃金台帳の記入事項を網羅している場合には、給与明細書を賃金台帳として保存することは問題ありません。
賃金台帳の記入事項
賃金台帳に記入しなければならない内容は、労働基準法によって次のとおり定められています(労働基準法施行規則第54条第1項)。
なお、賃金台帳は、従業員ごとに調整する必要がある点にも留意してください。
賃金台帳の記入事項
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとに、その額
- 賃金の一部を控除した場合には、その額
雇用期間が1ヵ月に満たない日雇いの労働者の場合、賃金台帳の作成対象にはなりますが、上記の項目のうち3.の「賃金計算期間」については記入する必要がありません。
また、管理監督者については、労働基準法のうち労働時間に関する定めが適用されないため、5.の「労働時間数」と、6.の「時間外労働・休日労働の時間数」の記入を要しません(労働基準法施行規則第54条第5項)。
ただし、管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金は支払う義務があるため、6.のうち「深夜労働の時間数」は記入する必要があります。
賃金台帳の様式
賃金台帳の様式(書式)について、常時雇用される従業員については、厚生労働省の「様式第20号」によって調製しなければならないと定められています(労働基準法施行規則第55条)。
ただし、当該様式は必要な事項の最低限度を定めるものであって、横書き、縦書き、その他異なる様式を用いることを妨げるものではありません(労働基準法施行規則第59条の2)。
賃金台帳の保存期間
会社は、賃金台帳を3年間保存しておく義務があります(労働基準法第109条、附則第143条第1項)。
この3年間の起算日は、会社が賃金台帳に「最後の記入をした日」と定められています(労働基準法施行規則第56条第1項第二号)。
罰則
賃金台帳の作成義務について違反があった場合の罰則として、30万円以下の罰金が定められています(労働基準法第120条第一号)。
違反とは、賃金台帳を作成していない場合、賃金台帳の記入事項に不足がある場合、賃金台帳に虚偽の内容を記入した場合などが該当するものと解されます。
年次有給休暇管理簿
年次有給休暇管理簿とは
「年次有給休暇管理簿」とは、労働者の年次有給休暇の取得状況を記入した帳簿をいいます。
労働基準法施行規則では、使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数および基準日(第一基準日および第二基準日を含む)を労働者ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成しなければならないと定められています(労働基準法施行規則第24条の7)。
なお、年次有給休暇管理簿は、労働者名簿、賃金台帳と併せて作成することが認められています(労働基準法施行規則第55条の2)。
年次有給休暇管理簿の記載事項
労働基準法施行規則に基づくと、最低限、以下の内容を記載する必要があります。
年次有給休暇の管理簿の記載内容
- 時季(有給休暇を取得した日付)
- 日数(有給休暇を取得した日数)
- 基準日(有給休暇が与えられた日)
上記の他にも、雇入れ日、付与日数などを記載することが考えられます。
年次有給休暇管理簿の様式
管理簿の様式については、特に指定されていませんので、使用者が任意に作成したもので構いません。
年次有給休暇管理簿の保存期間
年次有給休暇管理簿は、年次有給休暇を与えた期間中、および当該期間の満了後3年間保存しなければならないとされています。
罰則
行政通達では、年次有給休暇管理簿は、労働基準法第109条に規定する重要な書類には該当しないとされていることから、労働基準法第120条が定める罰則(第109条違反)は適用されないものと解されます(2018年9月7日基発0907第1号)。