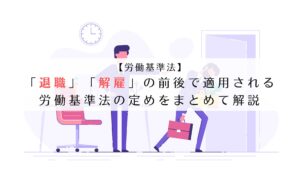【労働基準法】「賃金台帳」とは?記入事項、様式、保存方法、保存期間などを解説
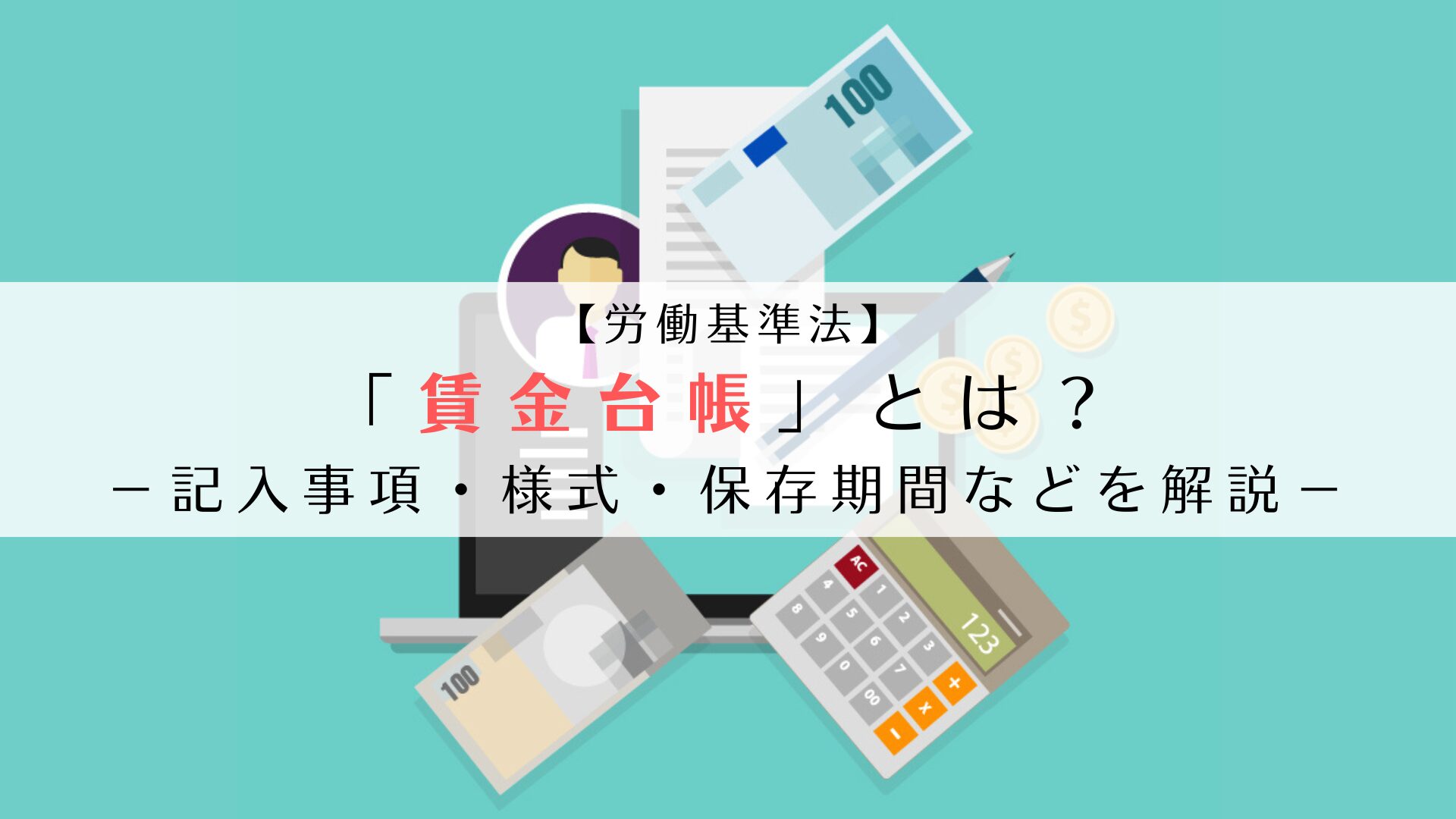
- 1. はじめに
- 2. 賃金台帳とは
- 2.1. 賃金台帳とは
- 2.2. 賃金台帳と給与明細書の違い
- 3. 賃金台帳の記入事項
- 3.1.1. 1.労働者の氏名
- 3.1.2. 2.性別
- 3.1.3. 3.賃金計算期間
- 3.1.4. 4.労働日数
- 3.1.5. 5.労働時間数
- 3.1.6. 6.時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
- 3.1.7. 7.基本給、手当その他賃金の種類ごとに、その額
- 3.1.8. 8.法第24条第1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
- 4. 賃金台帳の様式
- 4.1. 一般の労働者の賃金台帳
- 4.2. 日雇い労働者の賃金台帳
- 5. 賃金台帳の保存方法
- 6. 賃金台帳の保存期間
- 7. 賃金台帳の違反に対する罰則
はじめに
労働基準法に基づき、使用者に対して作成することが義務付けられている書類として、「労働者名簿」、「出勤簿」、「賃金台帳」および「年次有給休暇管理簿」の4つの帳簿があり、これらを一般に、「法定四帳簿」といいます。
本稿では、法定四帳簿のうち、「賃金台帳」について、記入事項、様式、保存方法、保存期間などを解説します。
「法定四帳簿」の各内容については、次の記事をご覧ください。
【労働基準法】法定四帳簿(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・年次有給休暇管理簿)の記入事項、様式、保存期間などを解説
賃金台帳とは
賃金台帳とは
「賃金台帳」とは、労働者の賃金計算および賃金支払いの基となる帳簿をいいます。
労働基準法では、使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を、賃金を支払う都度、遅滞なく記入しなければならないとされています(労働基準法第108条)。
賃金台帳は、事業の種類、規模(労働者数)に関わらず、また、労働者の雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)に関わらず、すべての労働者について作成する義務があります。
賃金台帳は、労働者名簿と異なり、日雇いの労働者についても作成する義務があります。
なお、賃金台帳は、労働者名簿、年次有給休暇管理簿と併せて作成することが認められています(労働基準法施行規則第55条の2)。
賃金台帳と給与明細書の違い
給与明細書は、一般に、使用者が労働者に対し、賃金(給与)を支払う都度、その給与の内訳などを通知するために交付するものです。
給与明細書の作成・交付は、労働基準法で義務付けられているものではなく、賃金から社会保険料や税金を控除したことを通知するために行われるものです(健康保険法第167条、所得税法第231条など)。
給与明細書は、その内容が賃金台帳と重複することがあるため、給与明細書が賃金台帳の記入事項を網羅している場合には、給与明細書を賃金台帳として保存することは問題ありません(昭和39年6月8日基収2784号)。
賃金台帳の記入事項
賃金台帳に記入しなければならない内容は、労働基準法によって次のとおり定められています(労働基準法施行規則第54条第1項)。
賃金台帳の記入事項
- 労働者の氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとに、その額
- 法第24条第1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
1.労働者の氏名
賃金台帳は、労働者ごとに、個人単位で作成する必要があります。
なお、労働者の氏名は、事業場で使用する労働者番号をもって代えることができます(様式第20号記載心得1)。
2.性別
労働者の性別を記入します。
3.賃金計算期間
雇用期間が1ヵ月に満たない日雇いの労働者の場合は、記入事項のうち「賃金計算期間」については、記入する必要がありません(労働基準法施行規則第54条第4項)。
4.労働日数
3.の賃金計算期間における労働日数を記入します。
5.労働時間数
管理監督者については、労働基準法のうち労働時間に関する定めが適用されないため、「労働時間数」については、記入する必要がありません(労働基準法施行規則第54条第5項)。
6.時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
労働時間数は、当該事業場の就業規則において、法の規定と異なる所定労働時間または休日の定めをした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数をもってこれに代えることができます(労働基準法施行規則第54条第2項)。
管理監督者については、労働基準法のうち労働時間に関する定めが適用されないため、「時間外労働・休日労働の時間数」については、記入する必要がありません(労働基準法施行規則第54条第5項)。
ただし、管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金は支払う義務があるため、6.のうち「深夜労働の時間数」は記入する必要があります(昭和23年2月3日基発161号)。
また、時間外労働または休日労働が深夜に及んだ場合には、深夜の部分の労働時間数を深夜労働時間数の欄にも記入する必要があります(様式第20号記載心得2)。
なお、5.の「労働時間数」と6.の「時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数」については、これらの時間が出勤簿やタイムカードに記録されている労働時間と整合していることが重要であり、これらの時間が整合していなければ、何らかの未払い賃金が生じている可能性があるといえます。
7.基本給、手当その他賃金の種類ごとに、その額
・年次有給休暇を取得した場合
労働者が年次有給休暇を取得したことにより、年次有給休暇手当を支払った場合には、賃金台帳の手当欄に、「年次有給休暇手当」などとして記入することとされています(昭和22年12月26日基発573号)。
また、年次有給休暇の期間における日数、時間数は、実際に従事した日数および労働時間数とみなしてそれぞれ様式の該当欄に記入し、その日数および時間数をそれぞれ該当欄に別掲して括弧をもって囲んで記入することとされています(昭和23年11月2日基収3815号)。
・宿日直手当
宿日直勤務については、手当欄に宿直手当または日直手当として記入し、各々その回数を括弧で囲んで金額欄に付記することとされています(昭和23年11月2日基収3815号)。
・通貨以外のもので支払われる賃金がある場合
賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならないとされています(労働基準法施行規則第54条第3項)。
実物給与の欄には、当該賃金計算期間において支給された実物給与の評価額をその種類ごとに記入する必要があります(様式第20号記載心得3)。
8.法第24条第1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
社会保険料や税金など、賃金から控除した項目とその金額を記入します。
なお、旅行の積立金など、法律に基づき控除することが認められていない賃金を控除する場合には、使用者と労働者の代表者との間で、賃金の一部控除に関する労使協定を締結する必要があります(労働基準法第24条)。
賃金台帳の様式
一般の労働者の賃金台帳
賃金台帳の様式(書式)については、常時雇用される労働者については、厚生労働省の「様式第20号」によって調製しなければならないとされています(労働基準法施行規則第55条)。
ただし、当該様式は必要な事項の最低限度を定めるものであって、横書き、縦書き、その他異なる様式を用いることを妨げるものではありません(労働基準法施行規則第59条の2)。
したがって、記入事項がきちんと網羅されていれば、例えば、各項目の順番が前後していても問題なく、一部が別冊になるなどしていても問題ありません(昭和25年1月13日基収4083号)。
日雇い労働者の賃金台帳
日々雇い入れられる者(一ヵ月を超えて引続き使用される者を除く)については「様式第21号」によって調製しなければならないとされています(労働基準法施行規則第55条)。
賃金台帳の保存方法
賃金台帳の保存方法としては、賃金台帳をパソコンなどにデータとして保存しておくか、紙面に印刷して保存しておく方法があります。
行政通達では、次の2つの要件をいずれも満たす場合には、データで保存することをもって労働基準法上の要件を満たすものとして取り扱うことが認められます(平成7年3月10日基収94号)。
データ保存の要件
- 電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調製された賃金台帳に法定必要記載事項を具備し、かつ、事業場ごとにそれぞれ賃金台帳を画面に表示し、および印字するための装置を備えつける等の措置を講ずること
- 労働基準監督官の臨検時など、貸金台帳の閲覧、提出などが必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出することができるシステムとなっていること
賃金台帳をデータとして保存する場合には、データをパソコンのハードディスクやCD-Rなどの媒体に保存しておき、労働基準監督官による臨検監督などの際には、監督官の求めに応じて直ちに閲覧し、または紙面に印刷できるようにしておく必要があります。
賃金台帳の保存期間
使用者は、賃金台帳を3年間保存しておく義務があります(労働基準法第109条、附則第143条第1項)。
この3年間の起算日は、使用者が賃金台帳に「最後の記入をした日」とされています(労働基準法施行規則第56条第1項第二号)。
賃金台帳の違反に対する罰則
賃金台帳の作成義務について違反があった場合の罰則として、30万円以下の罰金が定められています(労働基準法第120条第一号)。
違反とは、賃金台帳を作成していない場合、賃金台帳の記入事項に不足がある場合、賃金台帳に虚偽の内容を記入した場合などが該当するものと解されます。
実際には、虚偽記載など悪質な場合は別として、賃金台帳の記載事項のひとつに誤りや漏れがあったとしても、直ちに罰則が適用されることはないと考えます。
賃金台帳に不備があった場合には、まずは労働基準監督署から指導または是正勧告があり、これに従って速やかに是正をすれば、罰則が適用される可能性は低いと考えます。