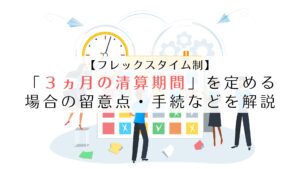【健康保険】19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件の変更(年収130万円未満→年収150万円未満)を解説【2025年10月1日変更】
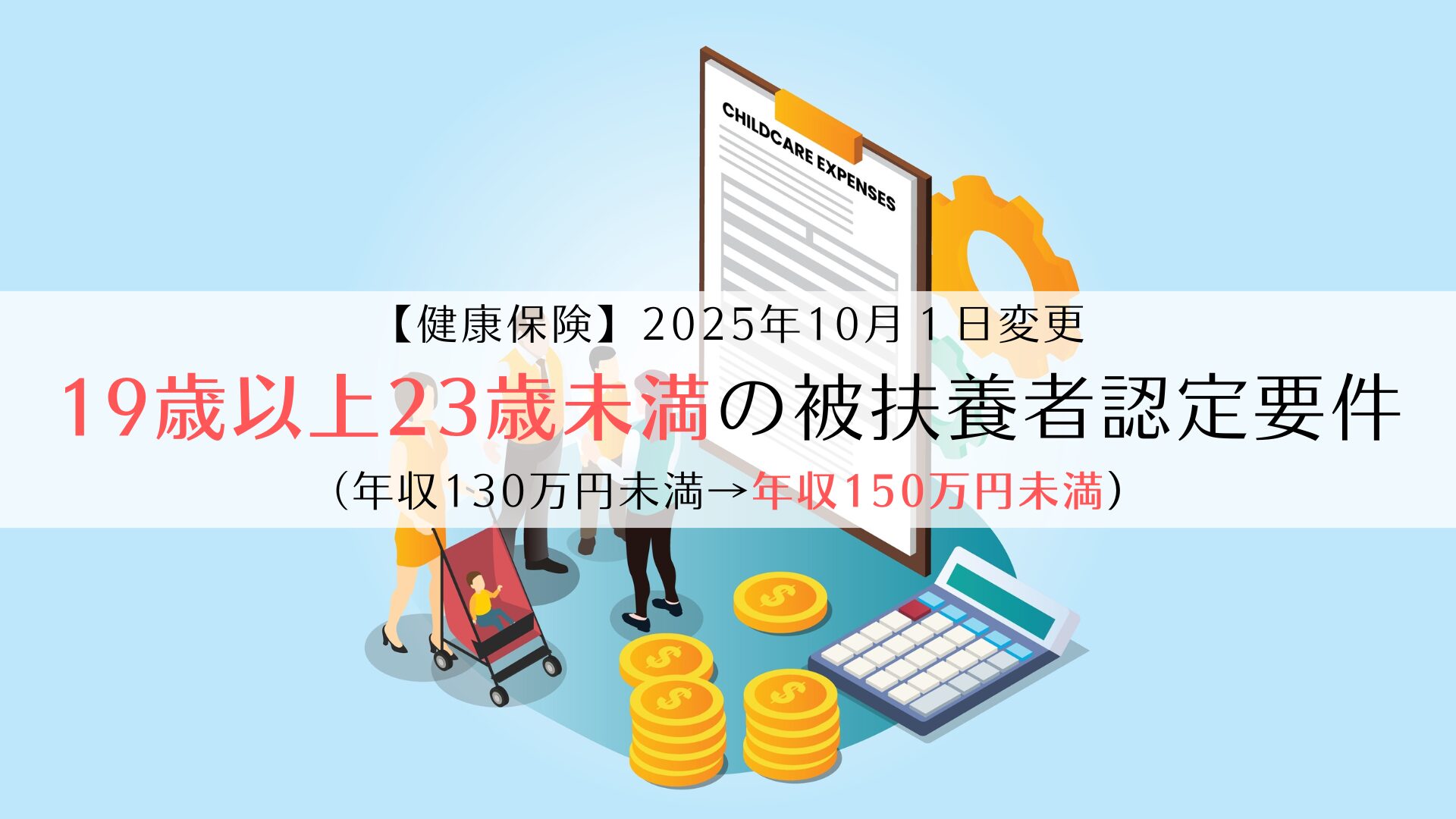
はじめに
2025(令和7)年度の税制改正において、厳しい人手不足の状況における就業調整対策などの観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における、特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われました。
これを受けて、健康保険においても、被扶養者の認定を受ける者が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件が変更され、2025(令和7)年10月1日より、年収130万円未満から年収150万円未満に引き上げられました。
被扶養者の認定における年間収入要件の変更内容
健康保険では、被保険者と、その被扶養者の病気、けが、出産などに対して保険給付が行われます。
健康保険において、被保険者の親族であって、年間収入要件など一定の要件を満たす場合は、保険者の認定を受けることによって、被保険者の扶養者として健康保険に加入することが認められています。
このとき、従来は、被扶養者の年間収入が原則として「130万円未満」であることが認定の要件とされていましたが、行政通達の変更により、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)については、年間収入にかかる要件が「150万円未満」に引き上げられました(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)。
この取り扱いは、2025(令和7)年10月1日から適用され、同日以降に被扶養者の認定を受ける者が対象となります。
この年間収入にかかる要件以外に、被扶養者の認定要件に変更はありません。
なお、今回の変更の対象には、被保険者の配偶者は含まれていません。
被扶養者の認定要件
被扶養者の認定要件
健康保険法において、被扶養者として認定されるための要件は、原則として、日本国内に住所を有する、被保険者と三親等内の親族であって【要件1】、かつ、主として被保険者の収入によって生計を維持されていること【要件2】とされています(健康保険法第3条第7項)。
ただし、後期高齢者医療の被保険者である者は除きます。
【要件1】被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は、同居の有無によって、次の親族が該当します。
【図】被扶養者の範囲
| 被保険者と別居していても認定される親族 | 被保険者と同居している場合のみ認定される親族 |
| 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母) 配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む) 子 孫 兄弟姉妹 | 三親等内の親族(左欄の者を除く) 配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係にある者の父母・子 上記の配偶者の死亡後におけるその父母・子 |
【要件2】被扶養者の年間収入要件
被扶養者の認定要件のうち、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」に該当するか否かの判定は、行政通達に基づき、主に年間収入と、被保険者との関連における生活の実態によって判断することとされています(昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号)。
【同居】被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者または一定の障害者である場合は180万円未満)であること
- 被保険者(扶養者)の年間収入の2分の1未満であること
ただし、上記の要件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者または一定の障害者である場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして認定されることがあります。
【別居】被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
- 認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上の者または一定の障害者である場合は180万円未満)であること
- 被保険者(扶養者)からの援助による収入額(仕送り額)より少ないこと
「年間収入」とは
健康保険における被扶養者の認定における「年間収入」とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降に見込まれる年間の収入額をいい、過去の収入額ではないことに留意する必要があります(なお、所得税では、1月1日から12月31日までに支給されることが確定した給与をもって所得控除などを判断する点で異なります)。
給与収入の場合には、月額108,333円(年間収入に換算すると、1,299,996円)以下であることが、130万円未満となるための目安となります。
「収入」には、給与収入はもちろん、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金および出産手当金なども収入として取り扱うこととされています。
年齢要件の判定(19歳以上23歳未満)
被扶養者の年齢(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢をもって判定されます。
例えば、扶養認定を受ける者が、2026(令和8)年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、2026(令和8)年の12月31日時点における年齢が19歳になることから、2026(令和8)年(1月1日から12月31日までの暦年)における年間収入要件は「150万円未満」となります。
そして、この場合には、2030年(令和12)年10月に23歳の誕生日を迎えることになるため、2030年(令和12)年における年間収入要件は「130万円未満」となります。
なお、被扶養者が学生であることは、要件とされていませんので、あくまでも年齢によって判断します。
年齢と年収判断(N年(暦年)に19歳の誕生日を迎える場合)
- N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は「130万円未満」
- N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は「150万円未満」
- N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は「130万円未満」
なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定の準用により、年齢は、誕生日の前日において加算します。
例えば、誕生日が1月1日である場合は、その前日の12月31日において年齢が加算されます。