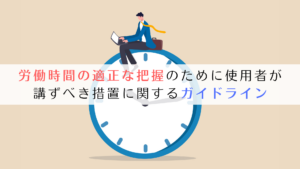「労働者数」に応じて適用される労働関連の法令(労働基準法など)をまとめて解説
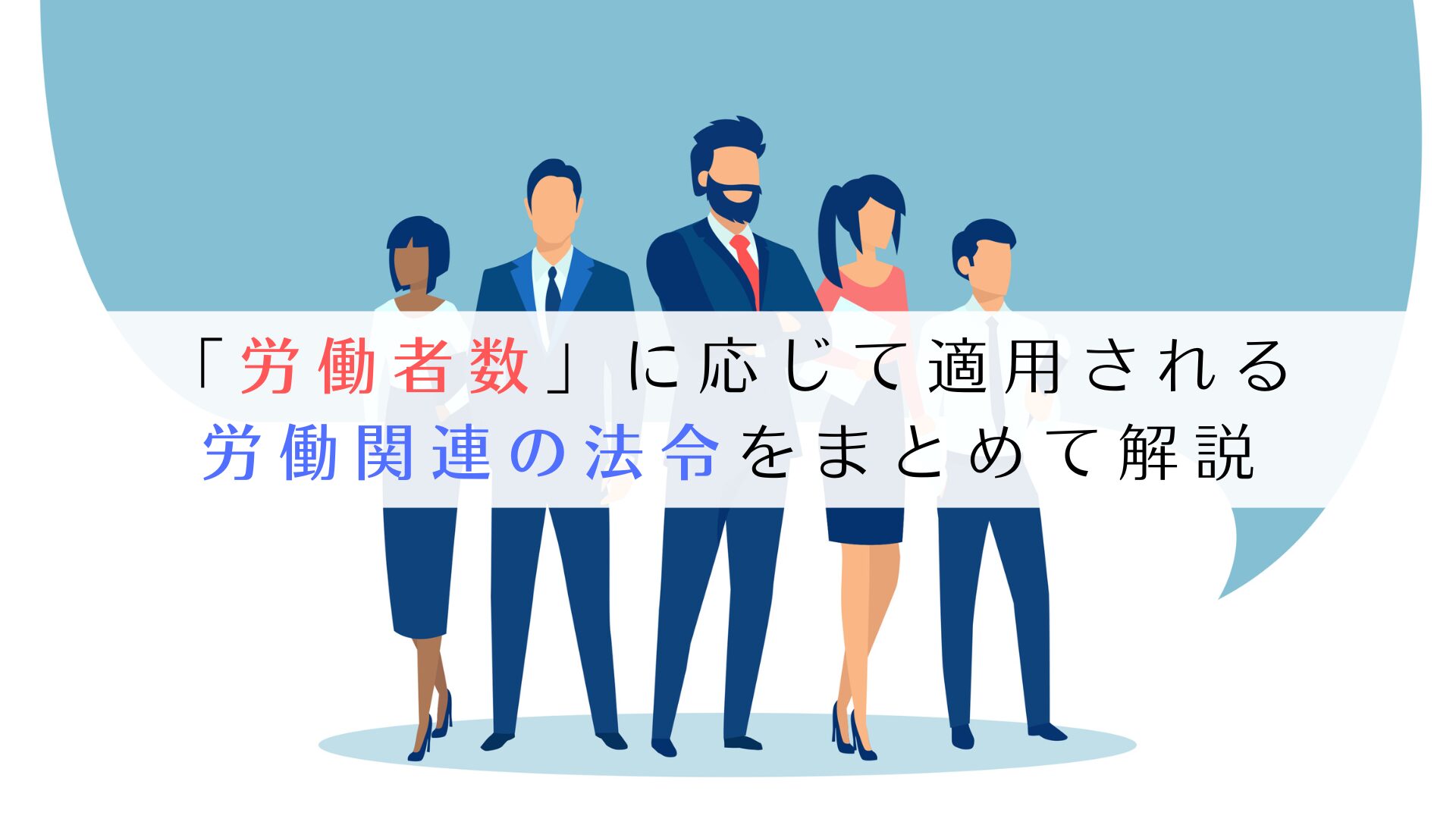
- 1. はじめに
- 2. 労働者数が1人以上の場合
- 2.1. 労働基準法の適用
- 2.2. 労働安全衛生法の適用
- 2.3. 労働保険への加入
- 2.4. 社会保険への加入(法人の場合)
- 3. 労働者数が5人以上の場合(個人事業所の場合)
- 4. 労働者数10人以上の場合(事業場単位)
- 4.1. 就業規則の作成義務
- 4.2. 安全衛生推進者または衛生推進者の選任義務
- 5. 労働者数50人以上の場合(事業場単位)
- 5.1. 産業医・安全管理者・衛生管理者の選任義務
- 5.2. 健康診断結果の報告義務
- 5.3. ストレスチェックの実施義務
- 6. 厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の場合
- 7. 労働者数101人以上の場合(企業単位)
- 7.1. 一般事業主行動計画の策定・届出・公表義務
- 7.2. 女性活躍推進法に基づく情報公表
- 7.3. 障害者雇用納付金の徴収・障害者雇用調整金の支給
- 8. 労働者数301人以上の場合(企業単位)
- 8.1. 中途採用比率の公表義務
- 8.2. 男性の育児休業の取得状況の公表義務
はじめに
企業の労務管理においては、労働基準法を始めとして、労働に関連する多くの法令が適用されます。
そして、当該法令の中には、企業または事業場を単位とする「労働者数」に応じて、適用の有無が異なるものがあります。
法律が定める労働者数に達しているにも関わらず、対応を失念すると、予期せぬ法違反が生じることもあります。
本稿では、特に「労働者数」を基準に適用される主な労働関連の法令をまとめて解説します。
労働者数が1人以上の場合
労働者数が1人以上の場合
- 労働基準法の適用
- 労働安全衛生法の適用
- 労働保険(労災保険・雇用保険)への加入
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入(法人の場合)
労働基準法の適用
使用者が労働者を1人でも雇用する場合には、労働基準法が適用されます。
労働基準法では、法定労働時間、法定休日、年次有給休暇など、労働条件の最低基準が定められており、使用者は、これを下回る労働条件を定めることができません。
例えば、労働者を雇い入れる際の労働条件の明示(労働基準法第15条)、労働時間が1日8時間・1週40時間を超えてはならないとする法定労働時間(労働基準法第32条)、法定労働時間を超えて時間外労働をする場合における36協定の手続き(労働基準法第36条)などの定めがあります。
労働安全衛生法の適用
使用者が労働者を1人でも雇用する場合には、労働安全衛生法が適用されます。
労働安全衛生法は、労働者の安全面、衛生面に関する措置を使用者に義務付けるものです。
例えば、使用者は、常時雇用する労働者について、雇い入れの際、および1年以内に1回、定期的に健康診断を実施する義務などを負います(労働安全衛生規則第43条、第44条)。
労働保険への加入
使用者が労働者を1人でも雇用する場合には、労働保険(労災保険および雇用保険)に加入する義務があります(労働者災害補償保険法第3条、雇用保険法第5条)。
労災保険は、労働者の業務上の負傷・疾病などに対し、その療養のための補償や休業補償などを行うために、政府が運営する公的な保険制度をいいます。
雇用保険は、労働者が失業した場合などにおいて、その生活の保障などを行うために、政府が運営する公的な保険制度をいい、使用者は、被保険者の要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であるなど)を満たす労働者について雇用保険に加入する義務があります。
社会保険への加入(法人の場合)
常時労働者を使用する法人の事業所は、健康保険および厚生年金保険への加入が義務付けられています(健康保険法第3条第3項第2号、厚生年金保険法第6条第1項第2号)。
労働者数が5人以上の場合(個人事業所の場合)
労働者数が5人以上の場合(個人事業所の場合)
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入
常時5人以上の労働者が働く事務所、工場、商店など、法律が定める17業種に該当する個人事業所は、法律上、健康保険および厚生年金保険への加入が義務付けられています(健康保険法第3条第3項第2号、厚生年金保険法第6条第1項第1号)。
なお、5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、社会保険に加入する義務はありません。
労働者数10人以上の場合(事業場単位)
労働者数10人以上の場合
- 就業規則の作成義務
- 安全衛生推進者または衛生推進者の選任義務
就業規則の作成義務
使用者は、事業場において常時10人以上の労働者がいる場合には、就業規則を作成したうえで、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています(労働基準法第89条)。
就業規則とは、使用者が、労働者の労働条件や服務規律などを定めた規定の総称をいいます。
基準となる10人の労働者数は、使用者単位(企業全体の労働者数)ではなく、事業場単位で判断します。
事業場とは、本店や支店、本社と工場、営業所や出張所など、主に場所的に独立しているかどうかで決定されます。
安全衛生推進者または衛生推進者の選任義務
「安全衛生推進者」とは、安全管理者の選任を要する事業場以外の事業場において、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、安全にかかる業務を担当する者をいいます。
「衛生推進者」とは、衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場において、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生にかかる業務を担当する者をいいます。
使用する労働者の数が、常時10人以上50人未満の事業場であって、安全管理者を選任すべき業種の事業場では安全衛生推進者を選任し、それ以外の事業場では、衛生推進者を選任することが義務付けられています(労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2)。
労働者数50人以上の場合(事業場単位)
労働者数50人以上の場合
- 産業医・安全管理者・衛生管理者の選任義務
- 健康診断結果の報告義務
- ストレスチェックの実施義務
産業医・安全管理者・衛生管理者の選任義務
「産業医」とは、事業場において、労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、労働者の健康管理を行い、専門的立場から指導・助言を行う医師をいいます。
「安全管理者」とは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、安全にかかる技術的事項について管理する者をいいます。
「衛生管理者」とは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生にかかる技術的事項について管理する者をいいます。
産業医と衛生管理者は、業種を問わず、事業場において常時50人以上の労働者を使用する場合に、選任することが義務付けられています(労働安全衛生法第12条第1項・第13条第1項、労働安全衛生法施行令第4条・第5条)。
安全管理者は、屋外的産業、製造工業的産業および商業の業種であって、事業場において常時50人以上の労働者を使用する場合に、選任することが義務付けられています(労働安全衛生法第11条第1項、労働安全衛生法施行令第3条)。
健康診断結果の報告義務
事業場において常時50人以上の労働者を使用する使用者は、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断または歯科医師による健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書(様式第6号)」を所轄の労働基準監督署に提出することが義務付けられています(労働安全衛生規則第52条)。
ストレスチェックの実施義務
事業場において常時50人以上の労働者を使用する使用者は、年に1回、ストレスチェックを実施したうえで、その結果を労働基準監督署に報告することが義務付けられています。
「ストレスチェック」とは、労働者に自身のストレスの状況について気づきを促すために、アンケートなどの調査票を用いて検査を実施することをいいます(労働安全衛生法第66条の10)。
厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の場合
厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の場合
- 短時間労働者の社会保険への加入義務
1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者は、原則として、社会保険に加入する必要はありません。
ただし、例外として、4分の3に満たない場合であっても、雇用する厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業(特定適用事業所)に雇用され、かつ一定の要件(賃金が月額88,000円以上であるなど)を満たす短時間労働者は、社会保険に加入する必要があります(令和4年9月28日保保発0928第5号)。
労働者数101人以上の場合(企業単位)
労働者数101人以上の場合
- 一般事業主行動計画の策定・届出・公表義務
- 女性活躍推進法に基づく情報公表
- 障害者雇用納付金の徴収・障害者雇用調整金の支給
一般事業主行動計画の策定・届出・公表義務
「一般事業主行動計画」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、「計画期間」、「目標」、「目標達成のための対策およびその実施時期」を定めるものをいいます。
労働者数が101人以上(企業単位での労働者数をいいます)の企業は、一般事業主行動計画の策定、届出および公表が義務付けられています(次世代育成支援対策推進法第12条)。
女性活躍推進法に基づく情報公表
労働者数が101人以上(企業単位での労働者数をいいます)の企業は、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行った上で、自社の女性活躍に関する情報を公表することが義務付けられています(女性活躍推進法第8条)。
障害者雇用納付金の徴収・障害者雇用調整金の支給
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などの経済的負担が伴います。
そこで、障害者雇用納付金制度により、障害者の雇用に伴う企業の経済的負担を調整し、その雇用の促進・継続を図るために、常用雇用する労働者の総数が101人以上で、かつ法定雇用障害者数を下回っている企業から「障害者雇用納付金」を徴収する一方で、当該納付金を財源として、法定雇用率を達成している企業に対して「障害者雇用調整金」や「報奨金」などの給付を行っています(障害者雇用促進法第49条第1号、第10号、障害者雇用促進法第53条第1項)。
労働者数301人以上の場合(企業単位)
労働者数301人以上の場合
- 中途採用比率の公表義務
- 男性の育児休業の取得状況の公表義務
中途採用比率の公表義務
常時雇用する労働者数が301人以上の企業は、労働施策総合推進法に基づき、労働者に占める中途採用者の割合を、定期的に公表することが義務付けられています(労働施策総合推進法第27条の2)。
男性の育児休業の取得状況の公表義務
常時雇用する労働者数が301人以上の企業は、年に1回、男性労働者の育児休業の取得状況を公表することが義務付けられています(育児・介護休業法第22条の2)。
公表する内容は、「男性の育児休業等の取得率」または「男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかを選択し、自社のホームページや厚生労働省の運営するウェブサイト「両立支援のひろば」など、インターネットを利用して公表します。