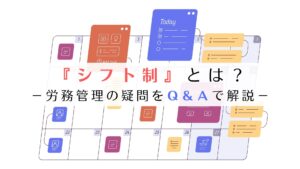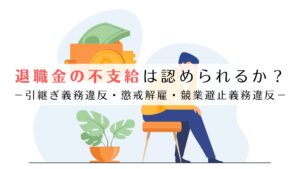【労働基準法】「労働契約の期間」は何年まで?契約期間の上限・下限などを解説
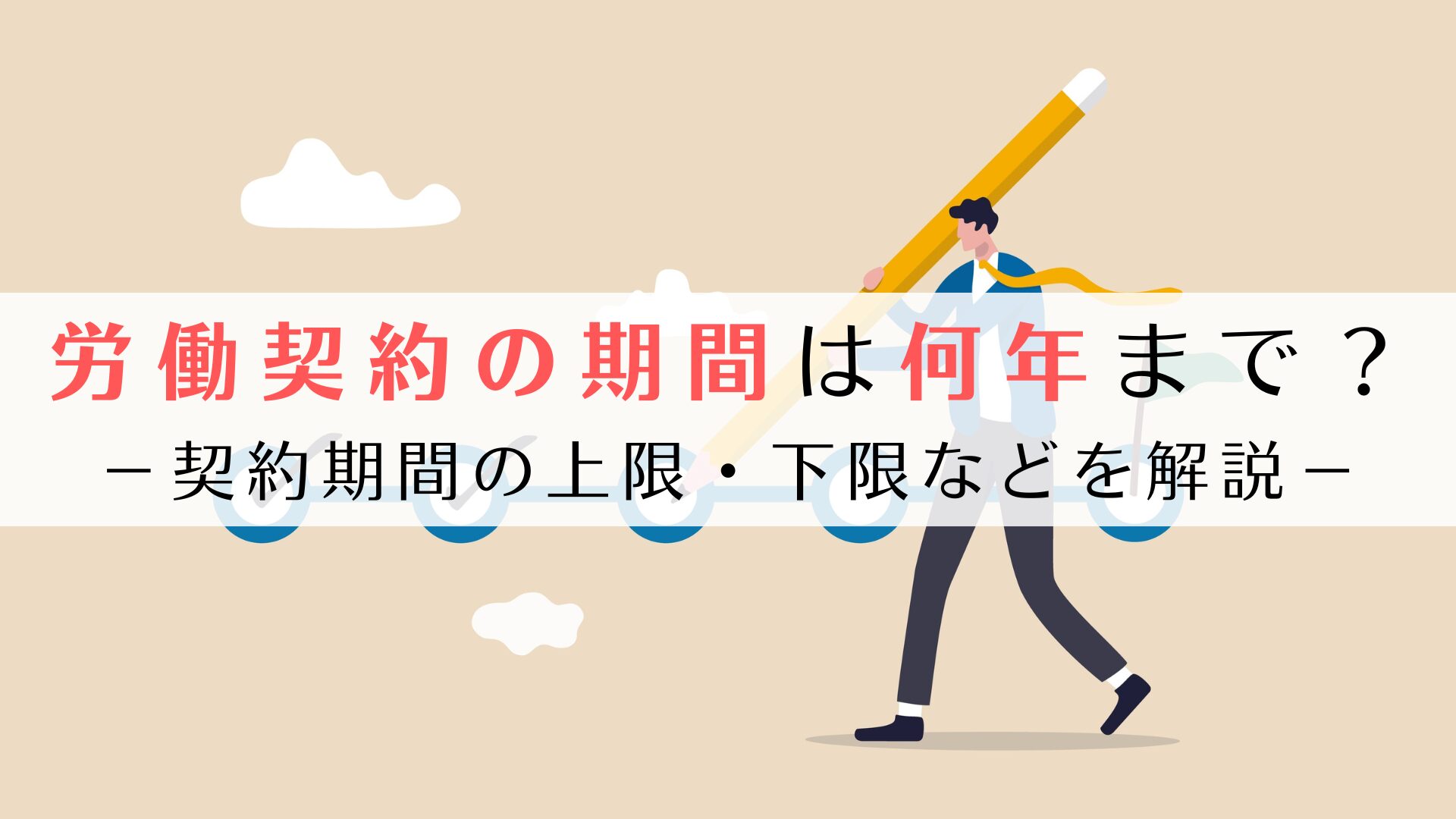
- 1. はじめに
- 2. 有期労働契約と長期人身拘束の防止
- 2.1. 労働契約の種類
- 2.2. 長期人身拘束の防止
- 3. 労働契約の期間の上限【原則】
- 4. 労働契約の期間の上限【例外】
- 4.1. 【例外1】高度の専門的知識等を有する労働者との間の労働契約
- 4.2. 【例外2】満60歳以上の労働者との間の労働契約
- 4.3. 【例外3】一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約
- 4.4. 【例外4】認定職業訓練を受ける労働者との間の労働契約
- 5. 労働契約の期間の下限
- 5.1. 労働契約の期間の下限
- 5.2. 訓示的規定(努力義務)
- 6. 労働契約の期間の途中における解約
- 6.1. 使用者からの解約
- 6.2. 労働者からの解約
- 6.2.1. 原則
- 6.2.2. 例外
- 7. 罰則
はじめに
労働基準法では、長期にわたる労働者の人身拘束を防止するために、労働契約の期間の長さに関する定めが設けられています。
本稿では、労働契約の期間にかかる法規制について、労働基準法を中心に解説します。
有期労働契約と長期人身拘束の防止
労働契約の種類
労働契約を締結する際に、その存続期間を定めるかどうかは、当事者(使用者・労働者)の自由とされています(契約自由の原則)。
存続期間の定めの有無によって、労働契約を分類すると、「無期労働契約」と「有期労働契約」に分かれます。
「無期労働契約」とは、期間を定めずに雇用される契約をいい、一般に、いわゆる正社員が該当します。
「有期労働契約」とは、6ヵ月や1年など、あらかじめ期間を定めて雇用される契約をいい、一般に、パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員などと呼ばれる雇用形態が該当します。
労働契約によって定められた期間が満了した場合、そのまま契約を終了することもあれば、契約を更新して(新たな有期労働契約を締結して)引き続き雇用することもあります。
長期人身拘束の防止
無期労働契約は、労働者がいつでも労働契約を解約できるため、労働基準法では、特に規制は設けられていません。
一方、有期労働契約は、長期の労働契約を締結することによって、労働者の人身拘束に繋がるおそれがあると解されており、労働基準法により、長期人身拘束を防止するために、労働契約の期間の長さに上限が設けられています。
なお、「定年制」は、一般に、無期労働契約を前提として、労働契約の終期(終了事由)を定めたものであり、有期労働契約には該当しないと解されています。
労働契約の期間の上限【原則】
期間を定めて労働契約を締結する場合、労働基準法により、原則として、契約期間の上限は「3年」とされています(労働基準法第14条第1項)。
ただし、これは1回の労働契約における契約期間の上限です。
例えば、1年の労働契約を毎年更新することによって、結果的に3年を超えることは問題ありません。
これは、労働者にとって、契約の更新をするかどうかの判断は自由にできることから、長期人身拘束には当たらないためです。
なお、有期労働契約を締結する場合には、労働条件通知書において、契約期間の定め、契約の更新の有無などを記載する必要があります(労働基準法第15条第1項)。
労働契約の期間の上限【例外】
労働契約の期間の上限については、次のとおり、4つの例外が設けられています。
【労働契約の期間の上限の例外】
| 例外 | 期間の上限 | |
| 1 | 高度の専門的知識等を有する労働者との間の労働契約 | 5年 |
| 2 | 満60歳以上の労働者との間の労働契約 | 5年 |
| 3 | 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約 | 事業の完了まで |
| 4 | 認定職業訓練を受ける労働者との間の労働契約 | 訓練期間の満了まで |
以下、順に解説します。
【例外1】高度の専門的知識等を有する労働者との間の労働契約
専門的な知識、技術または経験(以下、「専門的知識等」といいます)であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、契約期間の上限は、「5年」とされています(労働基準法第14条第1項第1号)。
例外を認める趣旨は、高度の専門的知識等を有する労働者の場合には、労働条件を定める際に、交渉上、使用者に対して劣位な立場となることは少ないといえるため、労働者の意思に反する長期の労働契約が締結される可能性が低いと考えられるためです。
高度の専門的知識等を有する労働者とは、具体的には、次の労働者をいいます(平成24年10月26日厚労告551号)。
高度の専門的知識等を有する労働
- 博士の学位を有する者
- 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士の資格を有する者
- ITストラテジスト試験に合格した者、システムアナリスト試験に合格した者、アクチュアリー試験に合格した者
- 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者、種苗法に規定する登録品種を育成した者
- 農林水産業・鉱工業・機械・電気・土木・建築の技術者、システムエンジニアの業務に就こうとする者、衣服・室内装飾・工業製品・広告等の新たなデザインの考案の業務(デザイナーの業務)に就こうとする者であって、一定の学歴と実務経験(大学卒業後5年、短期大学・高度専門学校卒業後6年、高等学校卒業後7年以上)を有し、年収1,075万円以上の者
- 国、地方公共団体、公益法人等によって、知識等が優れたものと認定された者
ただし、契約期間の上限が5年となるのは、実際に、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限られます。
実際に、労働者を高度の専門的知識等を必要とする業務に従事させていない場合は、例外を適用することは認められません(平成15年10月22日基発第1022001号)。
【例外2】満60歳以上の労働者との間の労働契約
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については、契約期間の上限は、「5年」とされています(労働基準法第14条第1項第2号)。
例外を認める趣旨は、60歳以上の労働者は、一般に雇用の機会の確保が困難な場合があることから、その継続雇用を確保する必要があるためです。
なお、労働契約の締結時に満60歳以上であることが必要です(平成15年10月22日基発第1022001号)。
【例外3】一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約
一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、契約期間の上限は、「事業の完了まで」とされています(労働基準法第14条第1項)。
これは、工事の途中で契約期間が満了すると、工事の続行に支障が生じるなどといった不都合が生じるためです。
「一定の事業の完了に必要な期間を定める」とは、例えば、ダム建設や道路建設などの有期事業をいいます。
例えば、工事の完成までに6年を要する場合には、6年間の労働契約を締結することが認められます。
【例外4】認定職業訓練を受ける労働者との間の労働契約
認定職業訓練を受ける労働者との間の労働契約については、契約期間の上限は、「訓練期間の満了まで」とされています(労働基準法第70条、同施行規則第34条の2の5)。
職業能力開発促進法に基づき、都道府県労働局長の許可を受けた使用者は、都道府県知事の認定を受けて職業訓練(認定職業訓練)を行うことができます。
「認定職業訓練」とは、職業能力開発促進法に基づき、事業主等の行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定める基準に適合して行われているものであって、申請により訓練基準に適合している旨の都道府県知事の認定を受けた職業訓練をいいます(職業能力開発促進法第24条第1項)。
この認定職業訓練を受ける労働者の労働契約期間は、認定職業訓練を可能にさせる趣旨から、当該訓練生が受ける訓練職種について、職業能力開発促進法施行規則に定める訓練期間の範囲内で定めることができます。
労働契約の期間の下限
労働契約の期間の下限
労働契約の期間の下限については、特に規制はありません。
例えば、1日、1週間、1ヵ月などといった短期の労働契約を締結することも可能です。
労働市場では、実際に1日から数日といったスポット的な需要も多数存在し、また、このような労働を求める労働者も相当数存在するため、労働契約の下限については、特に規制は設けられていません。
訓示的規定(努力義務)
「雇止めに関する基準」により、使用者は、有期労働契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している労働者との契約を更新しようとする場合は、その契約の実態および労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない(努力義務)とされています(雇止めに関する基準第4条)。
また、「労働契約法」では、使用者は、その有期労働契約により労働者を雇用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないように配慮しなければならないとされています(労働契約法第17条第2項)。
労働契約の期間の途中における解約
使用者からの解約
使用者が有期労働契約に基づき雇用している労働者について、その契約期間の途中において解約(解雇)する場合には、労働契約法により、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないと定められています(労働契約法第17条)。
裁判例では、「やむを得ない事由」とは、客観的に合理的な理由および社会通念上相当である事情に加えて、当該雇用を終了させざるを得ない特段の事情と解するのが相当であるとしています(仙台高等裁判所平成24年1月25日判決)。
労働者からの解約
原則
有期労働契約を労働者から一方的に解約する場合、民法の定めに従い、「やむを得ない事由」があるときは、直ちに契約の解除をすることができるとされています。
ただし、解約する場合において、その事由が労働者の過失によって生じたものであるときは、使用者に対して損害賠償の責任を負うとされています。
例外
民法の定めに関わらず、期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(期間について5年の例外が適用される労働者を除く)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず(やむを得ない事由がなくても)、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができるとされています(労働基準法附則第137条)。
罰則
使用者が、労働基準法が定める労働契約の期間を超えて契約をした場合には、罰則として、30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条第1号)。
労働基準法では、同法が定める期間を超える労働契約を「締結してはならない」と定めていることから、上限期間を超える契約を締結した時点で、罰則の対象になると解されます。
なお、罰則の適用については、労働基準法の定めが長期人身拘束を防止する趣旨であることから、使用者に対してのみ罰則が科されます(労働者は罰則の対象とはなりません)(昭和23年4月5日基発535号)。