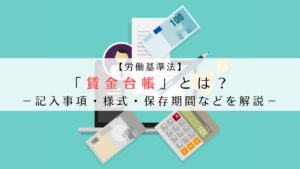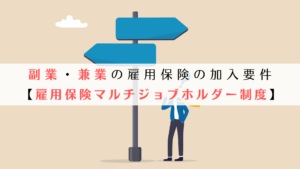【労働基準法】「退職」「解雇」の前後で適用される労働基準法の定めをまとめて解説
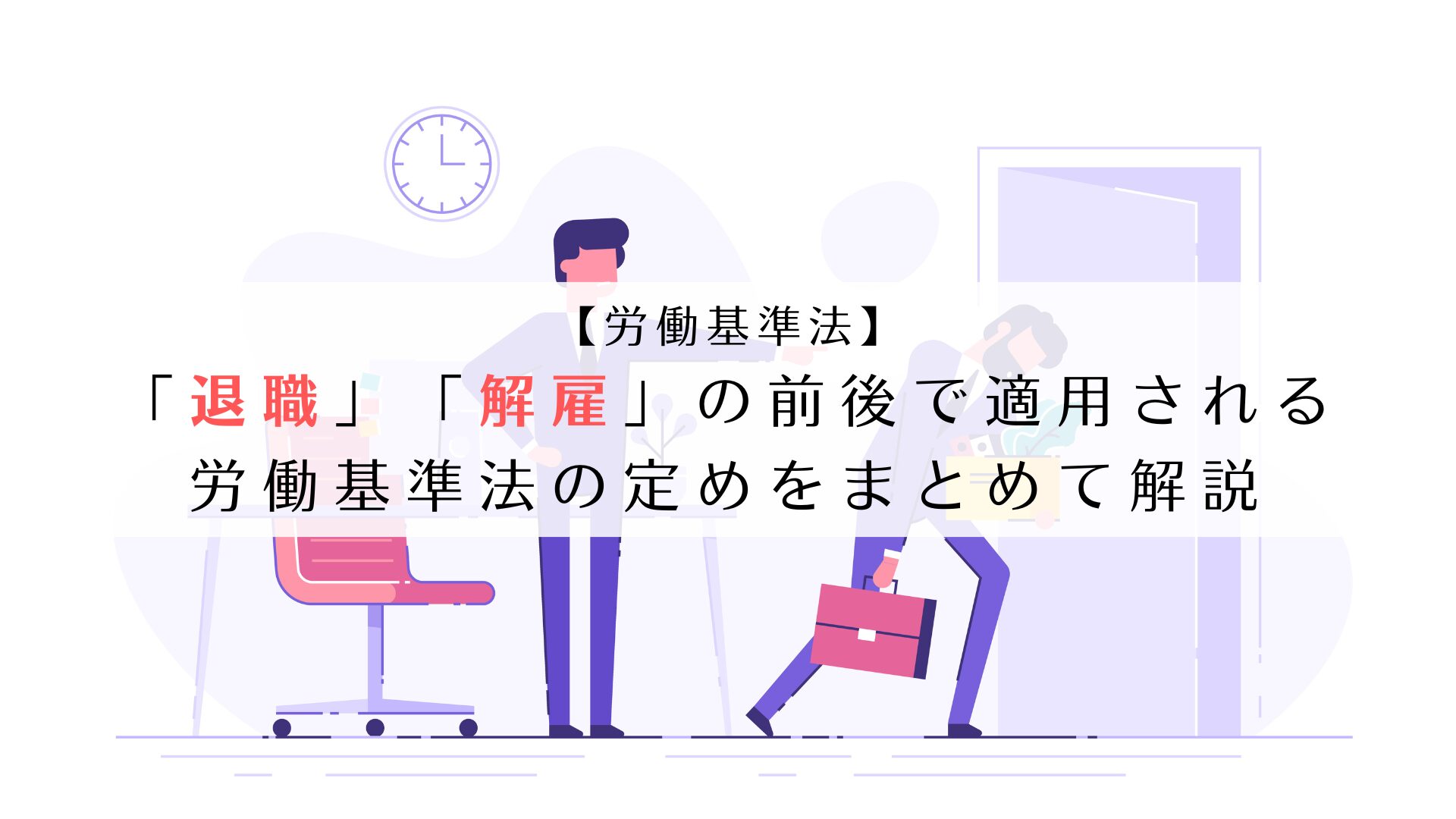
はじめに
労働基準法では、労働者を保護するために、労働者の退職・解雇の前後において適用される定めがあります。
本稿では、労働者の退職・解雇の前後において適用される労働基準法の定めを、まとめて解説します。
帰郷旅費
労働条件が事実と相違する場合の帰郷旅費
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労働基準法第15条第1項)。
これを受けて、一般に、労働者を雇入れる際には、労働条件通知書を交付することによって、労働条件を明示します。
そして、労働者保護の観点から、明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができるとされています(労働基準法第15条第2項)。
なお、雇入れ後に就業規則が変更された場合や、労働者の同意を得て労働条件を変更した場合には、「事実と相違する場合」には当たらないと解されます。
さらに、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は、必要な旅費を負担しなければならないとされています(労働基準法第15条第3項)。
「帰郷」とは、通常、就業する直前に労働者が居住していた場所まで帰ることをいいますが、必ずしもこれのみに限定されるものではなく、父母その他親族の保護を受ける場合には、その者の住所に帰る場合も含まれます(昭和23年7月20日基収2483号)。
「必要な旅費」とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の費用をいい、交通費のほか、食費、宿泊費も含まれます。
また、労働者とともに、その労働者により生計を維持されている同居の親族(内縁の配偶者を含む)が転居する場合には、その者の旅費なども含まれます(昭和22年9月13日発基17号)。
年少者の帰郷旅費
使用者が満18歳に満たない者を解雇する場合において、その者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は、必要な旅費を負担しなければならないとされています(労働基準法第64条)。
ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について、帰郷旅費支給除外認定申請書(様式第4号)により申請を行い、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、帰郷旅費を負担する必要はありません(労働基準法第64条但書、年少者労働基準規則第10条)。
解雇制限
原則
労働基準法では、使用者は、①労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、その療養のために休業する期間中およびその後30日間、②女性労働者の産前産後休業期間中およびその後30日間は解雇してはならないと定められており、これを「解雇制限」といいます(労働基準法第19条第1項)。
なお、①については、あくまで業務上の負傷・疾病が対象となるものであり、私傷病については、法律による解雇制限の対象とはなりません。
例外
解雇制限には、例外が設けられており、次のいずれかに該当する場合には、解雇制限が解除され、解雇制限期間中であっても、解雇することができる(解雇することが法律上禁止されなくなる)とされています(労働基準法第19条第1項但書)。
解雇制限の例外
- 打切補償を支払う場合
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(所轄労働基準監督署長の認定を受けることが必要)
「打切補償」とは、業務上の負傷または疾病により、療養補償を受けている労働者が、その療養開始から3年を経過しても傷病が治らない場合に、使用者が平均賃金の1,200日分を支払うことによって、その後の補償を打ち切ることをいいます(労働基準法第81条)。
なお、業務上の負傷または疾病により、療養補償を受けている労働者が、その療養開始から3年を経過した日において、労災保険による傷病補償年金を受けている場合(同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合を含む)には、使用者は労働基準法に基づく打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されることとなります(労災保険法第19条)。
解雇の手続
原則
使用者が労働者を解雇する場合には、労働基準法によって、解雇までに次のいずれかの手続を行う必要があります(労働基準法第20条)。
解雇の手続
- 解雇をする30日以上前に「解雇予告」をすること
- 平均賃金の30日分以上の「解雇予告手当」を支払うこと
つまり、使用者が労働者を解雇する場合には、30日以上前に解雇の日を予告しておく必要があり、もし直ちに(予告をしないで)解雇をしようとする場合には、解雇予告手当を支払う必要があります。
なお、解雇予告と解雇予告手当は併用することができ、例えば、解雇の日の15日前に、15日分の解雇予告手当を支払って解雇する、ということも認められます。
例外
労働基準法では、あらかじめ労働基準監督署の認定(除外認定)を受けることによって、前述の解雇予告の手続を行わないことを認めています。
労働基準法により、解雇予告の除外認定が認められるのは、次の2つの場合に限られています(労働基準法第20条但書)。
解雇予告の除外認定が認められる場合
- 天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
有期労働契約を雇止めする際の予告手続
使用者が次に該当する有期労働契約の契約を更新しない場合には、契約期間満了日の30日前までに予告をしなければならないとされています(雇止めに関する基準第2条)。
ただし、あらかじめ契約を更新しない旨を明示している場合を除きます。
契約の不更新時に予告を要する場合
- 3回以上契約が更新されている場合
- 雇入れの日から1年を超えて継続勤務している場合
退職時の証明書・解雇理由の証明書
退職時の証明書
労働基準法では、労働者が退職する場合において、下記の事項について、証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないとされています(労働基準法第22条第1項)。
退職時の証明書を交付する趣旨は、解雇など退職をめぐる紛争の防止や、労働者の再就職に役立たせるためと解されます。
退職時の証明書への記載事項
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 賃金
- 退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、解雇の理由を含む)
退職時の証明書について、詳細は、次の記事をご覧ください。
【労働基準法】「退職時の証明書」「解雇理由の証明書」への記載事項、ひな型(書式例)、作成時のポイントを解説
解雇理由の証明書
労働基準法では、使用者による解雇の予告がされた日から、退職の日までの間において、労働者が当該解雇の理由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないとされています(労働基準法第22条第2項)。
解雇理由の証明書を作成する趣旨は、解雇をめぐる紛争を未然に防止するためと解されます。
通信等の禁止
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、退職時の証明書および解雇理由の証明書において、秘密の記号を記入してはならないとされています(労働基準法第22条第4項)。
これは、労働者の就職を妨害することを目的とした、いわゆるブラックリストの作成を禁止する趣旨と解されます。
罰則
退職時の証明書および解雇理由の証明書の規定に違反した場合には、30万円以下の罰金が定められています(労働基準法第120条第一号)。
また、通信等の禁止の規定に違反した場合には、6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(労働基準法第119条第一号)。
金品の返還
使用者は、労働者が死亡し、または退職する場合において、権利者から請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないとされています(労働基準法第23条第1項)。
これは、あくまで権利者から請求があった場合に適用される定めであり、特に権利者から請求がない場合には、就業規則などによって定められた所定の賃金支払日に支払えば足ります。
「権利者」とは、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は労働者の遺産相続人をいい、一般債権者は含まれません(昭和22年9月13日発基17号)。
もし、所定の賃金支払日が権利者からの請求があった日から7日目より前の日であるときは、賃金はその所定の賃金支払日に支払う必要があります。
退職手当(退職金)については、必ずしも7日以内に支払う必要はなく、あらかじめ就業規則などで定められた支払時期に支払えば足りると解されます(昭和63年3月14日基発150号)。
なお、返還の対象となる賃金または金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、または返還しなければならないとされています(労働基準法第23条第2項)。