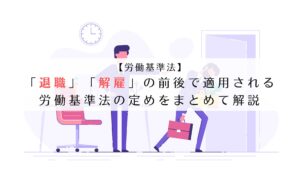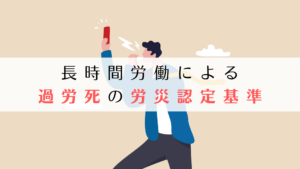副業・兼業をする場合の雇用保険の加入要件を解説【雇用保険マルチジョブホルダー制度】
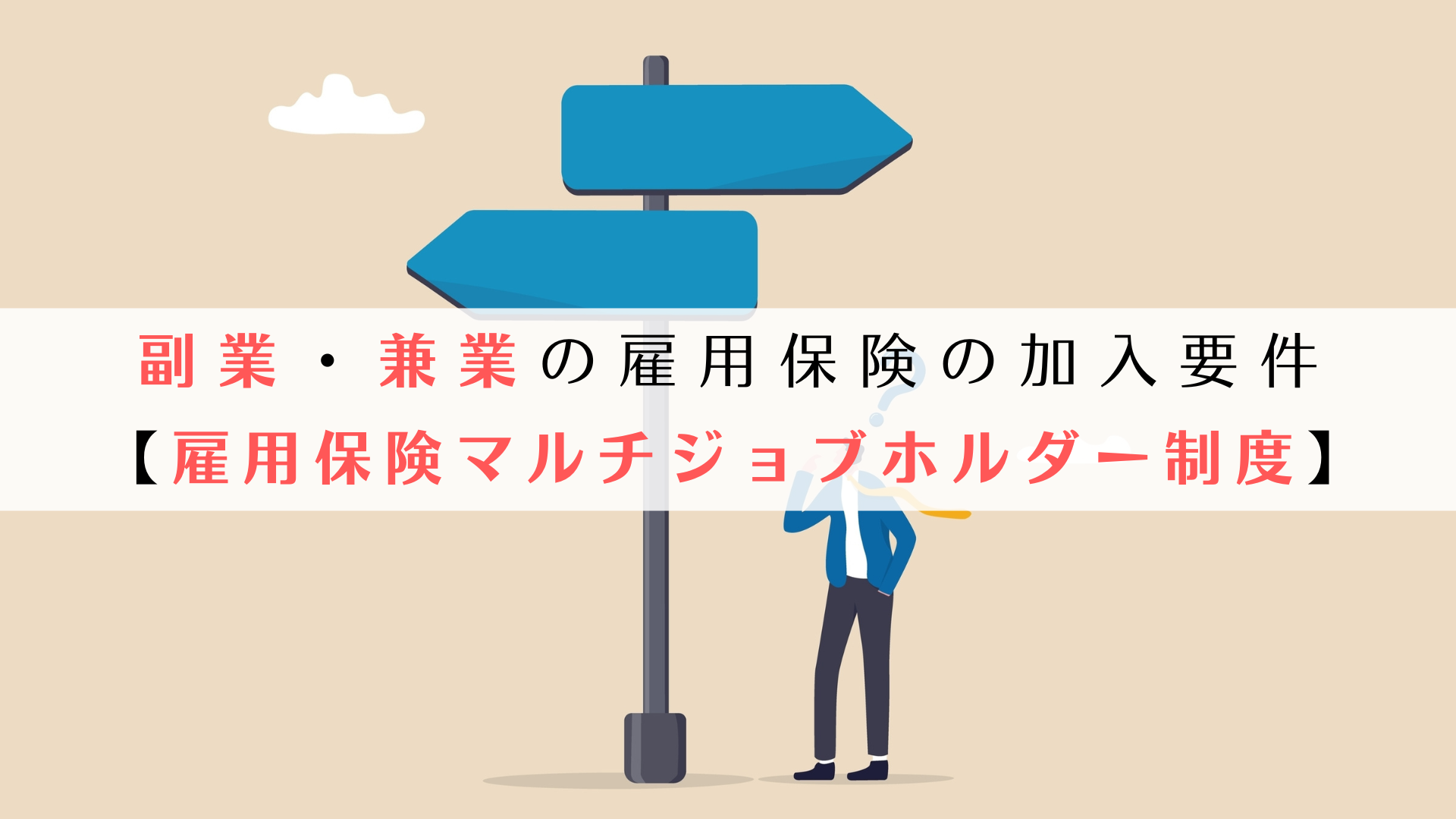
雇用保険とは
「雇用保険」とは、労働者の失業、高齢化、育児・介護などにより、その雇用の継続が困難となる事情が生じた場合に、その労働者に対して必要な生活保障を行うことにより、労働者の生活と雇用の安定を図ることを目的とした社会保険です。
例えば、雇用保険の代表的な給付として、労働者が失業した場合に支給される「基本手当」がありますが、これは、労働者が失業した場合に、再就職するまでの求職活動中の生活を保障するための給付です。
雇用保険は、政府が管掌する社会保険(一般に、労災保険と併せて「労働保険」といいます)であり、その申請手続については、全国各地のハローワーク(公共職業安定所)が窓口となっています。
雇用保険の加入要件(被保険者となる要件)
会社は、原則として、従業員が次の要件をいずれも満たす場合には、当該従業員について雇用保険に加入する義務があります(雇用保険法第6条)。
雇用保険の加入要件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上雇用されることが見込まれること
上記の要件は、雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)に関係なく適用されます。
したがって、パートやアルバイトであっても、上記の要件に該当する場合には、雇用保険に加入する義務があります。
ただし、学生は、原則として雇用保険に加入することはできません。
なお、要件にある「1週間の所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書などにより、その従業員が「通常の週」に勤務すべきとされている時間のことをいい、ここでいう「通常の週」とは、祝祭日、年末年始、夏季・冬季休暇などを含まない週をいいます(雇用保険に関する業務取扱要領20303)。
【原則】副業・兼業をする場合の取り扱い
従業員が兼業・副業により、2以上の事業所を掛け持ちして働く場合には、それぞれの勤務先における所定労働時間を把握した上で、雇用保険の加入要件を判断する必要があります。
兼業・副業先の所定労働時間が、いずれも週20時間以上
2以上の事業所に雇用されている従業員で、いずれの会社も所定労働時間が週20時間以上である場合、雇用保険は二重加入することは認められないことから、すべての事業所で雇用保険に加入するのではなく、そのうち1つの事業所についてのみ雇用保険に加入することとなります。
この場合、原則として、その従業員が生計を維持するために必要な、主たる賃金をうけている雇用関係についてのみ、雇用保険に加入することとなります(雇用保険に関する業務取扱要領20352)。
なお、個人事業主(フリーランス)は雇用保険の被保険者になりませんので、従業員が副業・兼業として自ら事業を営んでいる場合には、当該事業について雇用保険に加入することはありません。
事例1
【事例1】
A事業所の所定労働時間…週20時間/賃金…月15万円
B事業所の所定労働時間…週30時間/賃金…月30万円
【結論】
B事業所で雇用保険に加入する。
上記の例では、B事業所の方が賃金が多い(15万円<30万円)ため、主たる賃金は、B事業所から受け取っているものと解されます。
したがって、この場合は、B事業所で雇用保険に加入する必要があります。
兼業・副業先の所定労働時間が、いずれか1事業所だけが週20時間以上
事例2
【事例2】
A事業所の所定労働時間…週10時間
B事業所の所定労働時間…週20時間
【結論】
B事業所で雇用保険に加入する。
上記の例では、A事業所では雇用保険の加入要件を満たさず(10時間<20時間)、B事業所では雇用保険の加入要件を満たしている(30時間>20時間)ことから、B事業所で雇用保険に加入する必要があります。
兼業・副業先の所定労働時間が、いずれも週20時間未満
事例3
【事例3】
A事業所の所定労働時間…週15時間
B事業所の所定労働時間…週15時間
【結論】
雇用保険に加入しない。
上記の例では、いずれの事業所も週20時間に達していない(15時間<20時間)ことから、雇用保険に加入することはできません。
しかし、2つの会社の所定労働時間を通算すれば、週30時間(15時間+15時間)になり、雇用保険の加入要件を満たす程度に働いている以上は、副業・兼業をしている従業員についても、何らかの保護が必要ではないか、とも考えられます。
そこで、2022(令和4)年1月1日施行の法改正により、65歳以上の者を対象に、一定の要件を満たす場合には、兼業・副業先の所定労働時間が、いずれも週20時間未満である場合であっても、雇用保険に加入することができるようになりました。
【例外】兼業・副業先の所定労働時間が、「いずれも週20時間未満」である場合の雇用保険の加入要件【雇用保険マルチジョブホルダー制度】
前述のとおり、兼業・副業先の所定労働時間が、いずれも週20時間未満である場合には、原則として雇用保険に加入することができませんが、一定の要件を満たす場合には、雇用保険に加入することができます。
これを、通称「雇用保険マルチジョブホルダー制度」といいます。
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の高年齢労働者が、2つの事業所での勤務を合計して、次の要件を満たす場合には、本人からハローワークへの申し出に基づき、申し出を行った日から雇用保険に加入する(マルチ高年齢被保険者になる)ことができる制度です(雇用保険法第37条の5)。
雇用保険マルチジョブホルダー制度への加入要件
- 複数の事業所(2事業所以上)に雇用される、65歳以上の者であること
- 1つの事業所における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
- 2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
ただし、3.について合計することができるのは、1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限られます(雇用保険法施行規則第65条の7)。
なお、雇用保険に加入できるのは、2つの事業所までです。
3つ以上の事業所で勤務している場合は、本人が雇用保険に加入する2つの事業所を選択します。
手続
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、通常の雇用保険と異なり、要件を満たすと必ず加入しなければならないものではなく、加入を希望する従業員本人から申し出を行うことが必要です。
要件に該当する従業員が雇用保険に加入するための申し出は、必要事項を記載した届書に、労働契約にかかる契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第10号の2)と併せて、管轄公共職業安定所に提出することによって行うものとされています(雇用保険法施行規則第65条の6第1項)。
通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主である会社が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、従業員本人が手続を行う必要がある点が異なります。
なお、申し出にあたり、会社の同意は必要ありません。
事業主の義務
会社は、マルチジョブホルダーが雇用保険の資格の取得・喪失手続を行う際に、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行わなければなりません(雇用保険法施行規則第65条の6第4項)。
また、会社は、マルチジョブホルダーが申し出をしたことを理由として、解雇や雇止め、労働条件を不利益に変更するなど、不利益な取り扱いを行ってはならないこととされています(雇用保険法第73条)。
なお、マルチ高年齢被保険者が雇用保険の資格を取得すると、資格を取得した日(※)から雇用保険料の納付義務が生じます。
(※)ハローワークから事業主に対し、「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」が送付され、当該通知書に資格取得日が記載されています。
失業した場合の給付
マルチ高年齢被保険者であった者が失業した場合には、一定の要件を満たすことにより、「高年齢求職者給付金」(一時金)を受給することができます。
給付額は、原則として、賃金日額(離職日以前6ヵ月に支払われた賃金の合計を、180で割って算出した額)の50%から80%を「基本手当日額」として決定します。
そして、被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分、被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当日額の50日分が支給されます。
高年齢求職者給付金は、2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも、その事業所の賃金に基づいて算出された額を受給することができます。
ただし、3以上の事業所で就労しており、離職をしていない2つの事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者への加入要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、給付金を受給することはできません。