遅刻(欠勤)、時間単位年休を取得した日に残業した場合の、割増賃金(残業代)の支払い義務を解説【労働基準法】
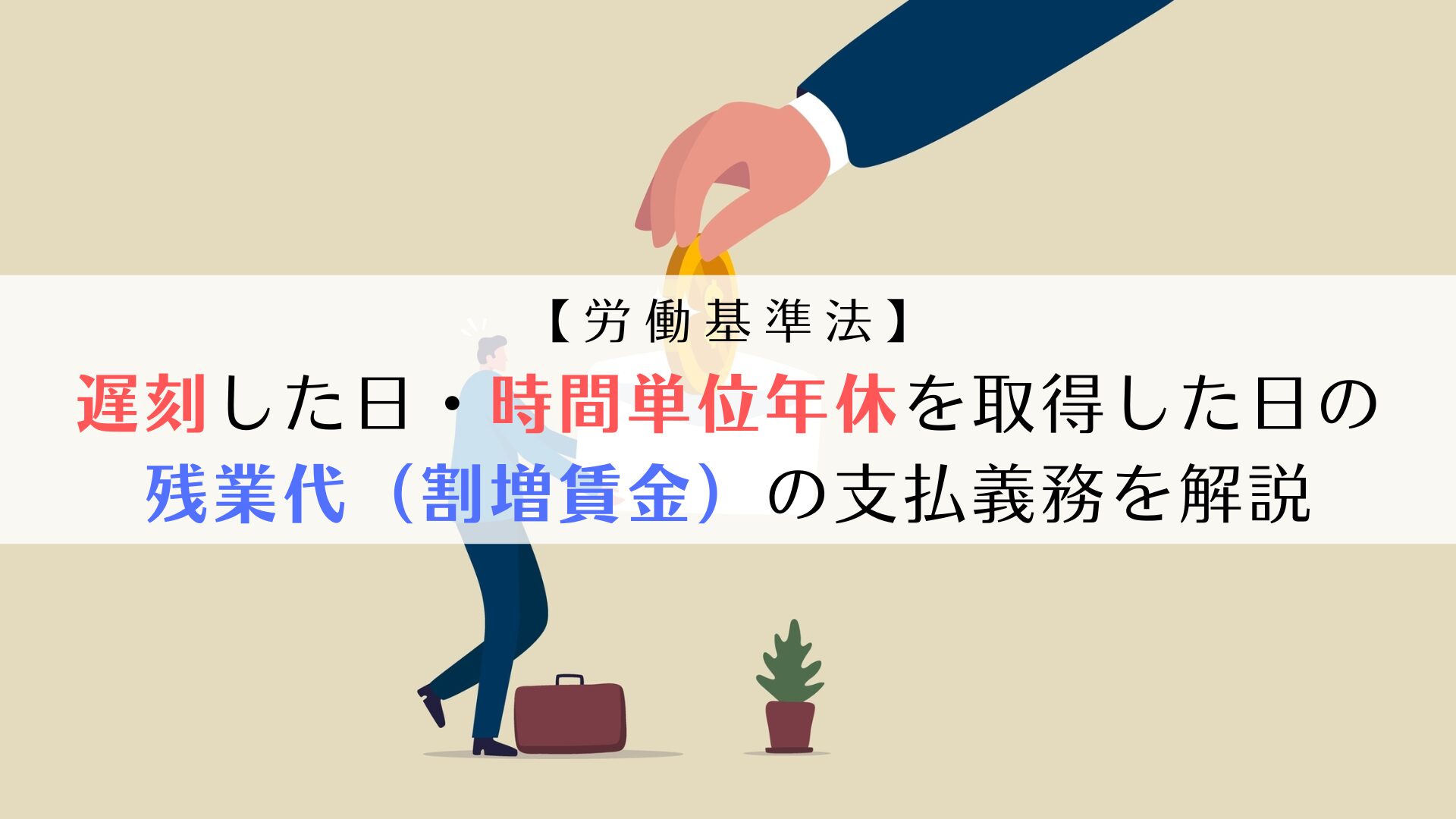
はじめに
労働基準法では、原則的な労働時間として、「法定労働時間」を定めており、従業員が法定労働時間を超えて労働した場合には、会社に対し、割増賃金を支払うことを義務付けています。
本稿では、従業員が、遅刻(欠勤)をし、または半日単位や時間単位で年次有給休暇を取得したことによって、1日の労働時間の一部について就労せず、その後残業をしたケースにおいて、会社がどのように割増賃金を支払うべきかを解説します。
法定労働時間と割増賃金
法定労働時間とは
「法定労働時間」とは、労働基準法が定める原則的な労働時間をいいます。
労働基準法では、原則として、「法定労働時間を超えて労働者を働かせてはならない」と定めており、このことから法定労働時間とは、いわば労働時間の上限時間といえます。
労働基準法では、法定労働時間として、次の2つの時間を定めています(労働基準法第32条)。
法定労働時間
- 1日8時間
- 1週40時間(※)
(※)労働基準法による労働時間の特例が認められる事業については、1週の法定労働時間は「44時間」になります。
労働時間の特例が認められる事業とは、常時10人未満の従業員を使用する、商業(卸売業、小売業など)、映画・演劇業(映画製作業を除く)、保健衛生業(病院、診療所など)、接客娯楽業(旅館、飲食店など)をいいます。
割増賃金とは
従業員が法定労働時間を超えて働く場合、会社は、従業員の過半数を代表する者との間で、書面による協定(通称、「36(さぶろく)協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることにより、法定労働時間を超えて働くことが可能となります(労働基準法第36条)。
このとき、法定労働時間を超えて働くことを、「時間外労働(または法定時間外労働)」といいます(本稿では、「法定時間外労働」といいます)。
会社は、従業員が法定時間外労働をした場合、その時間に対して、通常の賃金に25%以上を割り増しした「割増賃金」を支払う必要があります(労働基準法第37条)。
例えば、時給が1,000円の従業員であれば、法定時間外労働1時間あたり1,250円(1,000円+250円)以上を支払う必要があります。
なお、法定時間外労働が1ヵ月に60時間を超える場合には、その時間に対しては、通常の賃金に50%以上を割り増しする必要があります。
従業員が遅刻(欠勤)した日の時間外労働と割増賃金
事例
事例
- 1日の所定労働時間は8時間
- 従業員が1時間遅刻をし、所定労働時間の終了後(終業時刻後)に1時間の残業をした
- 従業員の時給は1,000円
- 割増賃金の割増率は25%
上記の事例では、遅刻をした従業員が1日に働いた労働時間は8時間であり、結果的に、遅刻をせずに所定労働時間を働いた場合と同じ時間となっています。
このとき、従業員の割増賃金の取り扱いについて、次の選択肢が考えられます。
割増賃金の取り扱いの選択肢
- 【A】1日で働いた時間は、所定労働時間と同じである点に着目し、通常どおり出勤したものとして取り扱い、割増賃金は支払わず、遅刻に対する賃金の控除もしない
- 【B】1時間分の割増賃金1,250円(1,000円×125%)を支払いつつ、1時間の遅刻に対して1時間分の賃金1,000円を欠勤控除し、差額250円(1,250円-1,000円)を支払う
原則的な取り扱い
原則的には、上記の選択肢のうち、【A】のとおり取り扱うこととなります。
労働基準法では、「1日において、8時間を超えて労働させてはならない」と定めており、これを超える労働に対して、割増賃金を支払うことを義務付けています。
つまり、労働基準法上、割増賃金を支払わなければならない法定時間外労働とは、所定の始業時刻・終業時刻の前後の労働を意味するものではなく、1日の実労働時間として、8時間を超える労働を意味するものと解されます。
したがって、1時間遅刻し、1時間残業をした従業員は、始業時刻と終業時刻がそれぞれ1時間遅くなっただけであり、実労働時間の長さは、結果的に法定労働時間と同じであることに着目し、割増賃金の対象となる法定時間外労働がなかったものとして取り扱うこととなります。
実労働時間主義
行政通達では、法定労働時間と割増賃金の関係性について、次のように示しており、このように、法定労働時間を超えるかどうか(割増賃金の支払い義務があるかどうか)について、実労働時間に着目して判断する考え方を、「実労働時間主義」といいます。
行政通達(昭和29年12月1日基収6143号)
法第32条(労働時間)または法第40条(労働時間及び休憩の特例)に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条1項に基く協定及び法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に基く割増賃金の支払いを要するのは、実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。
従って、例えば労働者が遅刻をした場合、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算すれば法第32条(労働時間)または法第40条(労働時間及び休憩の特例)の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基く協定及び法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に基く割増賃金の支払いの必要はない。
その他の考え方
実務上の取り扱いとしては、【B】の考え方(1時間分の割増賃金を支払いつつ、1時間の遅刻に対して1時間分の賃金を欠勤控除する)によることも可能です。
この考え方では、賃金計算の対象を、①始業時刻から終業時刻までの時間(所定労働時間帯)と、②それ以外の時間(残業時間帯)の2つに分けた上で、①に対しては「100%の賃金(通常賃金)×時間数」、②に対しては「125%の賃金(割増賃金)×時間数」を支払うことによって、画一的に賃金を計算します。
そして、①の時間について遅刻・早退・欠勤があった場合には、ノーワークノーペイの原則(従業員が労務を提供しない場合には、会社はその対価である賃金を支払う必要がないという考え方)に基づき、賃金の「控除」を行います。
また、②の時間について労働した場合は、すべて②の割増賃金を支払います(なお、厳密には、所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合には、法定労働時間を超える時間から割増賃金の支払い義務が生じます)。
このように、所定労働時間の範囲内であるのか、または範囲外であるのかによって、画一的に割増賃金を支払う考え方を、「所定労働時間主義」ということがあります。
【B】によれば、事例のように遅刻時間と残業時間が同じ場合には、125%の割増賃金を支払った上で、100%の欠勤控除を行うため、差額の25%が従業員に支払われることになりますので、金銭面では、【A】と比べて従業員に有利となります。
会社は余計な割増賃金を支払うように見えますが、【B】のように処理することで、会社にとっても給与計算事務の簡素化に繋がるなどのメリットが生じることがあります。
なお、【A】または【B】のいずれの方法による場合でも、遅刻をしたこと自体について、懲戒処分など制裁の対象となり、または人事評価への影響が生じ得る点については、別の問題となります。
従業員が1時間単位の年次有給休暇を取得した日の時間外労働と割増賃金
1時間単位の有給休暇(時間単位年休)とは
労働基準法では、1時間を単位とした年次有給休暇(以下、「時間単位年休」といいます)の取得を認める制度があります。
例えば、1日の所定労働時間が8時間の会社において、1時間単位で時間単位年休を取得する場合、従業員は1日分の年次有給休暇を8分割して、休暇を取得することができます。
時間単位年休の制度については、次の記事をご覧ください。
1時間単位の有給休暇(時間単位年休)とは?制度の内容・労使協定の記載例を解説
事例
事例
- 1日の所定労働時間は8時間
- 従業員が1時間の時間単位年休を取得し、所定労働時間の終了後(終業時刻後)に1時間の残業をした
- 従業員の時給は1,000円
- 時間単位年休を取得した時間に対する賃金は1,000円(通常賃金)
- 割増賃金の割増率は25%
上記の事例では、時間単位年休を取得した従業員が1日に働いた労働時間は8時間であり、結果的に、所定労働時間を働いた場合と同じ時間となっています。
一見すると、従業員は、遅刻のように職場の規律に違反したのではなく、法律に基づく権利の行使として時間単位年休を取得しており、かつ、その時間に対しては賃金が支払われることから、これを遅刻と同じように取り扱うことには問題があるようにも思います。
しかし、前述の「実労働時間主義」の考え方によれば、どのような理由に基づくものであれ、1日の実労働時間が法定労働時間を超えない限りは、割増賃金の支払い義務が生じないことに変わりはありません。
そもそも、割増賃金の趣旨は、長時間の労働をした従業員に対する補償であり、時間単位年休を取得したことで、現実に長時間の労働に従事していない場合には、その補償を行う必要はないと考えられます。
支払うべき賃金
この事例では、時間単位年休を取得した1時間に対しては、1,000円を支払い、さらに、終業時刻後の1時間の労働時間に対しては、割り増しをしない通常賃金1,000円を支払うこととなりますので、会社が支払う1日の賃金は9,000円(1,000円×9時間)となります。
その他の場合
上記の取り扱いは、従業員が、半日単位で年次有給休暇を取得した場合や、1日の一部について代替休暇(労働基準法第37条第3項)を取得した場合などにおいても同様です。
また、会社の責めに帰すべき事由により、1日の一部について休業(労働基準法第26条)した場合も、実際に労働に従事していませんので、同様です。
なお、欠勤はともかくとして、年次有給休暇など法律上の権利の行使に基づく場合には、当該時間は現実に労働したものとして取り扱い、割増賃金を支給することは差支えなく、むしろ従業員保護の観点からは望ましい取り扱いといえます。


