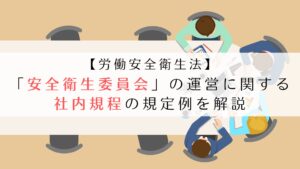【労働安全衛生法】「安全委員会」「衛生委員会」の設置要件、委員の構成、審議事項など、基本的な内容を解説
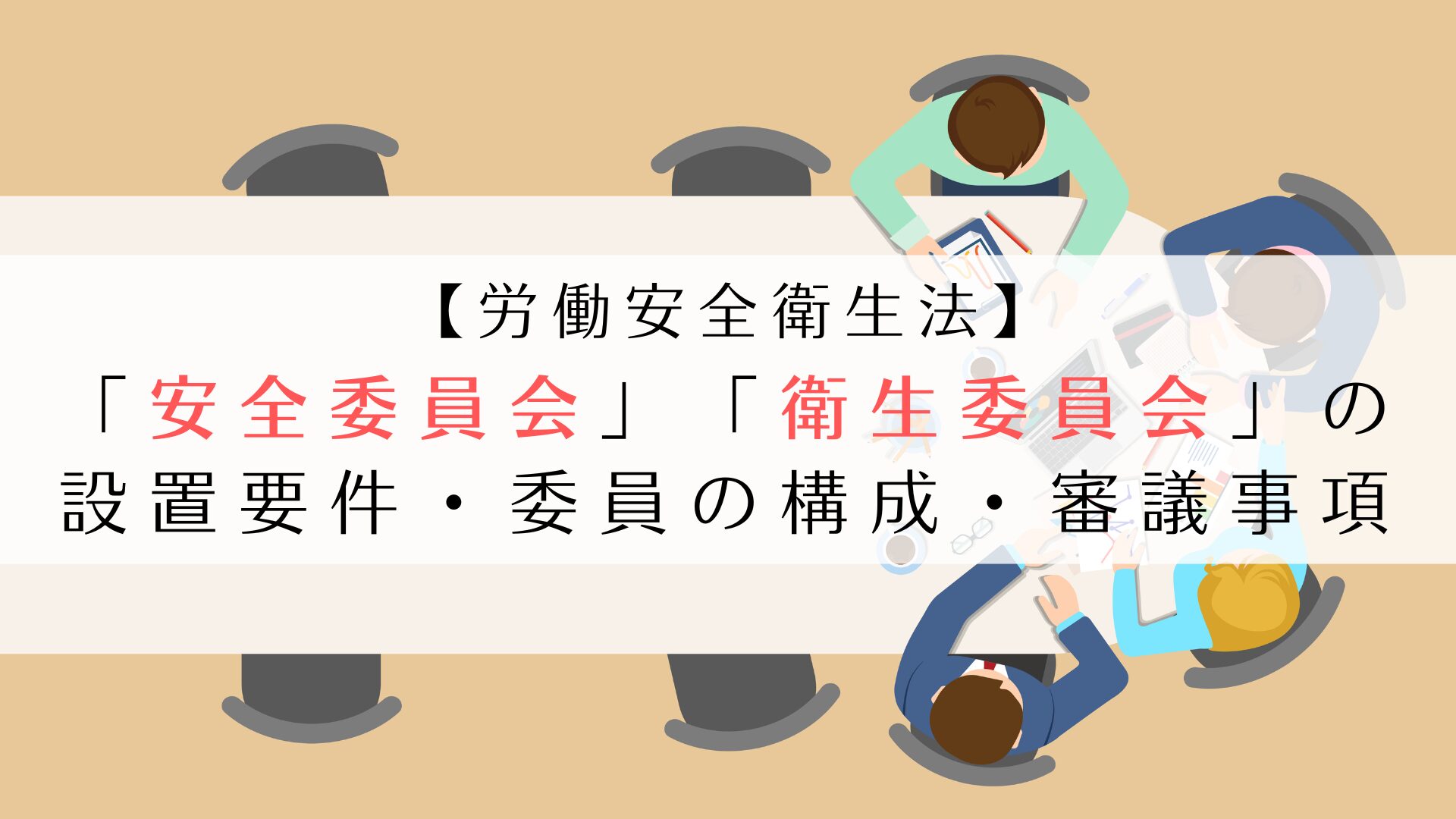
はじめに
労働安全衛生法では、事業場の業種および規模に応じ、安全衛生に関する調査・審議を行うための機関として、「委員会」の設置を義務付けています。
本稿では、労働安全衛生法が設置を義務付けている委員会について、設置要件、委員の構成、審議事項など、基本的な内容を解説します。
なお、安全衛生に関する基本的な管理体制(安全管理者、衛生管理者の選任など)については、次の記事をご覧ください。
【労働安全衛生法】安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者などの選任義務・職務内容)の基本について解説
安全委員会
安全委員会
「安全委員会」とは、事業場の労働者の危険の防止などに関する重要事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べることを目的として、法令で定める業種および規模に該当する事業場において、設置が義務付けられている組織をいいます(労働安全衛生法第17条第1項)。
安全委員会の設置を要する事業場(設置要件)
事業者は、業種および規模が次の要件に該当する事業場において、安全委員会を設置することが義務付けられています(労働安全衛生法施行令第8条)。
| 業種 | 規模(使用労働者数) |
| [屋外的産業] 林業、鉱業、建設業、清掃業 運送業のうち道路貨物運送業、港湾運送業 [製造工業的産業] 製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業 自動車整備業、機械修理業 | 常時50人以上 |
| [屋外的産業] 運送業(上記の業種を除く) [製造工業的産業] 製造業(物の加工業を含み、上記の業種を除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業 [商業等] 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 常時100人以上 |
安全委員会の委員の構成
安全委員会の委員は、次の者をもって構成する必要があります(労働安全衛生法第17条第2項)。
なお、安全委員会の議長は、1.の委員がなるものとされています(労働安全衛生法第17条第3項)。
安全委員会の委員の構成
- 「総括安全衛生管理者」または「総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者(もしくはこれに準ずる者(※))」のうちから、事業者が指名した者
- 「安全管理者」のうちから、事業者が指名した者
- 「事業場の労働者」で、安全に関して経験を有する者のうちから、事業者が指名した者
(※)「これに準ずる者」とは、当該事業場において事業の実施を統括管理する者以外の者で、その者に準じた地位にある者をいい、例えば、副所長や副工場長等が該当すると解されます。
1.以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)の推薦に基づき指名する必要があります(労働安全衛生法第17条第4項)。
衛生委員会
衛生委員会
「衛生委員会」とは、事業場の労働者の健康障害の防止および健康の保持増進などに関する重要事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べることを目的として、一定規模以上の事業場において、設置が義務付けられている組織をいいます(労働安全衛生法第18条第1項)。
衛生委員会の設置を要する事業場(設置要件)
事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、衛生委員会を設置することが義務付けられています(労働安全衛生法施行令第9条)。
衛生委員会の委員の構成
衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する必要があります(労働安全衛生法第18条第2項)。
なお、衛生委員会の議長は、1.の委員がなるものとされています(労働安全衛生法第18条第4項)。
衛生委員会の委員の構成
- 「総括安全衛生管理者」または「総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者(もしくはこれに準ずる者)」のうちから、事業者が指名した者
- 「衛生管理者」のうちから、事業者が指名した者
- 「産業医」のうちから、事業者が指名した者
- 「事業場の労働者」で、衛生に関して経験を有する者のうちから、事業者が指名した者
- 上記の他、事業者は、事業場の労働者で、作業環境測定を実施している「作業環境測定士」である者を、衛生委員会の委員として指名することができる(労働安全衛生法第18条第3項)。
1.以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)の推薦に基づき指名する必要があります(労働安全衛生法第18条第4項)。
安全衛生委員会
安全委員会および衛生委員会を設けなければならない事業者は、それぞれの委員会の設置に代えて、「安全衛生委員会」を設置することができます(労働安全衛生法第19条)。
安全委員会・衛生委員会の調査・審議事項
安全委員会・衛生委員会は、次の事項について調査・審議し、事業者に対して意見を述べることとされています(労働安全衛生法第17条第1項・第18条第1項、労働安全衛生規則第21条・第22条)。
| 安全委員会 | 衛生委員会 |
| 1.労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること 2.労働災害の原因および再発防止対策で、安全にかかるものに関すること 3.上記の他、労働者の危険の防止に関する次の重要事項 (1)安全に関する規程の作成に関すること (2)危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置のうち、安全にかかるものに関すること (3)安全衛生に関する計画(安全にかかる部分に限る)の作成、実施、評価および改善に関すること (4)安全教育の実施計画の作成に関すること (5)厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官または産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること | 1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること 2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること 3.労働災害の原因および再発防止対策で、衛生にかかるものに関すること 4.上記の他、労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する次の重要事項 (1)衛生に関する規程の作成に関すること (2)危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生にかかるものに関すること (3)安全衛生に関する計画(衛生にかかる部分に限る)の作成、実施、評価および改善に関すること (4)衛生教育の実施計画の作成に関すること (5)新規化学物質等の有害性の調査およびその結果に対する対策の樹立に関すること (6)作業環境測定の結果およびその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること (7)定期に行われる健康診断、臨時健康診断、自発的健康診断および法に基づく他の省令(特化則等)の規定に基づいて行われる医師の診断、診察または処置の結果ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること (8)労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成に関すること (9)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること (10)労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること (11)労働安全衛生規則第577条の2第1項、第2項および第8項の規定により講ずる措置に関すること、ならびに同条第3項および第4項の医師または歯科医師による健康診断の実施に関すること (12)厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官または労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること |
委員会の運営
委員会の開催頻度
事業者は、委員会を毎月1回以上開催する必要があります(労働安全衛生規則第23条第1項)。
議事の概要の周知
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を、次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知する必要があります(労働安全衛生規則第23条第3項)。
議事の概要の周知方法
- 常時、各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 事業者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルまたは電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ)をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
議事の記録の保管
事業者は、委員会の開催の都度、委員会の意見および当該意見を踏まえて講じた措置の内容など、委員会における議事で重要なものにかかる事項を記録し、これを3年間保存する必要があります(労働安全衛生規則第23条第4項)。
労働時間の該当性
委員会の会議の開催に要する時間は、労働時間と解されます。
したがって、会議が法定労働時間外に行なわれた場合には、参加した労働者に対して、割増賃金を支払う必要があります(昭和47年9月18日基発602号)。