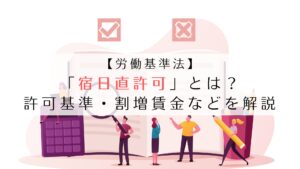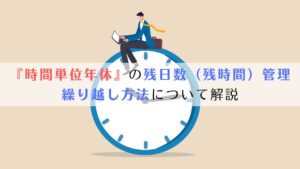「柔軟な働き方を実現するための措置」に関するQ&A(育児・介護休業法)【2025年10月改正】
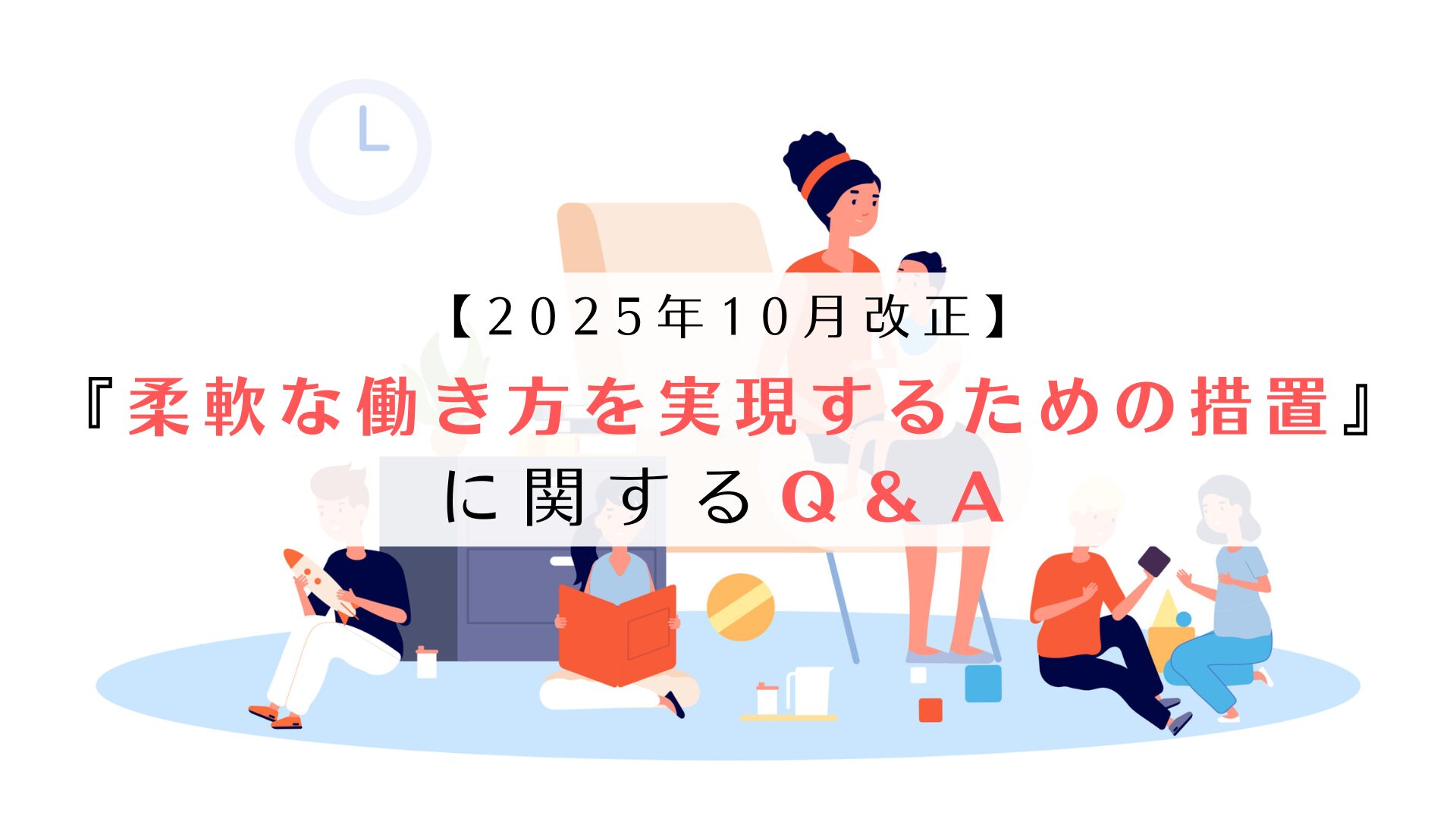
- 1. はじめに
- 2. 「措置の講じ方」に関するQ&A
- 2.1. 事業所、部署、職種ごとに異なる措置を講じることはできるか
- 2.1.1. 質問1
- 2.1.2. 回答1
- 2.2. 従業員の業務内容によっては、措置を選択できない場合
- 2.2.1. 質問2
- 2.2.2. 回答2
- 2.3. 措置を利用する際の手続について
- 2.3.1. 質問3
- 2.3.2. 回答3
- 3. 「始業時刻変更等の措置」に関するQ&A
- 3.1. 両方の措置を講じることの可否
- 3.1.1. 質問1
- 3.1.2. 回答1
- 3.2. 時差出勤の程度について
- 3.2.1. 質問2
- 3.2.2. 回答2
- 4. 「在宅勤務等の措置(テレワーク)」に関するQ&A
- 4.1. 在宅勤務の内容について
- 4.1.1. 質問1
- 4.1.2. 回答1
- 4.2. 在宅勤務の場所について
- 4.2.1. 質問2
- 4.2.2. 回答2
- 4.3. 在宅勤務の日数について
- 4.3.1. 質問3
- 4.3.2. 回答3
- 5. 「育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)」に関するQ&A
- 5.1. 6時間以下の短時間労働者がいる場合
- 5.1.1. 質問1
- 5.1.2. 回答1
- 5.2. 措置の内容が不合理とされる場合
- 5.2.1. 質問2
- 5.2.2. 回答2
- 6. 「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置」に関するQ&A
- 6.1. 休暇を無給とすることについて
- 6.1.1. 質問1
- 6.1.2. 回答1
- 6.2. 休暇の日数について
- 6.2.1. 質問2
- 6.2.2. 回答2
- 7. 「その他厚生労働省令で定めるもの」に関するQ&A
- 7.1. 「その他厚生労働省令で定めるもの」の内容について
- 7.1.1. 質問1
- 7.1.2. 回答1
はじめに
育児・介護休業法の改正により、事業主において、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じることが義務付けられ、2025(令和7)年10月1日に施行されます。
法改正により、事業主は、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、法令が定める下記の措置の中から、「2つ以上」の措置を講じ、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにする必要があります(育児・介護休業法第23条の3第1項第一号から第五号)。
事業主が講じる措置の内容(選択肢)
- 始業時刻変更等の措置
- 在宅勤務等の措置
- 育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)
- 労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置(子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇として与えられるものを除く)
- その他厚生労働省令で定めるもの
本稿では、「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じる際、実務上、疑問が生じやすい点について、厚生労働省から公表されている「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年1月23日時点)」(以下、「厚生労働省Q&A」といいます)に掲載されている内容を独自に編集して解説します。
なお、法改正の基本的な内容については、次の記事をご覧ください。
【2025年10月育児・介護休業法改正】「柔軟な働き方を実現するための措置(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)」の義務化を解説(措置の内容、手続など)
【関連動画はこちら】
「措置の講じ方」に関するQ&A
事業所、部署、職種ごとに異なる措置を講じることはできるか
質問1
「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じる際において、会社単位(会社全体)で一律に2つの措置を講じるのではなく、例えば、事業所ごと、部署ごと、職種(業務内容)ごとに、それぞれ異なる措置を講じることは問題ないでしょうか。
回答1
措置の選択に当たっては、職場の実情を適切に反映するため、事業所の業務の性質や内容などに応じて、措置の内容や組み合せを変えるなどの取り組みを行うことが望ましいといえます。
したがって、例えば、事業所ごと、部署ごと、職種(業務内容)ごとに、それぞれの実情に即した措置を講じることは問題なく、むしろ、より望ましい取り組みといえます(参考:厚生労働省Q&A2-4)。
従業員の業務内容によっては、措置を選択できない場合
質問2
事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じた場合であっても、従業員の業務内容によっては、その措置を選択できないような場合(例えば、シフト制による交替制勤務の職場において、テレワークの措置を講じるなど)、事業主は措置義務を果たしたことになるでしょうか。
回答2
法律は、従業員の個々の事情による求めに応じた措置を講じることまでは義務付けていないと解されるものの、従業員の職種や配置などから、利用できないことがあらかじめ想定される措置を講じることは、事業主が措置義務を果たしたことにはならないと解されます。
このような場合には、回答1のとおり、事業所ごと、部署ごと、職種(業務内容)ごとに、それぞれに適した措置を講じるなど、実情に即した措置を検討する必要があると考えられます(参考:厚生労働省Q&A2-5)。
措置を利用する際の手続について
質問3
「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用する従業員に対し、その際の社内手続として、例えば、「制度利用の1ヵ月前までに事前に申請する」などといった手続を定めることは問題ないでしょうか。
回答3
法律上、「柔軟な働き方を実現するための措置」の利用の申出の期限などについて、特に定めはありません。
基本的には、就業規則や育児介護休業規程など、社内規定に定められた申請の時期や方法に従うこととなります(参考:厚生労働省Q&A2-9)。
「始業時刻変更等の措置」に関するQ&A
両方の措置を講じることの可否
質問1
「始業時刻変更等の措置」のうち、「フレックスタイム制」と「時差出勤の制度」のどちらも(両方とも)選べる制度を設けた場合、それによって、2つの措置を講じたことになるでしょうか。
回答1
「始業時刻変更等の措置」は、「フレックスタイム制」と「時差出勤の制度」の「いずれか」を指すものであって、仮に、どちらも選べる制度を設けた場合であっても、措置を2つ設けたものと評価されることはなく、措置義務を果たしたことにはなりません(参考:厚生労働省Q&A2-8①)。
時差出勤の程度について
質問2
「時差出勤の制度」については、最低、何時間以上の時差出勤を可能にする必要があるなど、法律上の決まりはあるでしょうか。
回答2
始業・終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる時間の範囲について、法律上の制限はありません(参考:厚生労働省Q&A2-8②)。
例えば、「少なくとも1時間以上の繰り上げ・繰り下げを認めなければならない」などといった決まりはありません。
ただし、保育所への送迎の便宜など、時差出勤を行う目的を考慮すると、あまり短い時差出勤(10分など)は、実質的にみて、制度を講じる目的に沿わないものとなります。
例えば、従業員ごとに、育児の状況に応じて、30分や1時間など時差出勤のパターンを選択することができるように配慮することが望ましいと考えます。
「在宅勤務等の措置(テレワーク)」に関するQ&A
在宅勤務の内容について
質問1
法律上は、「在宅勤務「等」の措置」と定められていますが、「等」には何が含まれるのでしょうか。
回答1
「在宅勤務(テレワーク)」は、一般に、従業員が事業場以外の場所において、情報通信技術を利用して行う勤務を指すもの解されます。
ただし、業務内容によっては、必ずしも情報通信技術を利用しない業務も想定されることから、在宅勤務「等」と表記されています(参考:厚生労働省Q&A2-10)。
在宅勤務の場所について
質問2
在宅勤務(テレワーク)を行う場所について、決まりはありますか。
回答2
在宅勤務(テレワーク)を実施する場所については、従業員の自宅で行われることを基本としています。
ただし、事業主が認める場合には、サテライトオフィス等(従業員個人または事業主のいずれが契約したものであるかは問わない)において実施する業務を含みます(参考:厚生労働省Q&A2-10)。
在宅勤務の日数について
質問3
在宅勤務(テレワーク)の利用について、法律上は、「月に10日」と定められていますが、例えば、社内規定で「3ヵ月で30 日」と定めるなど、平均して月10 日以上の在宅勤務(テレワーク)を利用できる仕組みにすることは問題ないでしょうか。
回答3
在宅勤務(テレワーク)については、1週間の所定労働日数が5日の労働者については、「1ヵ月につき」10 労働日以上利用できるものとする必要があります。
法律上は、「1ヵ月につき」という要件のみが定められていることから、例えば、従業員が2ヵ月以上の期間利用する場合でも、平均して、1ヵ月につき10 労働日以上利用できることが制度上担保されていれば、問題ありません(参考:厚生労働省Q&A2-11)。
「育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)」に関するQ&A
6時間以下の短時間労働者がいる場合
質問1
パートなど、短時間労働者で、すでに6時間勤務以下の従業員がいる場合で、短時間勤務制度にかかる措置を講じた場合、当該短時間労働者に対しても、措置を講じたものと評価されるのでしょうか。
それとも、短時間労働者に対しては、短時間勤務制度以外で、2つ以上の措置を実施しなければならないのでしょうか。
回答1
パートタイム労働者等の短時間労働者であって、1日の所定労働時間が6時間以下の従業員がいる場合、事業主が短時間労働者も含めて、①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間に短縮できるもの)と、②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置について、①と②を合わせて2つ以上講じた場合、措置義務を履行したことになると解されます。
ただし、従業員の1日の所定労働時間が6時間以下であることをもって、当該従業員の意向に関係なく、自動的に「短時間勤務制度」の措置が選択されたものとして取り扱うことは適切ではなく、事業主は、短時間勤務制度を含む5つの選択肢の中から、2つ以上を選択できるように措置を講じる義務があります。
措置の内容が不合理とされる場合
質問2
パートなど、短時間労働者がいる場合に、措置の内容が不合理とされるのは、どのような場合でしょうか。
回答2
例えば、1日の所定労働時間が6時間以下の短時間労働者と、1日の所定労働時間が6時間を超える正社員がいる事業所において、正社員には短時間勤務制度「以外」の選択肢から2つの措置を講じつつ、短時間労働者には短時間勤務制度を「含む」2つの措置を講じるような場合、パートタイム・有期雇用労働法に基づき、職務の内容などに照らして、不合理な待遇差に当たらないように留意することが求められます。
「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置」に関するQ&A
休暇を無給とすることについて
質問1
「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(以下、「養育両立支援休暇」といいます)については、取得した日について「無給」としてもよいでしょうか。
回答1
従業員が養育両立支援休暇を取得した日については、法律上、賃金を支払うことは義務付けられていないため、無給でも問題ありません(参考:厚生労働省Q&A2-13)。
もちろん、会社が独自に、福利厚生として、法を上回る措置として有給とすることは差し支えなく、むしろ望ましいことといえます。
休暇の日数について
質問2
養育両立支援休暇については、法律上、1年に10 日以上の休暇を付与することが定められていますが、休暇を付与する単位を、例えば、「6ヵ月につき5日」や「1ヵ月につき1日」などと定め、合計で1年に10日以上となるような休暇を付与する仕組みにすることは問題ないでしょうか。
回答2
養育両立支援休暇については、「1年につき」10 労働日以上の利用をすることができるようにする必要があります。
あくまで「1年につき」とだけ定められているため、例えば、「6ヵ月につき5日」や「1ヵ月につき1日」などのように、社内の制度において、1年以内の期間で日数の配分を定めた場合であっても、1年単位でみたときに合計10労働日以上の休暇が確保されている限りは、問題ありません(参考:厚生労働省Q&A2-14)。
反対に、「6ヵ月につき3日」など、1年単位でみたときに、1年につき10 労働日に達しない制度は、法律上認められません。
「その他厚生労働省令で定めるもの」に関するQ&A
「その他厚生労働省令で定めるもの」の内容について
質問1
措置のうち、「その他厚生労働省令で定めるもの」の内容は、どのようなものでしょうか。
回答1
厚生労働省令では、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」を定めています(育児・介護休業法施行規則第75条の4)。
「保育施設の設置・運営」とは、事業主自らが保育施設を設置し、運営する場合の他、例えば、他の事業主が設置・運営する保育施設に委託をし、その費用を負担することが考えられます。
また、「これに準ずる便宜の供与」とは、従業員からの希望に基づき、ベビーシッターを手配し、その費用を事業主が補助することなどが該当します。
なお、「手配」とは、ベビーシッター派遣会社と事業主が契約を締結し、従業員からの希望に応じて自社への派遣を依頼すること、または従業員が直接、当該派遣会社に派遣の依頼をすることが含まれます(参考:厚生労働省Q&A2-15)。