「傷病手当金」とは?支給要件・支給額・支給期間など、制度の基本的な内容を解説【健康保険法】
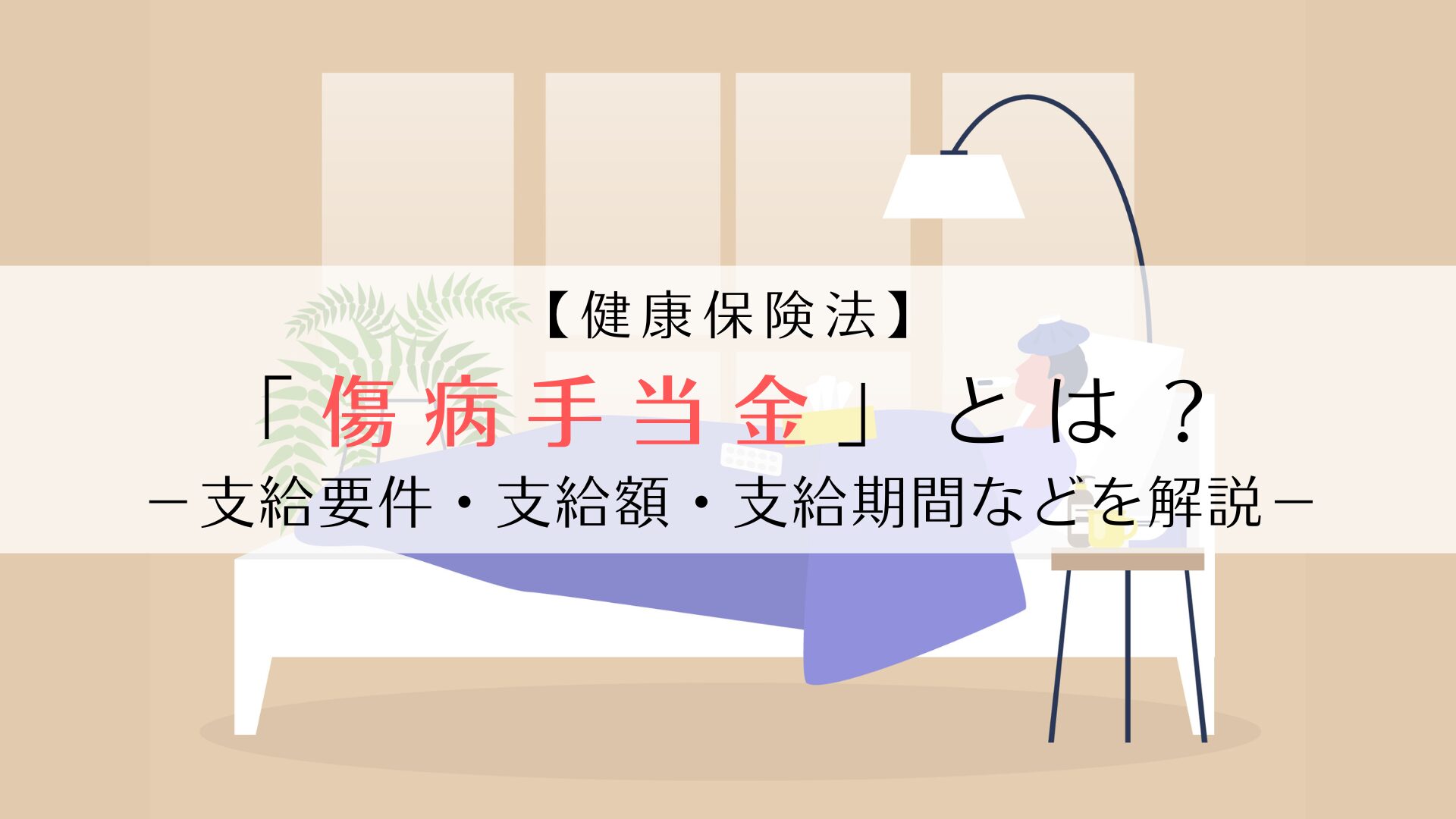
- 1. 「傷病手当金」とは
- 1.1. 「傷病手当金」とは
- 1.2. 傷病手当金が支給される健康保険の種類
- 2. 傷病手当金の対象者
- 3. 傷病手当金の支給要件
- 3.1. 【要件1】「業務外」の事由による疾病または負傷の療養のための休業であること
- 3.2. 【要件2】「労務不能」である(仕事に就くことができない)こと
- 3.3. 【要件3】連続する3日間を含み、「4日以上」仕事に就くことができなかったこと
- 3.3.1. 待期期間とは
- 3.3.2. 待期期間中の年次有給休暇の取得日・公休日の取り扱い
- 3.3.3. 就業時間の途中から休業した場合
- 3.4. 【要件4】休業した期間について、「賃金の支払いがない」こと
- 4. 傷病手当金の支給額の計算方法
- 4.1. 計算手順
- 4.2. 1.標準報酬月額の平均額の算定
- 4.2.1. 原則
- 4.2.2. 例外(加入期間が12ヵ月に満たない場合)
- 4.3. 2.標準報酬日額の算定
- 4.4. 3.傷病手当金の支給額の算定
- 5. 傷病手当金の支給期間
- 5.1. 傷病手当金の支給期間
- 5.2. 資格喪失後(退職後)の継続給付の場合
「傷病手当金」とは
「傷病手当金」とは
「傷病手当金」とは、従業員(健康保険の被保険者)が、業務外の疾病または負傷によって労務不能となり休業し、会社から給与が支給されない場合に、休業期間中の生活を保障するために、健康保険から支給される給付金をいいます。
傷病手当金により、労務不能により休業した日について、給与の3分の2程度の保障を、通算1年6ヵ月にわたって受けることができます。
傷病手当金が支給される健康保険の種類
主に会社員などが勤務先を通じて加入する健康保険として、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と、「組合管掌健康保険(組合健保)」の2種類があります。
また、主に自営業者などが加入する健康保険として、市区町村が運営する「国民健康保険(市町村国保)」と、業界団体が運営する「国民健康保険組合」の2種類があります。
このうち、傷病手当金が支給されるのは、全国健康保険協会(協会けんぽ)または組合管掌健康保険(組合健保)であり、国民健康保険(市町村国保)では、原則として傷病手当金は支給されません(国民健康保険組合については、組合ごとに異なります)。
傷病手当金の対象者
傷病手当金の対象者は、原則として、現に健康保険に加入している被保険者本人です。
健康保険の給付の中には、被保険者が扶養している親族(以下、「被扶養者」といいます)も対象となる給付がありますが(例えば、窓口で医療費が3割負担になる「療養の給付」など)、傷病手当金は、被保険者本人を対象としているため、被扶養者が疾病または負傷によって労務不能となっても、傷病手当金は支給されません。
また、傷病手当金は、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、勤務先を通じて健康保険に加入している被保険者であれば、支給対象となります。
なお、任意継続被保険者(退職後も引き続き同じ健康保険に加入している被保険者)に対しては、原則として、傷病手当金は支給されません(資格喪失後の継続給付に該当する場合を除く)。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金は、次の4つの要件をすべて満たす場合に支給されます(健康保険法第99条)。
傷病手当金の支給要件
- 「業務外」の事由による疾病または負傷の療養のための休業であること
- 「労務不能」である(仕事に就くことができない)こと
- 連続する3日間を含み、「4日以上」仕事に就くことができなかったこと
- 休業した期間について、「賃金の支払いがない」こと
【要件1】「業務外」の事由による疾病または負傷の療養のための休業であること
傷病手当金は、「業務外」の事由による疾病または負傷(業務とは関連しない私傷病)を対象としています。
一方、業務に起因した「業務上」の事由による疾病または負傷については、健康保険ではなく、「労災保険」から給付が行われます。
医師の指示に基づく休業であれば、入院だけでなく、病後の静養や自宅療養をしながら通院している場合でも、その休業期間について傷病手当金が支給されます(昭和32年8月13日保文発第6905号)。
また、身体の疾病または負傷に限らず、うつ病などの精神疾患であっても、要件を満たす限り傷病手当金の対象となります。
一方、美容整形手術など、健康保険の給付対象とならない治療(自費診療)を行うために休業したとしても、傷病手当金は支給されません(昭和4年6月29日保理第1704号)。
【要件2】「労務不能」である(仕事に就くことができない)こと
傷病手当金は、健康保険の保険者(協会けんぽなど)において、被保険者が労務不能であるかどうかを判断します。
判断の際には、その被保険者の従事する業務の種別を顧慮して、その業務に堪え得るか否かを標準として、社会通念により保険者が個々の事例を認定します(昭和15年1月31日社発第83号通知)。
医師の意見などをもとに、従業員の業務内容などを考慮して判断されるため、従業員の自己判断や、自己申告によって決まるものではありません。
なお、休業からの復帰後、医師の指示または許可のもと、半日出勤し従前の業務に服する場合には、たとえごく短時間の出勤でも、「労務不能」の要件に該当しないため、傷病手当金は支給されません(昭和29年12月9日保文発第14236号)。
なお、労務不能期間中において、その事業所の公休日がある場合でも、療養のため労務に服することができない状況にあれば、当該公休日は支給期間に含まれます(昭和2年2月5日保理第659号)。
【要件3】連続する3日間を含み、「4日以上」仕事に就くことができなかったこと
待期期間とは
傷病手当金は、疾病または負傷の療養のために休業を開始した日から、連続して3日間が経過した後、4日目以降の休業日に対して支給されます。
この3日間のことを「待期期間」といいます。
待期期間は、虚病による傷病手当金の不正受給を防ぐ目的で設けられている期間です。
待期期間は、3日間連続していることが必要とされており、例えば、連続して2日間会社を休んだ後、3日目に出勤した場合には、要件を満たさず、待期期間が成立しないことから、仮に4日目に休業を開始したとしても傷病手当金は支給されません(昭和32年1月31日保発第2号の2)。
なお、一度待期が完了した場合には、その後いったん出勤し、再び同じ疾病または負傷で休業する場合でも、再度待期を完成させる必要はありません(昭和2年3月11日保理第1085号)。
待期期間中の年次有給休暇の取得日・公休日の取り扱い
従業員が休業を開始してから3日間の待期期間の途中に、年次有給休暇を取得したり、休日や祝祭日などの公休日がある場合でも、当該年次有給休暇の取得日や公休日については、待期期間に含めるものとして取り扱います(昭和26年2月20日保文発第419号)。
また、待期期間中に賃金の支払いがあったかどうかは、待期の完成に影響しません。
就業時間の途中から休業した場合
待期は労務不能となった日から起算しますが、従業員が就労時間の途中において、業務外の事由で発生した疾病または負傷によって労務不能になった場合(早退した場合)には、その日を待期期間に含め、待期期間の1日目として起算します(昭和28年1月9日保文発第69号)。
なお、当日の業務終了後に労務不能となった場合には、その翌日から待期期間を起算します。
【要件4】休業した期間について、「賃金の支払いがない」こと
傷病手当金は、疾病または負傷によって賃金が支給されなくなった場合の生活保障を行うための給付であることから、休業中であっても会社から賃金が支払われている間は、傷病手当金は支給されません(健康保険法第108条第1項)。
ただし、会社から賃金が支払われている場合であっても、当該賃金の額が、傷病手当金の支給額よりも少ない場合には、その差額が傷病手当金として支給されることとなります(健康保険法第108条第1項但書)。
傷病手当金の支給額の計算方法
計算手順
傷病手当金は、1日単位で支給されるため、1日あたりの支給額の計算方法を定めています。
傷病手当金の支給額(1日あたり)の計算方法は、次のとおりです(健康保険法第99条第2項)。
傷病手当金の支給額(1日あたり)
- 支給開始日の属する月以前の直近12ヵ月間の各月でみた「標準報酬月額の平均額」を算定する
- 1.に30分の1を乗じて、「標準報酬日額」を算定する(計算の結果生じた5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる)
- 2.に3分の2を乗じて、「傷病手当金の支給額(1日あたり」を算定する(計算の結果生じた50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる)
1.標準報酬月額の平均額の算定
原則
はじめに、支給開始日の属する月以前の直前12ヵ月間でみた、「標準報酬月額の平均額」を算定します。
「標準報酬月額」とは、健康保険料を算定する際に用いる、計算上の(仮の)給与額をいいます。
健康保険料は、従業員の給与額にそのまま健康保険料率を乗じるのではなく、給与額に応じて段階的に定められた標準報酬月額(全50等級)に当てはめて、当該額に健康保険料率を乗じて保険料を算定します。
「支給開始日」とは、最初に傷病手当金が支給される日のことをいい、当該日の属する月以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均額を求めることとなります。
なお、賞与(ボーナス)は、標準報酬月額とは別に、「標準賞与額」として保険料を算定するため、傷病手当金の計算手順に含まれません(したがって、傷病手当金の支給額に賞与額は反映されません)。
例外(加入期間が12ヵ月に満たない場合)
支給開始日の属する月以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合は、「支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額」と、「支給する年度の前年度の9月30日における、全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額」のうち、いずれか低い方の額によります。
2.標準報酬日額の算定
1.で算定した平均標準報酬月額の平均額に対し、30分の1を乗じる(30で割る)ことによって、「標準報酬日額」を算定します。
標準報酬日額は、おおむね1日あたりの給与額に近い金額になります。
3.傷病手当金の支給額の算定
2.で算定した標準報酬日額に3分の2を乗じた額が、1日あたりの傷病手当金の額となります。
なお、労務不能期間中に報酬の減額があった場合でも、それに応じて傷病手当金の額が減額されることは、傷病手当金が生活保障のための制度であることを考えると不適当であるから、労務不能期間中に報酬の変動があった場合でも、傷病手当金は減額されません(昭和26年6月4日保文発第1821号)。
傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6ヵ月間とされています(健康保険法第99条第4項)。
支給期間は、待期期間である3日間が経過した後、傷病手当金の支給が開始される4日目から起算し、暦(こよみ)によって把握します。
支給期間の途中に、職場に復帰したことなどにより、傷病手当金が支給されない期間(無支給期間)がある場合には、無支給期間については、支給期間に影響しません。
1年6ヵ月とは具体的に何日間をいうのか、実際の支給日数の計算方法を説明します。
事例
- 2025年3月1日から4月10日まで労務不能(支給日数は38日間)
- 2025年4月11日から4月20日まで労務不能(支給日数は10日間)
- 2025年4月21日から5月10日まで就労した(傷病手当金の支給なし)
- 2025年5月11日から6月10日まで労務不能(支給日数は31日間)
上記の例では、2025年3月1日から3月3日までの3日間は待期期間であるため、傷病手当金の支給開始日は3月4日となります(最初の3日間は支給日数に含まれません)。
そして、傷病手当金の支給期間は、暦(こよみ)によって把握することから、2025年3月4日から18ヵ月後にあたる2026年9月3日をもって、1年6ヵ月が経過することとなります。
そして、この期間の支給日数を合計すると、総支給日数は「549日」になります。
傷病手当金が支給されるごとに、支給日数は減っていき、残りの支給日数が0日になる日が支給満了日となります。
上記の事例の最後の時点では、傷病手当金の支給残日数は470日となります。
なお、4月21日から5月10日までに20日間就労しているため、この期間は傷病手当金が支給されませんが、総支給日数には影響を与えません。
資格喪失後(退職後)の継続給付の場合
傷病手当金は、一定の要件(退職日までに、健康保険の被保険者であった期間が継続して1年以上あるなど)を満たせば、退職後においても支給されることがあります。
ただし、資格喪失後の傷病手当金は、資格喪失後も継続して支給を受け続けることが必要です(健康保険法第104条)。
したがって、退職後において、一時的に働くことが可能な状態になった場合には、その時点で傷病手当金の支給が終了するため、その後に再び労務不能となった場合でも、傷病手当金は支給されません。


