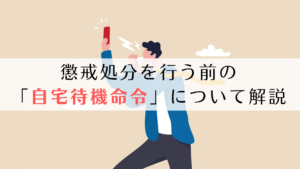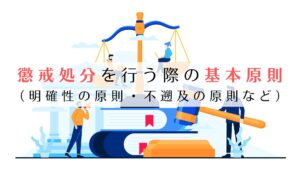懲戒処分を行う際の手続に関する就業規則の規定例(記載例)を解説

はじめに
一般に、会社組織では、企業秩序を維持するために、服務規律が定められており、従業員がこれに違反する行為(以下、「違反行為」といいます)をした場合には、その行為に対する制裁として、懲戒処分を行うことがあります。
懲戒処分を行う際には、違反行為に相当する処分内容とするために、調査から決定に至るまで、各段階で適正な手続を担保しなければなりません。
本稿では、会社が懲戒処分を行う際の手続に関する、就業規則の規定例(記載例)を解説します。
なお、会社が懲戒処分を行う際の手続については、次の記事を併せてご覧ください。
懲戒処分を行う際の手続(調査・弁明の付与・懲戒委員会など)を流れに沿って解説
懲戒処分のための準備手続(事実確認・証拠収集・事情聴取)に関する規定例(記載例)
懲戒処分のための準備手続に関する規定例(記載例)
(事実確認と証拠収集)
第1条 会社は、懲戒処分を行うにあたり、事前に調査を実施し、事実確認と証拠収集を行うこととし、その結果に基づいて違反行為の認定を行った上で、当該違反行為に対する懲戒処分の内容を決定する。
2 違反行為が疑われる従業員およびその関係者は、会社が行う調査に協力しなければならない。
(事情聴取)
第2条 会社は、前条に定める事実確認と証拠収集を行うにあたり、必要に応じて、違反行為が疑われる従業員およびその関係者に対して、事情聴取を行う。
2 会社が前項の事情聴取を行う場合は、原則として、2名以上の担当者で行うものとし、そのうち1名が聴取内容を記録する。
従業員による違反行為が発覚した場合、会社はまず、調査を実施して、就業規則上の懲戒事由に該当する行為があったのかどうか、事実関係を確認する必要があります。
会社には違反行為をした従業員に対する調査権限があり、違反行為をした従業員は、原則として、会社の実施する調査に対する協力義務を負うものと解されます(富士重工業事件/最高裁判所昭和52年12月13日判決)。
上記の規定例は、懲戒処分の前段階として、適正な手続を担保するために、会社が事実確認、証拠拠集および事情聴取を行うことを規定したものです。
自宅待機命令を行う場合の規定例(記載例)
自宅待機命令を行う場合の規定例(記載例)
(自宅待機命令)
第3条 会社は、本規則に定める懲戒事由に該当する行為をしたことが発覚し、またはその疑いがある従業員に対して、その調査を行い、処分を決定するまでに必要な期間について、自宅待機を命じることがある。
2 自宅待機期間中の賃金は、原則として支給する。ただし、従業員の行為が諭旨解雇もしくは懲戒解雇事由に該当し、または該当する疑いがある場合であって、自宅待機を命じる理由が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、自宅待機期間中の賃金を支給しない。
一、不正行為の再発のおそれがある場合
二、証拠隠滅のおそれがある場合
三、前各号の他、緊急かつ合理的な理由がある場合
3 会社は、前項に基づき自宅待機を命じる場合は、従業員に対して「自宅待機命令書」を交付する。
自宅待機命令は、労働契約上の労務指揮権に基づき、一種の業務命令として行うことができると解されます。
自宅待機は会社の業務命令に基づくものであり、これをもって従業員の労務提供義務は尽くされていると解されることから、会社は、原則として、自宅待機期間中の賃金を支払う義務を負います。
裁判例では、「自宅謹慎は、それ自体として懲戒的性質を有するものではなく、当面の職場秩序維持の観点から執られる一種の職務命令とみるべきものであるから、使用者は当然にその間の賃金支払い義務を免れるものではない」として、自宅待機期間中の賃金の請求を全額認めたものがあります(日通名古屋製鉄作業株式会社事件/名古屋地方裁判所平成3年7月22日判決)。
ただし、同裁判例では、「当該労働者を就労させないことにつき、不正行為の再発、証拠隠滅のおそれなどの緊急かつ合理的な理由が存する」ときは、会社が賃金支払義務を免れる場合があることを示していることから、規定例では、例外的に賃金を支給しない場合があることを規定しています。
自宅待機命令については、次の記事をご覧ください。
懲戒処分を行う前の「自宅待機命令」について解説
懲戒委員会を設置して審議を行う場合の規定例(記載例)
懲戒委員会を設置して審議を行う場合の規定例(記載例)
(懲戒委員会)
第4条 会社は、懲戒処分の適正を期す為、懲戒委員会を設置する。
2 懲戒委員会は、懲戒処分を行うかどうか、また、行う場合には量定をどの程度にするかについて審議および決議を行う。
3 懲戒委員会は、社長、人事部長、および社長の指名する5名以内の委員をもって構成し、委員長には社長があたる。
4 懲戒委員会の委員のうち1名は、従業員の代表者を含めることができる。 5 懲戒委員会の事務局は、人事部内に置く。
(懲戒処分の手続)
第5条 各部門の管理監督者は、所属する従業員に懲戒事由に該当する疑いがあると認めたときは、速やかに人事部長に対して報告を行わなければならない。人事部長は、当該報告を受けて、懲戒委員会による審議を必要と判断する場合は、委員長に対して、懲戒委員会の開催を求めるものとする。
2 懲戒委員会は、必要があると認めるときは、懲戒対象者またはその関係者を出席させて、当該事案に関する説明または弁明を求めることができる。
法律上、懲戒委員会を設置することは義務付けられていません。
懲戒委員会を設置するかどうか、および設置した場合の委員の構成などについては、会社が任意に決めることができます。
ただし、就業規則などに懲戒委員会を設置する旨を定めた場合には、懲戒委員会に諮らずに行われた懲戒処分について、手続上の瑕疵が生じることになります。
なお、必要に応じて、任意に諮問機関を設置することは問題なく、その場合の規定例は次のとおりです。
任意に諮問機関を設置する場合の規定例(記載例)
(諮問機関の設置)
第6条 会社は、懲戒処分の決定にあたり必要と認めた場合は、諮問機関を設置することができる。
2 前項に基づき諮問機関を設置した場合は、当該諮問機関が本規則に基づく懲戒処分に関する審査を行うものとする。
懲戒処分の審議・決定に関する規定例(記載例)
懲戒の原則に関する規定例(記載例)
懲戒の原則に関する規定例(記載例)
(懲戒の原則)
第7条 会社は懲戒処分を行うにあたり、就業規則に規定する懲戒事由に該当する行為でなければ、これを行うことができない。
2 就業規則の制定前または新たに懲戒事由の追加をした場合、その制定前または追加前の事案に対しては、遡及的に懲戒処分を行ってはならない。
3 懲戒処分は、同一の事案に対して、重ねて行うことはできない。
4 懲戒事由が発覚してから懲戒処分を行うまでに、長期間が経過しないようにしなければならない。
5 懲戒処分は、同程度の事案に対して、懲戒の種類および程度が異なってはならない。
懲戒処分の審議に関する規定例(記載例)
懲戒処分の審議に関する規定例(記載例)
(懲戒処分の審議)
第8条 会社は、就業規則に定める懲戒事由の該当事実、弁明内容等を総合的に勘案して、懲戒処分の量定を審議するものとする。
2 会社は懲戒処分の審議にあたり、懲戒処分の量定について、次の事項を総合的に勘案して決定しなければならない。
一、違反行為をした目的・動機
二、違反行為における過失の程度
三、懲戒処分対象者の役職・職責・勤続年数
四、過去における違反行為の有無およびその内容
五、過去における懲戒処分の有無およびその内容
六、懲戒処分対象者の日頃の勤務態度、勤務成績、人事評価
七、懲戒処分対象者の反省の程度、謝罪の有無
八、違反行為によって会社に生じた損害の程度
九、過去に発生した類似事例との比較
十、責任能力の有無
十一、類似事案に関する裁判例
十二、その他一切の事情
3 会社は、懲戒処分の審議内容について、議事録に記録しなければならない。
4 情状酌量の余地があり、または従業員が自らの違反行為が発覚する前に会社に対し自主的に申し出るなど、改悛の情が明らかに認められる場合は、処分を減軽し、または免除することがある。
弁明の機会の付与手続に関する規定例(記載例)
弁明の機会の付与手続に関する規定例(記載例)
(弁明の機会の付与)
第9条 会社は懲戒処分を行う場合、諭旨解雇または懲戒解雇に該当するおそれのあるときは、口頭または文書により弁明の機会を与える。
違反行為をした従業員に対して、弁明の機会を与えることは、法律上、必ずしも義務付けられるものではありません。
しかし、明らかに懲戒事由に該当する場合を除いては、従業員から懲戒事由に対する説明や反論を一切聴取することなく、会社が一方的に懲戒事由の有無を判定することは、公平性を担保した適正な手続とはいえず、懲戒権を濫用したものとして争われるリスクが残ると考えます。
懲戒の過重に関する規定例(記載例)
懲戒の過重に関する規定例(記載例)
(懲戒の過重)
第10条 次の各号の事由に該当する場合には、その懲戒を過重する。
一、違反行為の動機もしくは態様が極めて悪質であるとき、または違反行為の結果が極めて重大であるとき
二、違反行為をした従業員が、管理または監督の地位にあるとき
三、違反行為による会社に及ぼす影響が特に大きいとき
四、過去に類似の違反行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
五、同時に2つ以上の懲戒事由に該当する行為をしたとき
教唆および幇助をした従業員に関する規定例(記載例)
教唆および幇助をした従業員に関する規定例(記載例)
(教唆および幇助)
第11条 従業員が、他人を教唆し、または幇助して、懲戒事由に定める行為をした場合は、当該行為に準じて懲戒処分を行う。
実際に非違行為をした従業員だけでなく、教唆(実行行為をそそのかす行為)、または幇助(実行行為を手伝う行為)をした従業員に対しても、懲戒処分の対象とする場合の規定です。
懲戒処分決定後の手続に関する規定例(記載例)
懲戒処分決定後の手続に関する規定例(記載例)
(決定の通知)
第12条 懲戒委員会が懲罰の決定を行ったときは、会社は、懲罰を決定した従業員に対し、書面を交付することによって、処分内容を通知する。この場合において、会社が必要と認めるときは、社内で処分内容を公表することがある。
2 懲戒解雇に該当するときであって、従業員の行方が知れず、懲戒解雇処分の通知を本人に対して行えないときは、届出住所または家族の住所への懲戒処分通知書の送達をもって、懲戒解雇の通知が到達したものとみなす。
法律上、懲戒処分の通知方法には決まりがないため、口頭で通知することでも足ります。
しかし、懲戒処分の対象となる従業員に対して、懲戒処分の重大さを理解させ、問題行動を改めさせるためには、懲戒処分は書面で通知することが望ましいといえます。
懲戒処分が行われたことを広く社内に知らしめ、注意を喚起することは、著しく不相当な方法によるものでない限り、何ら不当なものとはいえないと解されます(X社事件/東京地方裁判所平成19年4月27日判決)。
しかし、懲戒処分の内容の公表は、再発防止のために有効である反面、懲戒処分を受けた従業員の信用を低下させることにもつながるため、あくまで必要最小限の範囲に留めたうえで、従業員の名誉を傷付けることのないように、配慮する必要があると考えます。
損害賠償に関する規定例(記載例)
損害賠償に関する規定例(記載例)
(損害賠償)
第13条 従業員が故意または過失によって会社に損害を与えたときは、懲戒されたことによって損害の賠償を免れることはできない。
従業員が労働契約に基づく労務提供義務に違反した場合には、会社に対する損害賠償責任を負うこととなります(民法第415条、同第416条)。
このような従業員の損害賠償責任は、懲戒処分を受けたからといって、当然に免責されるものではありませんので、規定例では、そのことを確認的に規定しています。