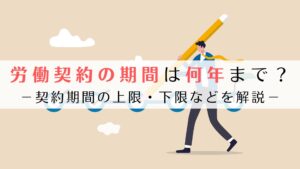「退職金の不支給」は認められるか?引継ぎ義務違反・懲戒解雇・競業避止義務違反について、ケース別に解説
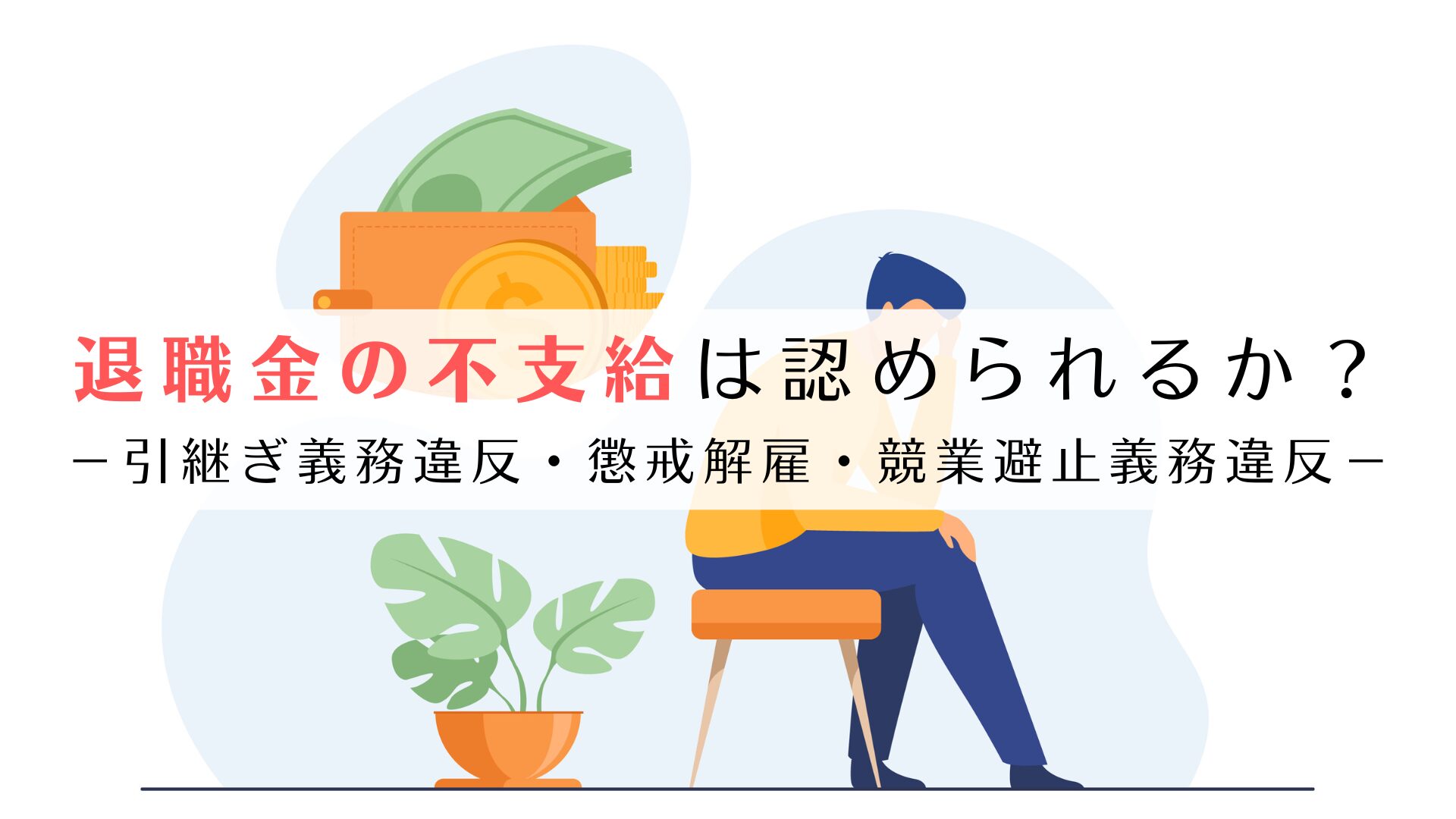
- 1. はじめに
- 2. 退職金の法的性質と退職金の不支給
- 2.1. 退職金とは
- 2.2. 退職金の法的性質と退職金の不支給
- 3. 引継ぎ義務違反による退職金不支給
- 3.1. 引継ぎ義務違反とは
- 3.2. 参考裁判例①(日本高圧瓦斯工業事件/大阪地方裁判所昭和59年7月25日判決)
- 3.3. 参考裁判例②(帝国デンタル製作所事件/東京地方裁判所昭和59年3月6日判決)
- 3.4. 参考裁判例③(東京ゼネラル事件/東京地方裁判所平成11年4月19日判決)
- 4. 懲戒解雇による退職金の不支給
- 4.1. 懲戒解雇と退職金不支給
- 4.2. 退職金規程の整備の必要性
- 4.3. 参考裁判例④(小田急電鉄(退職金請求)事件/東京高等裁判所平成15年12月11日判決)
- 4.4. 参考裁判例⑤(みずほ銀行事件/東京高等裁判所令和3年2月24日判決)
- 4.5. 参考裁判例⑥(伊藤忠商事ほか事件/東京地方裁判所令和4年12月26日判決)
- 5. 競業避止義務違反による退職金不支給
- 5.1. 競業避止義務違反とは
- 5.2. 参考裁判例⑦(三晃社事件/最高裁判所昭和52年8月9日判決)
- 5.3. 参考裁判例⑧(野村證券元従業員事件/東京地方裁判所平成28年3月31日判決)
- 5.4. 参考裁判例⑨(日本リーバ事件/東京地方裁判所平成14年12月20日判決)
はじめに
会社が福利厚生として退職金制度を設けている場合、通常、従業員が会社を円満に退職すれば、退職金規程で定められた退職金が満額支給されます。
一方、従業員が懲戒解雇によって退職する場合など、円満な退職でない場合には、会社が、退職金の全部または一部を支給しないことがあります。
どのような場合に退職金を支給しないことが認められるのか、法律上、明確な基準はなく、裁判例を参考に判断する必要があります。
本稿では、退職金の不支給について、引継ぎ義務違反、懲戒解雇、競業避止義務違反の3つのケースに分けて、裁判例を中心に解説します。
退職金の法的性質と退職金の不支給
退職金とは
「退職金」とは、一般に、従業員が退職する際に、会社が支払う金銭をいいます。
一般的には、あらかじめ退職金規程などによって、退職金の算定方法など支給基準を定めます。
法律上、会社には退職金を支給する義務はありません。
ただし、会社が一たび退職金制度を導入した場合は、退職金の支払いが、会社と従業員との間の労働契約の内容となることから、その後、会社が一方的に退職金制度を廃止したり、退職金を減額したりすることは基本的に認められません。
退職金制度については、次の記事をご覧ください。
退職金制度とは?4種類の退職金制度の内容とメリット・デメリットをわかりやすく解説
退職金の法的性質と退職金の不支給
制度設計にもよりますが、退職金の法的性質としては、一般に、「功労報償的性格」と「賃金の後払的性格」があると解されています。
「功労報償的性格」とは、従業員の長年の勤続の功を評価して支給することをいい、「賃金の後払的性格」とは、在職中の労働の対価である賃金を、従業員の退職後の生活保障などといった意味合いで、退職時に後払いして支給することをいいます。
このような退職金の法的性質から、退職金を不支給とすることができるのは、従業員に勤続の功を抹消(全部不支給の場合)ないし減殺(一部不支給の場合)してしまうほどの、著しく信義に反する行為があった場合に限られるものと解されます。
裁判例では、「退職金は、功労報償の性質を有することは否定できないから、退職手当金規程において、懲戒解雇事由がある場合に退職金の一部または全部を支給しない旨を定めることは許されると解すべきであるが、退職金が一般に賃金の後払いの性質を有することからすると、退職金を支給しない、または減額することが許されるのは、従業員にその功労を抹消または減殺するほどの信義に反する行為があった場合に限られると解される」としています(東芝事件/東京地方裁判所平成14年11月5日判決)。
引継ぎ義務違反による退職金不支給
引継ぎ義務違反とは
退職時に起こり得る問題として、従業員が突然退職したり、退職を申し出てから退職日まで年次有給休暇を取得したりすることによって、引き継ぎを行わずに退職することがあります。
会社は、このような退職のされ方を防止するために、退職金規程に、退職金の不支給事由として、「会社の指示に反して、退職時に業務の引継ぎをしないときは、退職金を支給しない」などと定めることがあります。
このように、退職金を不支給とする制裁を定めることによって、間接的に引継ぎをするように導く会社も少なくなく、それ自体は違法ではないと解されます。
ただし、裁判例の傾向からは、会社が規定を設けているからといって、引継ぎ義務違反があれば、いつでも退職金を不支給とすることができる、という性質のものではないことに留意する必要があります。
一概にはいえませんが、裁判例の傾向からは、仮に引継ぎ義務違反があった場合でも、よほどの事情がない限り、退職金を不支給とすることは認められないものと解されます。
参考裁判例①(日本高圧瓦斯工業事件/大阪地方裁判所昭和59年7月25日判決)
会社の就業規則には、「会社は、従業員が円満なる手続により退職するときは、退職金を支給する」、「退職したときは直ちに業務の引継ぎをなす」という旨の定めがあったところ、営業所長であった従業員が、退職願の提出をせず、退職について会社の承認を得ず、さらに事務引継ぎをまったく行わずに退職したことから、会社が退職金を支給しなかった事案です。
裁判所は、「退職金が労基法所定の賃金に該当する場合には、懲戒解雇等、円満退職でない場合には退職金を支給しない旨の規定があっても、これが労働者に永年の勤続の功労を抹消してしまうほどの不信行為があった場合についての規定ならば、その限度で有効と解するのが相当であり、労働者に右のような不信行為がなければ退職金を支給しないことは許されない」と示しました。
そして、本事案では、会社が主張する事由は、従業員の退職についての手続規定違反を論難するものに過ぎず、従業員の永年勤続の功労を抹消してしまうほどの不信行為に該当するものといえないとして、会社に退職金の支払いを命じました。
参考裁判例②(帝国デンタル製作所事件/東京地方裁判所昭和59年3月6日判決)
従業員らが就業規則に定める一定の期間以前に退職届を提出せず、就業規則に定める手続を経ないで退職したことに対し、会社が退職金規程の要件に該当しないとして退職金を不支給とした事案です。
裁判所は、「就業規則の規定は、従業員の突然の退職による会社の業務上の不都合を防止するために、退職しようとする従業員に対して、退職希望日の一定期間前にその旨の届出をすべきことを命じたにすぎないものであって、ここに定められた期間を遵守するか否かによって、退職金請求権の存否が決せられるような性質の規定であると解することは到底できず、退職金規程の規定も就業規則の手続を経なければ退職金請求権が発生しないことを定めたものと解することはできない」として、退職金の支払いを命じました。
参考裁判例③(東京ゼネラル事件/東京地方裁判所平成11年4月19日判決)
支店長が無断で職場を離脱して職務を放棄し、業務の引継ぎを行わなかったため、会社が退職金を不支給とした事案において、会社は退職権ないし辞職権の濫用であり退職は無効と主張したのに対し、裁判所は、「支店長が意表を突く方法で職場を離脱したのは、穏当な方法で退職しようとすれば上司から激しい妨害を受け、退職の目的を遂げることができないと思ったことによるものと思われ、また憲法22条1項で職業選択の自由に連なる退職の自由があることを考えると、退職の意思表示を無効とすることはできない(退職は法的に有効であり、退職金を支払うべきである)」としました。
懲戒解雇による退職金の不支給
懲戒解雇と退職金不支給
会社は、退職金規程に、従業員が非違行為に基づき懲戒解雇されたことによって退職した場合には、退職金の全部または一部を不支給とする旨を定めることがあります。
退職金は、功労報償的な性格も有していることから、在職中の勤労の功を抹消ないし減殺するほどの重大な非違行為がある場合には、退職金を不支給とすることが認められると解されます。
ただし、退職金は賃金の後払い的な性格も有していることから、賃金の後払い的性格の傾向が強ければ、退職金を全額不支給とすることが認められない場合があります。
退職金規程の整備の必要性
退職金規程において、退職金不支給の事由として、「懲戒解雇された場合」とのみ定められていることがあります。
この場合、もし、従業員が退職した後に、懲戒事由に該当することが判明したとしても、裁判例によると、「退職金規程に基づく退職金の支給要件を満たす労働者がすでに退職した場合、使用者は、同労働者に対して懲戒解雇をすることができず、したがって、懲戒解雇による場合に退職金を不支給または減額にすることができる旨の退職金規程等の定めがあるとしても、この定めをもって直ちに退職金を不支給または減額にすることはできない」と解されます(ピアス事件/大阪地方裁判所平成21年3月30日判決)。
したがって、非違行為を理由とする退職金不支給を定める際には、「懲戒解雇された場合」という定めに加えて、「懲戒解雇に相当する行為をした場合」など、悪質な非違行為を行ったこと自体を事由として定めておくことが有用です。
また、退職金の支給後に、懲戒解雇事由に該当していたことが発覚することがあるため、退職金の支給後に、退職金の不支給事由が存在することが発覚した場合は、退職金の返還を義務付ける規定を設けておくことが必要です。
参考裁判例④(小田急電鉄(退職金請求)事件/東京高等裁判所平成15年12月11日判決)
電鉄会社の職員が、電車内での痴漢行為により逮捕・起訴され有罪となったことを理由とする懲戒解雇に伴い、退職金が不支給とされた事案です。
裁判所は、本件では、退職金支給規則に基づき、給与および勤続年数を基準として、支給条件が明確に規定されている場合には、その退職金は、賃金の後払い的な意味合いが強いとした上で、このような賃金の後払い的要素の強い退職金について、その退職金全額を不支給とするには、それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要であると示しました。
さらに、「それが業務上の横領や背任など、会社に対する直接の背信行為とはいえない職務外の非違行為である場合には、それが会社の名誉信用を著しく害し、会社に無視しえないような現実的損害を生じさせるなど、上記のような犯罪行為に匹敵するような強度な背信性を有することが必要であると解される」と示しました。
そして、職員に対する退職金不支給につき、痴漢行為は決して軽微な犯罪とはいえないが、永年の勤続の功を抹消するほどの重大な背信行為とまではいえないとして、会社に退職金の3割に当たる額の支払いを命じました。
参考裁判例⑤(みずほ銀行事件/東京高等裁判所令和3年2月24日判決)
銀行員が、対外秘である行内通達などを多数社外に持ち出し、出版社などに漏洩したことを理由に懲戒解雇され、これに伴い退職金を不支給とされた事案において、裁判所は、「銀行員による情報漏洩行為は、その具体的態様等に照らすと銀行の信用を大きく毀損する悪質性の高い行為というべきであり、同人の退職金を全部不支給とすることが裁量権の濫用に当たるとはいえない」と判断しました。
参考裁判例⑥(伊藤忠商事ほか事件/東京地方裁判所令和4年12月26日判決)
従業員が、他社へ転職する直前の時期に、機密情報を含むファイルを自己のアカウントにアップロードしたため、機密保持違反などを理由に懲戒処分を受け、退職金を不支給とした事案です。
裁判所は、本件アップロード行為の悪質性、退職が決まった従業員による非違行為を抑止する上での必要性のほか、従業員の勤務年数が5年に満たないものであることからすれば、退職金に賃金の後払いとしての性質があることを踏まえても、従業員が会社において就労した間の功労を覆滅するに足りる著しい背信行為をしたものとして、退職金を不支給とするのもやむを得ないと判断しました。
競業避止義務違反による退職金不支給
競業避止義務違反とは
「競業避止義務」とは、一般に、従業員が、競業行為によって、会社の不利益になるようなことをしてはならない義務をいいます。
競業行為は、従業員が競合する他社に転職し、あるいは自分で競合する事業を起業する場合に生じることがあります。
競業避止義務への違反は、一般的に退職後に生じることが多いため、その抑止力を担保するために、違反に対する制裁として、退職金を不支給(既に支払った場合には、返還を求める)とすることを定める場合があります。
ただし、退職金には、在職中の功労に報いるという性質もあるため、退職後の行為によって、退職金の全額を当然に不支給にすることは認められません。
参考裁判例⑦(三晃社事件/最高裁判所昭和52年8月9日判決)
競業避止義務違反があった場合には、退職金の支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額にするという特約があった事案で、裁判所は、本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできず、この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されることから、当該特約を有効と判断しました。
参考裁判例⑧(野村證券元従業員事件/東京地方裁判所平成28年3月31日判決)
証券会社が、元従業員との間で、会社を退職する際、同業他社に転職した場合は返還する旨の合意をして退職加算金を支給したものの、従業員が退職して1年8ヵ月後に同業他社に転職したとして、上記返還合意に基づき、退職加算金の返還を求めた事案です。
裁判所は、「退職金の返還合意は、自己都合退職する一定年齢の社員に対して会社の承認を条件として通常の退職慰労金に加えて退職加算金を支給するという制度に基づく退職加算金の支給に伴うものであるところ、同制度の利用は従業員の自由な判断にゆだねられており、返還合意は従業員に対して同業他社に転職しない旨の義務を負わせるものではなく、また、同制度は返還合意を考慮しても通常の退職よりも有利な選択肢であるということができるから、同制度のうち返還合意だけを取り上げて退職後の職業選択の自由を制約する競業禁止の合意であると評価することはできず、転職が禁止される期間や同業他社の地域等に限定が付されていないことを考慮しても、返還合意が公序良俗に違反するとは認められない」としました。
そして、「前記元従業員の就職先が前記会社のグループ会社であること、退職してから1年8ヵ月を経過していたこと、同業他社での就業が4ヵ月と比較的短期間にとどまったこと、その間の収入が退職加算金の額を大幅に下回ることを十分に考慮しても、会社の請求が権利の濫用であると評価することはできないというべきである」として、会社の請求を認めました。
参考裁判例⑨(日本リーバ事件/東京地方裁判所平成14年12月20日判決)
化粧品の製造販売等を業とする会社のマネージャーの地位にあった従業員が、会社が開発を検討していた商品のデータを漏洩し、同業他社への転職が内定した後で会社の機密事項を扱う会議に出席し、そこで入手した資料を持ち出した事案です。
裁判所は、従業員の行為は極めて背信性が高いとして、同人に対する懲戒解雇を有効と判断し、懲戒解雇事由は、長年の功労を否定し尽くすだけの著しく重大なものであるとして、同人への退職金の不支給は正当であると判断しました。