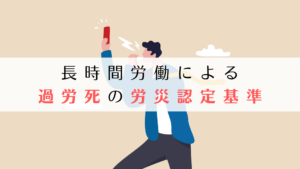育児・介護休業取得者の業務を代替する者への手当・賞与|制度設計のポイント、就業規則の規定例(記載例)などを解説【業務代替手当・育児休業サポート手当など】
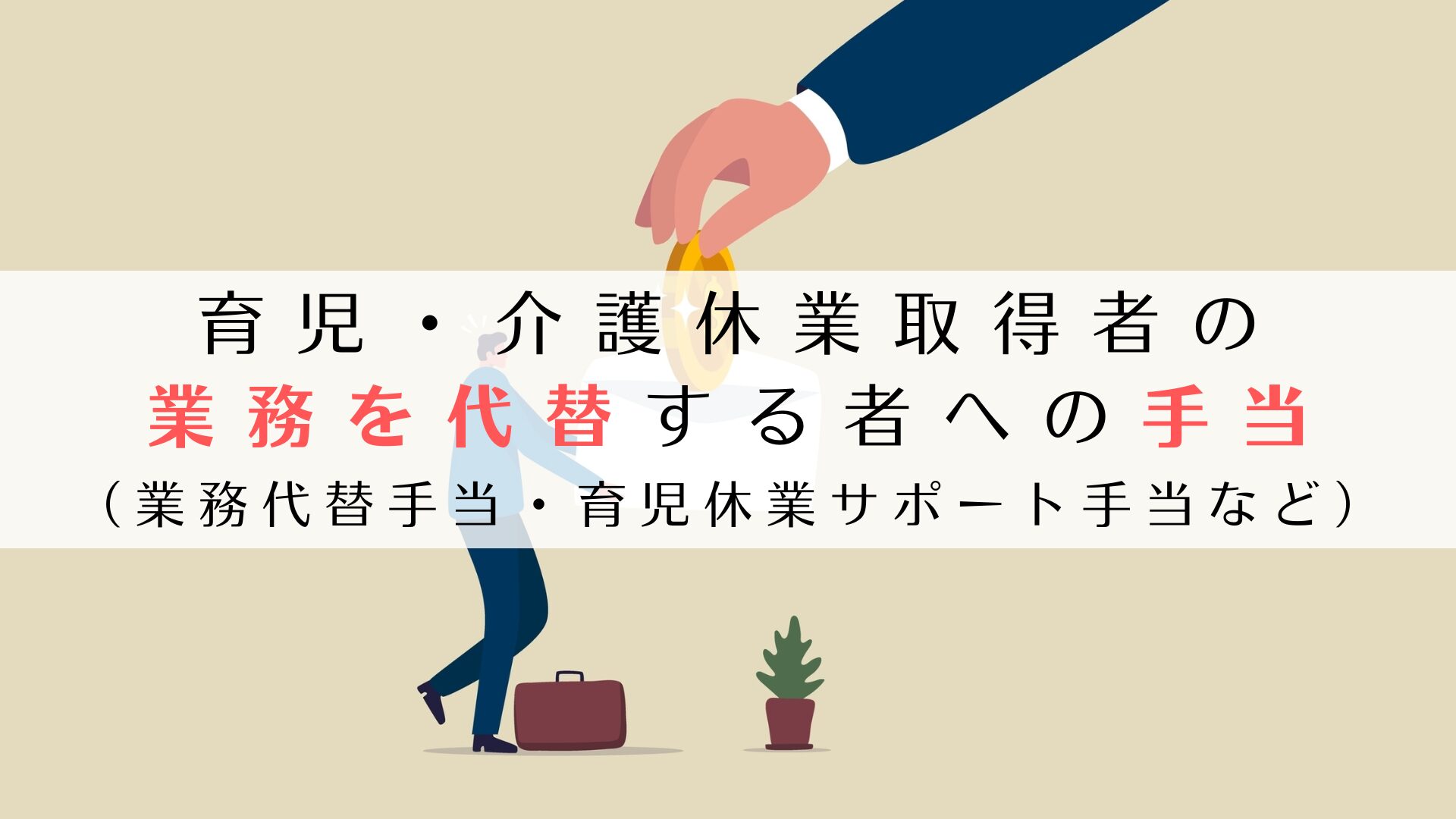
- 1. はじめに
- 2. 手当・賞与の支給目的
- 2.1. 手当・賞与の支給目的
- 2.2. 手当・賞与の名称
- 3. 制度設計のポイント①【支給方法】
- 3.1. 「手当(月額)」によって支給する場合
- 3.2. 「賞与」によって支給する場合
- 3.3. 「一時金」によって支給する場合
- 4. 制度設計のポイント②【対象者】
- 4.1. 対象となる休業
- 4.2. 手当などの支給対象者
- 4.3. 制度の適用除外
- 5. 制度設計のポイント③【社会保険料・割増賃金への影響】
- 5.1. 社会保険料
- 5.2. 割増賃金(労働基準法)
- 6. 企業の導入事例
- 7. 手当(月額)として支給する場合の就業規則の規定例(記載例)
- 7.1. 手当の対象となる休業・手当の額に関する規定例(記載例)
- 7.2. 手当の額の算定に関する規定例(記載例)
- 7.2.1. 手当の額を代替業務を行う者の頭数で割る場合
- 7.2.2. 手当の額を代替業務の負担割合で按分する場合
- 7.3. 手当の支給期間に関する規定例(記載例)
はじめに
近年、従業員が育児・介護休業を取得する場合において、その従業員が担当していた業務を代わりに行う職場の同僚や上司などに対し、手当や賞与などの金銭的報酬を支払う企業があります。
手当の名称や制度設計は、企業によって様々ですが、共通する主な目的としては、育児・介護休業の取得を職場が応援し、誰もが気兼ねなく育児・介護休業を取得できる企業風土(社風)を醸成することにあります。
本稿では、育児・介護休業取得者の業務を代替する者に対し、手当や賞与などを支給する場合における制度設計のポイント、就業規則の規定例(記載例)などを解説します。
手当・賞与の支給目的
手当・賞与の支給目的
近年では、男性の育児休業取得率が増加傾向にあるなど、全体としては、育児・介護休業の取得について、職場の理解を得やすくなってきているといえます。
しかし、実際には、育児・介護休業を取得することで、休業期間中において、業務を代わりに行う職場の同僚や上司の業務負担が増えることがあるため、周囲に気兼ねしてしまい、育児・介護休業の取得を躊躇してしまうことがあります。
また、業務を代替する職場の同僚や上司などにとっても、休業期間中の業務負担が増えることに対し、不満を感じることがあります。
そこで、育児・介護休業取得者の業務を代替する者に対し、手当や賞与など金銭的報酬を支払うことで、育児・介護休業の取得を応援する企業風土(社風)を醸成していこうとする動きがあります。
また、副次的には、業務を代替する前提として、休業する従業員が行う業務の棚卸しを行う必要があるため、業務にかかるマニュアル作成やプロセスの見直しなどによる作業効率の向上、および属人化を防止することなどにもつながるというメリットがあります。
手当・賞与の名称
制度を導入する場合において、手当や賞与の名称は、どのような名称でも構いません。
例えば、手当として支給する場合の名称として、「業務代替手当」、「育児休業応援手当」、「育児休業サポート手当」などがあり、賞与(または一時金)として支給する場合の名称として、「報奨金」、「祝い金」などが挙げられます。
傾向としては、名称には、育児・介護休業取得者に対する「応援」や「サポート」というキーワードが含まれることが多いように思います。
制度設計のポイント①【支給方法】
金銭の支払方法としては、手当(月額)、賞与または一時金で支給する方法が考えられますが、それぞれ、制度設計の検討にあたり、次の点がポイントになります。
「手当(月額)」によって支給する場合
手当(月額)によって支給する場合には、手当の額、および支給期間を明確にする必要があります。
手当の額については、特に法律上の制約はありませんので、いくらであっても構いません。
また、手当の支給期間については、手当を支給する趣旨から、育児休業などを開始した時点から支給を開始することが一般的といえます。
ただし、必ずしも休業期間のすべてを支給対象とする必要はなく、例えば、手当の支給期間の上限を6ヵ月から1年程度としている事例があります。
「賞与」によって支給する場合
賞与によって支給する場合には、①あらかじめ具体的な支給額(10万円など)を定めておく制度設計と、②具体的な支給額は定めず、評価(考課)のポイントを上乗せするなどして、賞与制度(評価制度)の枠組みの中で、賞与額を増額する制度設計が考えられます。
なお、賞与には、通常、算定対象期間が設けられていることから、賞与の算定対象期間中のうち、代替業務を行った期間に応じて、支給額を変えることも考えられます。
「一時金」によって支給する場合
手当や賞与によって支給する方法以外にも、祝い金などの名目で、一時金を支給することも考えられます。
この場合、育児休業などを開始したタイミング、または休業から復帰したタイミングなどで支給することが考えられます。
手当や賞与として支給する場合と比べると、支給時期を柔軟に設定でき、また、制度設計をシンプルにしやすいメリットがあると考えます。
制度設計のポイント②【対象者】
手当や賞与の支給対象者については、制度設計の検討にあたり、次の点がポイントになります。
対象となる休業
手当や賞与の支給対象となる休業の範囲について、あらかじめ定めておく必要があります。
例えば、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業、介護休業、私傷病休職などのうち、どの休業を対象とするかを明確にしておく必要があります。
また、休業期間について、例えば、1ヵ月以上の休業を対象とするなどの基準を定めておくことも考えられます。
手当などの支給対象者
手当や賞与などの支給対象者として、休業を取得した者の職場の全員を支給対象とするのか、または代替業務を行う者のみを対象とするのかを決めておく必要があります。
また、後者の場合、業務を引き継いだ者が複数人いる場合には、①手当や賞与を全員一律に(同額を)支給するのか、②手当や賞与の上限額を定めておいて頭数で割るのか(例えば、支給額の上限を3万円とし、代替業務を行う者の頭数で割るなど)、③業務を負担している割合に応じて按分するのかなどを決めておく必要があります。
【手当の支給方法(例)】
| 支給方法 | 支給例 (代替業務を行う者が3人の場合) |
| 一律に同じ手当の額を支給する | 代替業務を行う者3人に対し、それぞれ1万円の手当を支給するなど(代替業務を行う者の人数は、手当の額に影響しない) |
| 手当の額を代替業務を行う者の頭数で割る | 手当の上限額3万円を、代替業務を行う者の頭数である3で割り、それぞれ1万円の手当を支給するなど |
| 手当の額を代替業務の負担割合で按分する | 手当の上限額3万円を、代替業務を行う者の負担割合である4:4:2で按分するなど |
制度の適用除外
職場の同僚や上司が業務を代替するのではなく、代替要員を新たに雇用した場合(派遣で確保した場合など)には、制度の対象外とすることが一般的といえます。
また、育児休業などの取得者が、休業期間中に退職した場合には、それ以降は手当や賞与の支給を行わないとすることが考えられます。
制度設計のポイント③【社会保険料・割増賃金への影響】
社会保険料
育児・介護休業取得者の業務を代わりに負担する者(同僚など)に対し、手当や賞与など金銭的報酬を支払う場合には、当該手当または賞与は、労働の対償として支給されるものであることから、社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料など)の対象になると解されます。
手当で支給する場合には、定時決定や随時改定によって標準報酬を算定した上で、各月の社会保険料を納付します。
また、賞与または一時金で支給する場合には、当該賞与または一時金を支給する際に、標準賞与として社会保険料を算定して納付します。
割増賃金(労働基準法)
育児・介護休業取得者の業務代替を行う者に対し、毎月手当を支給する場合には、当該手当は割増賃金の算定の基礎となる賃金に該当することから、当該手当を含めて、割増賃金の計算および支払いを行う必要がある(手当の支給に伴って割増賃金が増額する)ことに留意する必要があります。
企業の導入事例
参考に、公表されている企業の導入事例を掲載します(リリース当時の情報です)。
| 社名 (導入時期) | 名称 | 制度の概要 | |
| 1 | G社(2022年10月) | 子育て休業応援手当 | 育児休業・介護休業(最低1ヵ月以上)を取得する者の担当業務を引き継ぎ、業務が増加する従業員への対価として、引き継ぎ者に最高で月額10万円の手当を支給する(支給期間は最大6ヵ月) |
| 2 | M社(2023年7月) | 育休職場応援手当 | 育児休業取得者本人を除く職場全員に、職場の人数規模等に応じて、3,000円から最大10万円の一時金を支給する |
| 3 | O社 (2024年4月) | 育休サポート報奨金 | 1ヵ月以上連続の育児休業を取得した従業員(男女は問わない)1人につき最大10万円の一時金を、当該育児休業の取得をサポートした従業員に分配して支給する |
| 4 | T社 (2024年5月) | 育休等職場応援祝金 | 従業員の産前産後休業・育児休業期間における、業務の代替者に対して賞与支給のタイミングと合わせて祝金を支給する。 業務の代替者が複数いる場合は、総額を均等に配分して支給する(産前産後休業・育児休業の取得期間が1ヵ月以上の場合は10万円、2ヵ月以上の場合は20万円、12ヵ月以上の場合は40万円) |
| 5 | D社(2025年4月) | 育児介護応援手当 | 育児・介護休業を連続1ヵ月以上取得する従業員の休業開始月において同じ課またはチームに所属する従業員に対し、賞与(6月・12月の年2回)を支給する(支給額は、休業期間が1ヵ月以上3ヵ月未満の場合は2万円、3ヵ月以上の場合は3万円) |
手当(月額)として支給する場合の就業規則の規定例(記載例)
手当の対象となる休業・手当の額に関する規定例(記載例)
手当の対象となる休業・手当の額に関する規定例
(業務代替手当)
第1条 会社は、育児・介護休業規程に定める育児休業(出生時育児休業を含む)または介護休業を1ヵ月以上取得した従業員(以下、「休業取得者」という)がある場合、その休業期間中において、休業取得者が行っていた業務を代替して行う従業員(以下、「支給対象者」という)に対して、業務代替手当として、月額30,000円を支給する。
2 前項の手当は、休業取得者の業務を代替するために新たな人員を配置した場合には支給しない。
手当の額の算定に関する規定例(記載例)
手当の額を代替業務を行う者の頭数で割る場合
手当の額の算定に関する規定例(手当の額を代替業務を行う者の頭数で割る場合)
(業務代替手当の分配)
第2条 業務代替手当は、休業取得者の業務を複数人で分担することにより、支給対象者が複数いる場合には、第1項の額を支給対象者の頭数で除した額(計算の結果100円未満の端数が生じた場合は、100円に切り上げる)とする。
手当の額を代替業務の負担割合で按分する場合
手当の額の算定に関する規定例(手当の額を代替業務の負担割合で按分する場合)
(業務代替手当の分配)
第2条 業務代替手当は、業務を分担することにより、支給対象者が複数いる場合には、所属長が各支給対象者の業務量等を勘案して負担割合を決定し、業務代替手当を当該負担割合によって按分した額(計算の結果100円未満の端数が生じた場合は、100円に切り上げる)とする。
手当の支給期間に関する規定例(記載例)
手当の支給期間に関する規定例
(業務代替手当の支給期間)
第3条 業務代替手当は、第1条第1項に定める休業が開始した日の属する賃金計算期間から支給を開始する。賃金計算期間の途中から休業を開始し、または終了する場合は、手当の額を30日で除した額を日額として、休業日数に応じて日割り計算した額を支給する。
2 業務代替手当は、第1条第1項に定める休業が終了した日、または次の各号に定める日のうち、もっとも早い日の属する賃金計算期間まで支給する。
一、休業取得者の業務を代替するために新たな人員を配置した日
二、休業取得者が退職した日
三、休業開始日から1年が経過した日