【フレックスタイム制】「3ヵ月の清算期間」を定める場合の留意点や手続などを解説
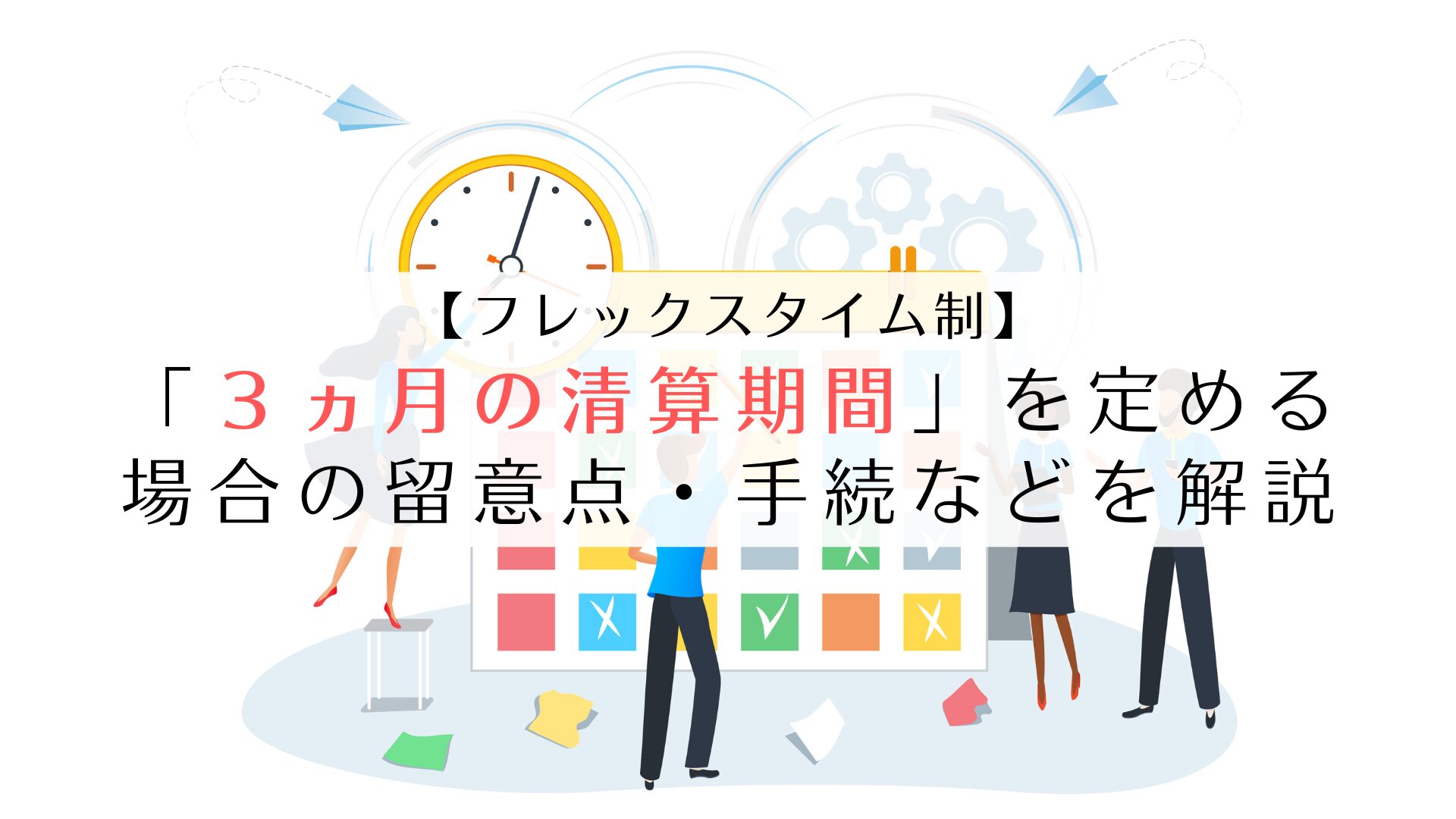
はじめに
従来、フレックスタイム制を運用する場合における清算期間は1ヵ月以内とされていましたが、より柔軟な働き方の選択を可能にするために、2019年4月1日施行の法改正により、最大3ヵ月までの清算期間を定めることができるようになりました。
本稿では、1ヵ月を超え、3ヵ月以内の清算期間を定めるフレックスタイム制を運用する場合の留意点や手続などを解説します。
なお、フレックスタイム制の基本的な制度内容については、次の記事をご覧ください。
「フレックスタイム制」とは?制度の内容・導入手続(就業規則・労使協定)をわかりやすく解説
フレックスタイム制とは
「フレックスタイム制」とは、一定の期間(最大3ヵ月とし、これを「清算期間」といいます)の総労働時間をあらかじめ定めておき、従業員がその範囲内で、日々の始業・終業時刻を自ら決定して働くことができる制度をいいます(労働基準法第32条の3)。
法定労働時間の総枠(清算期間が1ヵ月以内の場合)
清算期間における総労働時間(後述)は、法定労働時間に基づいて算出された労働時間の限度(以下、「法定労働時間の総枠」といいます)に収める必要があります。
清算期間における法定労働時間の総枠は、次の計算によって算出します。
清算期間における法定労働時間の総枠
1週間の法定労働時間×清算期間の暦日数÷7日
「1週間の法定労働時間」は、原則として、40時間となります(労働基準法第32条第1項)。
なお、特例措置対象事業場については、「44時間」が1週間の法定労働時間となります。
「清算期間の暦日数」は、暦月1ヵ月を清算期間とする場合には、28日から31日までの日数となります。
例えば、4月(暦日30日)を清算期間とする場合には、法定労働時間の総枠は、171.4時間(40時間×30日÷7日)となります。
【図】法定労働時間の総枠(清算期間が1ヵ月以内の場合)
| 清算期間(1ヵ月)の暦日数 | 法定労働時間の総枠 |
| 31日 | 177.1時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 28日 | 160.0時間 |
清算期間における総労働時間(所定労働時間)
フレックスタイム制を運用する場合には、清算期間ごとに「総労働時間」を定める必要があります。
清算期間における「総労働時間」とは、労働契約に基づき、清算期間において労働すべき時間として定められた、所定労働時間をいいます。
そして、所定労働時間は、法定労働時間を超えて定めることはできないことから、総労働時間(所定労働時間)は、法定労働時間の総枠を超えて定めることはできません。
例えば、4月(暦日30日)を清算期間とする場合、前述のとおり、法定労働時間の総枠は171.4時間ですが、当該清算期間における総労働時間(所定労働時間)は、必ず171.4時間以内に収める必要があるということです。
法定労働時間の総枠と、総労働時間(所定労働時間)の関係
法定労働時間の総枠≧総労働時間(所定労働時間)
なお、清算期間における総労働時間(所定労働時間)の定め方としては、例えば、「1ヵ月160時間」などと各清算期間を通じて一律の総労働時間を定める場合のほか、各清算期間における所定労働日に、標準となる1日の労働時間(1日あたり8時間など)を乗じて総労働時間を定める場合などがあります。
1ヵ月を超える清算期間とすることのメリット
清算期間を1ヵ月以内とする場合には、清算期間における実労働時間が、あらかじめ定めた総労働時間(所定労働時間)に達しないときは、原則として欠勤扱いとなり、賃金が控除されることとなります。
すると、仕事を早く終わらせた場合にも、欠勤扱いとならないようにするために、総労働時間に達するまでは働かなければなりません。
これに対し、清算期間を2ヵ月や3ヵ月とすることで、業務量や労働者の生活事情などに合わせて、労働時間の調整を行いやすくなるというメリットがあります。
例えば、4月は繁忙期、6月は閑散期であるような場合には、4月から6ヵ月までの3ヵ月を清算期間とすることで、4月に多く働いた分、6ヵ月の労働時間を少なくするといった調整ができるようになります。
清算期間が1ヵ月を超える場合の上限時間
清算期間における法定労働時間の総枠
清算期間が1ヵ月を超える場合であっても、法定労働時間の総枠を算出するための計算式は同じです。
ただし、清算期間が1ヵ月を超える場合には、特例措置対象事業場であっても、法定労働時間の総枠を求める際における1週の法定労働時間は「週40時間」となる点に留意する必要があります(特例の「週44時間」を適用することは認められません)(労働基準法施行規則第25条の2第4項)。
清算期間が1ヵ月を超える場合には、清算期間を通じた法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働となります。
時間外労働を行う場合には、36協定を締結した上で、割増賃金を支払う必要があります。
【図】法定労働時間の総枠(清算期間が2ヵ月単位または3ヵ月単位の場合)
| 2ヵ月単位 | 3ヵ月単位 | ||
| 清算期間(2ヵ月)の暦日数 | 法定労働時間の総枠 | 清算期間(3ヵ月)の暦日数 | 法定労働時間の総枠 |
| 62日 | 354.2時間 | 92日 | 525.7時間 |
| 61日 | 348.5時間 | 91日 | 520.0時間 |
| 60日 | 342.8時間 | 90日 | 514.2時間 |
| 59日 | 337.1時間 | 89日 | 508.5時間 |
1ヵ月ごとの労働時間の上限
清算期間が1ヵ月を超える場合には、過重労働を防止するために、法定労働時間の総枠とは別に、各月における上限時間が設けられています。
清算期間が1ヵ月を超える場合には、その清算期間を1ヵ月ごとに区分した各期間(最後に1ヵ月未満の期間を生じたときには、その期間)ごとに、その期間を平均して1週間あたりの労働時間が50時間を超えることができません(労働基準法第32条の3第2項)。
具体的には、次の計算式によって算出した時間が上限となります。
各月における上限時間
50時間×各月における暦日数÷7日
上記の上限時間を超えた労働時間は、時間外労働となり、36協定の締結および割増賃金の支払いが必要となります。
このため、月によって繁閑差が大きい場合であっても、繁忙月にあまりに偏って働くことはできません。
なお、清算期間の最後に1ヵ月に満たない期間が生じた場合には、その期間について週平均50時間を超えないようにする必要があります。
【図】週平均が50時間となる月間の労働時間数
| 月の暦日数 | 週平均が50時間となる月間の労働時間数 |
| 31日 | 221.4時間 |
| 30日 | 214.2時間 |
| 29日 | 207.1時間 |
| 28日 | 200.0時間 |
整理
以上を整理すると、清算期間が1ヵ月を超える場合には、次の2つの時間が、それぞれ時間外労働として把握されることとなります。
清算期間が1ヵ月を超える場合の時間外労働
- 1ヵ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間
- 清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
事例
事例として、4月から6月までの3ヵ月間を清算期間と定めた場合において、結果として、実際の労働時間(実労働時間)が次のようになったケースをみていきます。
【事例】4月から6月までの実労働時間
| 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
| 実労働時間 | 220時間 | 180時間 | 140時間 | 540時間 |
各月における週平均50時間を超える労働時間数の把握
まずは、1ヵ月ごとに、各月の平均労働時間が50時間を超える労働時間を把握し、時間外労働としてカウントします。
| 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
| 実労働時間 | 220時間 | 180時間 | 140時間 | 540時間 |
| 週平均が50時間となる月間の労働時間数 | 214.2時間 | 221.4時間 | 214.2時間 | |
| 時間外労働 | 5.8時間 | - | - | 5.8時間 |
事例では、4月において、週平均が50時間となる月間の労働時間数を超えていますので、5.8時間の時間外労働をカウントします。
これにより、4月の賃金支払い日において、5.8時間の時間外労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
法定労働時間の総枠を超えて労働した時間の把握
| 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
| 実労働時間 | 220時間 | 180時間 | 140時間 | 540時間 |
| 法定労働時間の総枠 | 520時間 | 520時間 | ||
| 時間外労働 | - | - | - | 20時間 |
4月から6月までの暦日数は91日であることから、清算期間における法定労働時間の総枠は、520時間(40時間×91日÷7日)となります。
すると、清算期間を通じて、20時間(540時間-520時間)の時間外労働が生じていることになりますが、このうち、すでに4月に5.8時間の時間外労働をカウントし、割増賃金を支払っています。
そこで、6月の賃金支払い日においては、20時間から5.8時間を差し引いた、14.2時間の時間外労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
清算期間を通じた時間外労働の把握方法
清算期間を通じた時間外労働=清算期間を通じた実労働時間-各月において週平均50時間超過分として清算した時間外労働の合計-清算期間における法定労働時間の総枠
(事例の当てはめ)
14.2時間=540時間-5.8時間-520時間
清算期間の途中で入退社があった場合
清算期間が1ヵ月を超える場合に、中途入社や途中退職などによって、実際に労働した期間が清算期間よりも短い労働者については、その期間において清算を行う必要があります。
このとき、実際に労働した期間を平均して、週40時間を超えて労働していた場合には、その超えた時間が時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります(労働基準法第32条の3の2)。
例えば、労働者の清算期間中の労働期間が45日であった場合には、その期間の労働時間が257.1時間(40時間×45日÷7日)を超えているときは、その超えた時間が時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
導入手続
清算期間が1ヵ月を超える場合には、フレックスタイム制にかかる労使協定届(様式第3号の3)を、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります(労働基準法第32条の3第4項)。
これに違反した場合の罰則として、30万円以下の罰金が定められています。
なお、清算期間が1ヵ月以内の場合には、届出は不要です。
【図】清算期間による手続の違い
| 1ヵ月以内の清算期間 | 1ヵ月を超え3ヵ月以内の清算期間 | |
| 就業規則への定め | 必要 | 必要 |
| 労使協定の締結 | 必要 | 必要 |
| 労使協定の届出 | 不要 | 必要 |


