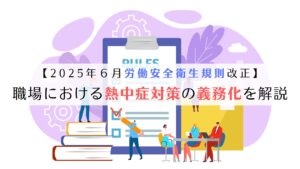【私傷病休職】「復職」の可否を判断する際の留意点(医師の診断書、リハビリ勤務など)を解説
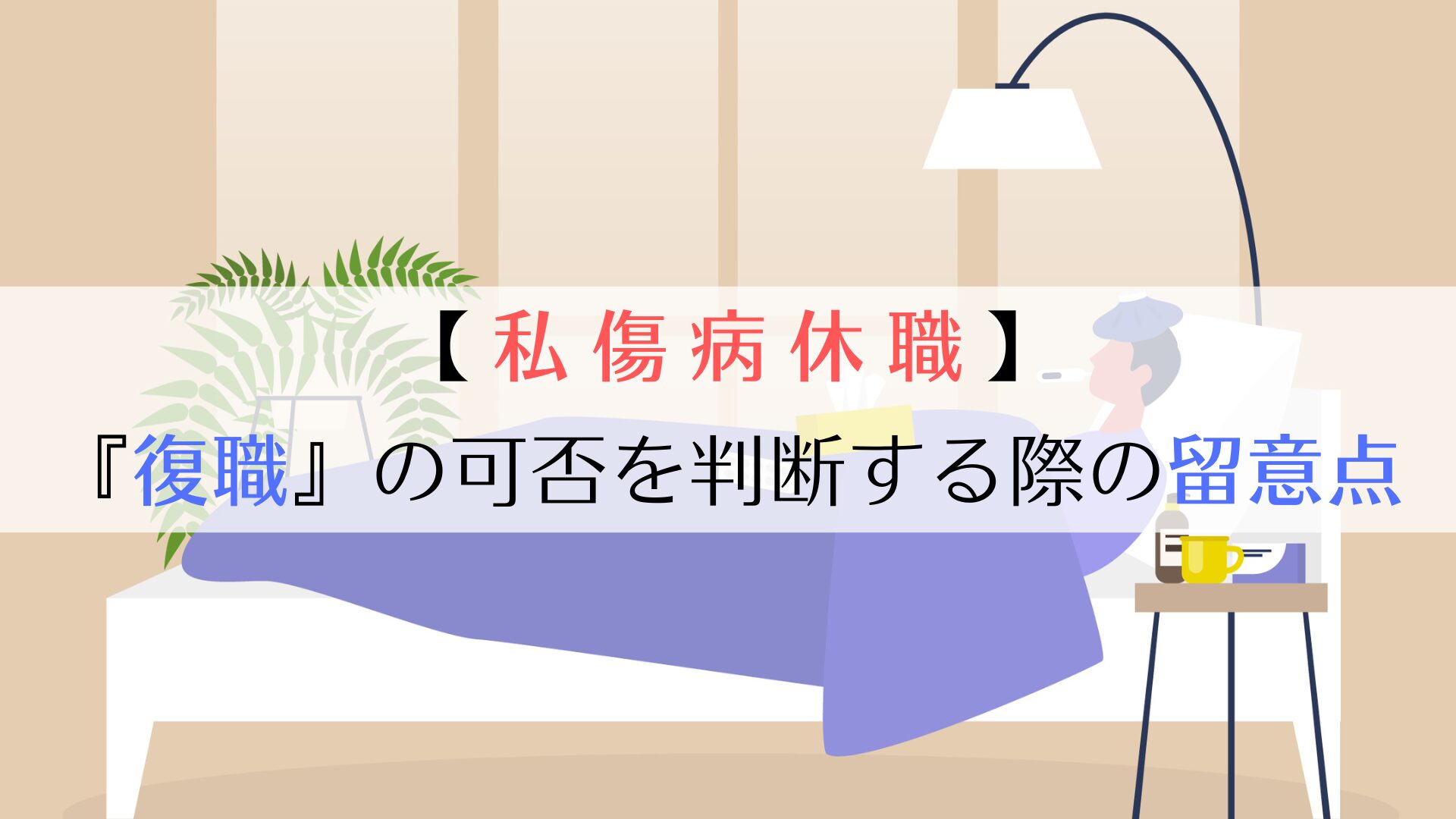
私傷病休職と復職
私傷病休職とは
「休職」とは、一般に、従業員が私傷病などの事由によって、長期間にわたって業務を行うことができない場合(労務不能の場合)に、従業員としての身分を保ったままで、会社が一定期間の就労を免除することをいいます。
「私傷病休職」とは、一般に、業務上の理由に基づかない、従業員の心身の病気・ケガなどの療養のために休職することをいいます。
従業員が私傷病によって労務を提供できない状況が続けば、労働契約を終了する(解雇する)ことを検討せざるを得ませんが、労務を提供できなくなった時点ですぐに解雇することは、現実的ではありません。
そこで、休職制度を設けることにより、いわば一定期間の解雇の猶予を行うことで、雇用の安定を図ることが、労務管理における慣習として根付いています。
私傷病休職と復職
会社の就業規則では、一般的に、休職期間満了時において、私傷病が治癒していて復職ができる状態であれば、復職を命じ、復職ができない状態であれば、自然退職または普通解雇とする定めが設けられています。
従業員にとって、休職期間の満了日までに復職できないことは、退職する(または解雇される)ことを意味するため、復職の可否は死活問題であり、復職の可否をめぐっては、労務トラブルに発展しやすい傾向があります。
復職可能な状態にあることの立証責任
まず、私傷病休職において、「復職可能な状態にある(私傷病が治癒しており、労務の提供ができる状態にある)」ことを立証する責任は、労使のどちらが負うのか、という問題があります。
この点、裁判例では、「休職期間満了前の休職原因の消滅は、労務の提供ができなかったにもかかわらず、解雇権を留保されていた、労働者が主張立証責任を負うと解するのが相当である」として、復職可能な状態にあることは、原則として、従業員(休職者)が立証責任を負うものと解されます(株式会社綜企画設計事件/東京地方裁判所平成28年9月28日判決)。
また、別の裁判例でも、休職期間満了までに債務の本旨に従った労務提供ができる程度に症状が回復したことについては、従業員(休職者)が主張立証責任を負うとしています(伊藤忠商事事件/東京地方裁判所平成25年1月31日判決)。
したがって、休職していた従業員は、復職可能な所見が記載された主治医の診断書を提出するなど、自ら休職事由が消滅した事実を明らかにしなければならず、休職期間が満了したからといって、当然に復職できるものではありません。
裁判例では、業務外の交通事故による受傷を理由とした私傷病休職について、休職期間満了による退職通知を受けた従業員が、退職通知は復職の可能性、意思について審査することなく一方的にされた解雇であって、解雇権の濫用であると主張して退職の効力を争った事案において、「退職通知をするに際して、会社が専門医師による休職者の診断を求めようとしたことは窺われないが、従業員においても復職申出の趣旨に沿う休職事由の消滅の事実を明らかにしたことは窺われない」と示し、さらに退職通知は、1年8ヵ月以上の長期間、従業員(休職者)に就労の形跡・就労の意思が認められない状況のもとでなされたことに鑑み、「会社が専門医師による診断を求めなかったからといって、これが退職通知の効力に影響を及ぼすものではないというべきであり、退職通知が権利濫用に当たるということはできない」と判断しました(タカラ事件/東京地方裁判所平成4年9月8日判決)。
復職の判断と会社の安全配慮義務
復職の判断の権限
復職を認めるかどうかの判断を行う権限は、最終的に、人事権を有する会社にあります。
復職の可否を判断し、復職命令を行うことは、会社の人事権の行使であり、従業員(休職者)、主治医、産業医などが権限を有するものではありません。
復職の判断と会社の安全配慮義務に関する裁判例
会社は、従業員に対し、安全配慮義務を負っており、復職が可能なほど回復していないのに復職させることにより、傷病が再発し、悪化した場合には、会社は安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負うことがあります(労働契約法第5条)。
復職の判断において、会社が安全配慮義務に違反するとした裁判例として、会社が、休職していた従業員からの復職の申し出に対し、精神状態や身体的状態等について、主治医の医学的所見を得るなど、専門的な立場からの助言等を何ら踏まえることなく、単に、上司と面談しただけで、漫然と職場復帰を決めた事案があります。
裁判所は、会社は、従業員が精神科に通院して抗うつ剤や睡眠導入剤の処方を受けていることを本人から聴取するとともに、職場の人間関係に不和と思わしき状況が存在して精神的負担を感じていたことや、過去に自殺未遂をしたことを認識しており、従業員の精神状況が危機的な状況に陥っていることを容易にうかがい知ることができたにもかかわらず、医師から進言された臨床心理士との面談実施等の具体的な措置を取らず、また、主治医等の医学的所見を聴取する等の措置を講ずることなく安易に職場復帰を決定しており、同従業員に対する安全配慮義務を怠ったと認められるとして、会社の損害賠償責任(約3,000万円)を認めました(市川エフエム放送事件/東京高等裁判所平成28年4月27日判決)。
医師(主治医)の診断書について
医師(主治医)の診断書の位置付け
通常、従業員(休職者)が復職を願い出る際の手続きとして、私傷病が治癒していて、元の職務に復帰できることを証明するために、主治医の診断書を提出することが一般的です。
このとき、会社が、主治医の診断書に記載された診断結果のみをもって復職を判断することは、適切ではない場合があります。
主治医は、休職中の従業員を長く診ていますが、当該従業員の会社における業務のことを、正確に把握していない場合があります。
復職が可能か否かの判断は、「会社での通常業務を問題なく遂行できるまでに回復したかどうか」という判断である以上、同じ病状であっても、ある会社(業務)では復職できるけれども、別の会社(業務)では復職できない、ということがあり得ます。
また、主治医の診断結果は、患者である従業員の意向に影響されやすいことも懸念されます。
そこで、会社は、従業員(休職者)の業務内容をよく把握している立場である産業医の診断を求めるなど、客観的立場にある専門医から、主治医の診断結果を裏付けるための診断や意見を提出してもらうことが重要となります。
参考裁判例
参考となる裁判例として、会社が主治医の診断書の診断結果を採用せず、復職を認めなかった事案について、会社の判断を尊重した裁判例があります。
事業者への保証・保険の信用補完や貸付け等を行う法人の職員が、主治医の診断書で「現時点で当面業務内容を考慮した上での通常勤務は可能である」とされていました。
しかし、裁判所は、本事案では、主治医の診断書について、「法人の復職に対する対応により、職員の症状に対する診断が変わるというのは不可解である」として、法人による復職を認めないとの判断を尊重しました。
そして、当該職員につき、2年6ヵ月の休職期間満了時において、法人の職員が通常行うべき金融・財務に関する判断を伴う職務を遂行しうる状態にあったとは認められず、また、当初軽易な職務に就かせればほどなく当該職務を通常に行うことができたとも認められないとされ、休職期間満了による解雇を有効と判断しました(独立行政法人N事件/東京地方裁判所平成16年3月26日判決)。
「治癒」の定義とリハビリ勤務の必要性
「治癒」の定義
従業員(休職者)が復職するための条件として、私傷病が治癒していることが必要となります。
裁判例では、「治癒」とは、「病気休職者が、従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したときをいう」としています(平仙レース懲戒解雇事件/浦和地方裁判所昭和40年12月16日判決)。
また、別の裁判例では、「業務外傷病により休職した労働者について、休職事由が消滅した(治癒した)というためには、原則として、休職期間満了時に、休職前の職務について労務の提供が十分にできる程度に回復することを要し、このことは、業務外傷病により休職した労働者が主張・立証すべきものと解される」としています(アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド事件/東京地方裁判所平成26年11月26日判決)。
リハビリ勤務の必要性
実務上、「治癒」の判断において問題となるのは、例えば、復職した初日から通常勤務に戻ることが難しく、少しの期間、リハビリ勤務を要する場合です。
このような場合に、会社がリハビリ勤務を認めなければならないのかどうか、問題となります。
裁判例の傾向では、リハビリ勤務について、当初軽易な職務に就かせれば、程なく従前の職務を通常に行うことができると予測できる回復ぶりである場合には、会社は配慮を行う信義則上の義務があるものと解されます。
リハビリ勤務に関する参考裁判例
参考裁判例(北産機工事件/札幌地方裁判所平成11年9月21日判決)
直ちに100パーセントの稼働ができなくとも、職務に従事しながら、2、3ヵ月程度の期間を見ることによって完全に復職することが可能であったと推認することができるから(さらに、会社において、当該期間程度の猶予を認める余裕がなかった、あるいは、従業員に月に一、二回の通院を認めることによって業務遂行に支障が生じるとの事情は認められないから、信義則上、休職期間の満了後は一切の通院は認められない、とすることもできない)、休職期間の満了を理由に従業員を退職させる要件が具備していたと認めることはできず、会社が休職期間満了として退職とした取り扱いは無効であると解するべきである。
参考裁判例(全日本空輸(退職強要)事件/大阪地方裁判所平成11年10月18日判決)
直ちに従前業務に復帰ができない場合でも、比較的短期間で復帰することが可能である場合には、休業または休職に至る事情、会社の規模、業種、労働者の配置等の実情から見て、短期間の復帰準備時間を提供したり、教育的措置をとるなどが信義則上求められるというべきで、このような信義則上の手段をとらずに、解雇することはできないというべきである。
ただし、リハビリ勤務の期間について、あまりに長期間を要する場合には、そもそも、復職可能なほど回復していなかったともいえます。
裁判例では、主治医の見解によれば、復職する従業員が当初担当すべき業務量は、従前の半分程度であり、その期間として半年程度を要するされていたところ、「半年という期間は、いかにも長く、半分程度の業務量ということからすれば、従業員の休職が2年6ヵ月と長期間に及んでいることを考慮したとしても、実質は休職期間の延長というべき内容であって、しかも、半年後には十分に職務を行えるとの保障もなく、当初軽易な職務に就かせれば程なく従前の職務を通常に行うことができると予測できる場合とは解されない」として、復職を認めるべき状況にまで回復していたということはできないと判断しました(独立行政法人N事件/東京地方裁判所平成16年3月26日判決)。