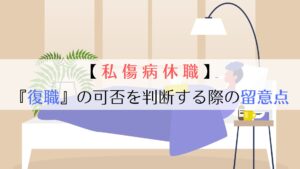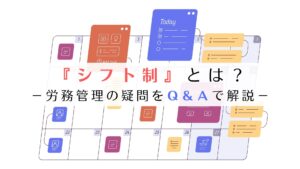【2025年6月改正】職場における熱中症対策の義務化を解説【労働安全衛生法(施行規則)】

はじめに
厚生労働省は、2025年4月15日に、事業主に対する熱中症対策の義務化を定めた、労働安全衛生法の省令(施行規則)の改正を公布しました。
法改正では、暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下(屋外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し、連絡できる体制を整備することを事業主に義務付けました。
また、重症化を防ぐために、応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成し、周知することも求められます。
法改正の施行日は、2025年6月1日です。
本稿では、職場における熱中症対策の義務化について、法改正を解説します。
熱中症とは
「熱中症」とは、高温多湿な環境下において、体内の水分および塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称をいいます。
症状としては、めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、意識障害、痙攣、手足の運動障害、高体温などが現われることがあります。
法改正の趣旨
職場における熱中症による死亡災害が、2年連続(令和4年度・令和5年度)で30人を超えており、そのほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因と解されています。
熱中症は、死亡災害に至る割合が他の災害の約5~6倍あり、さらに、死亡者の約7割は屋外作業であるため、今後の気候変動の影響により、さらに増加することが懸念されています。
法改正の趣旨は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じて、迅速かつ適切に対処することを可能とすることにあります。
法改正の内容
法改正の内容
法改正により、事業主に対し、労働者が「熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際」において、次の3つの取り組みを義務付けています。
職場における熱中症対策の義務化
- 【義務1】早期発見のための報告体制の整備
- 【義務2】重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
- 【義務3】(義務1と義務2について)関係作業者への周知
なお、事業主は、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記の取り組みを行う必要があるとされています。
熱中症を生ずるおそれのある作業
「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
熱中症を生ずるおそれのある作業
- WBGT値(暑さ指数)28度、または、気温31度以上の作業場において行われる作業
- 連続して1時間以上、または、1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業
「WBGT値(暑さ指数)」とは、熱中症を予防することを目的とした指標であり、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目し、人体の熱収支に与える影響の大きい①湿度、 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、③気温の3つを取り入れた指標です。
なお、単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。
WBGT値は、日本産業規格(JIS Z 8504)を参考に、実際の作業現場で測定するか、または、測定できない場合には、環境省の「熱中症予防情報サイト」などで把握することができます。
ただし、厚生労働省は、上記の作業に該当しない場合であっても、作業強度や着衣の状況などによっては、熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応を行うことを推奨しています。
【義務1】早期発見のための報告体制の整備
事業主は、前述の「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際に、熱中症の自覚症状がある作業者、および、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定めることが義務付けられました(労働安全衛生規則第612条の2第1項)。
さらに、厚生労働省は、報告を受ける体制に加えて、①職場巡視、②バディ制の採用、③ウェアラブルデバイス等の活用、④双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めることを推奨しています。
【義務2】重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
事業主は、前述の「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際に、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を、事業場ごとにあらかじめ定めることが義務付けられました(労働安全衛生規則第612条の2第2項)。
実施手順には、例えば、次の事項を盛り込む必要があります。
実施手順の内容(例)
- 作業からの離脱
- 身体の冷却
- 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の医療機関(※)の連絡先および所在地など
(※)医療機関への搬送に際しては、必要に応じて救急隊を要請することや、救急隊を要請すべきか判断に迷う場合は「#7119」を活用するなど、専門機関や医療機関に相談し、専門家の指示を仰ぐことなどを実施手順に定めておくことが考えられます。
【義務3】関係作業者への周知
事業主は、【義務1】と【義務2】に基づき定めた報告体制と実施手順について、関係作業者に対して周知を行う必要があります。
周知の方法については、法令では直接定められていませんが、厚生労働省のリーフレットでは、関係作業者への周知方法として、次の方法を例示しています。
関係作業者への周知(例)
- 朝礼、ミーティングでの周知
- 会議室、休憩所など、分かりやすい場所への掲示
- メール、社内イントラネットでの通知
熱中症の予防対策
法改正では直接義務付けられていませんが、熱中症の予防対策を行うことも重要です。
熱中症の予防対策については、厚生労働省の「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年7月26日基発0726第2号)が参考になります。
要綱では、主に次の4つの観点から熱中症の予防を行うことを定めています。
熱中症予防対策
- 作業環境管理(WBGT値の低減、休憩場所の整備など)
- 作業管理(暑熱順化、水分・塩分の摂取など)
- 健康管理(健康診断結果に基づく対応など)
- 労働衛生教育(緊急時の救急処置など)
厚生労働省の「第175回安全衛生分科会資料」では、異常が認められる者が発生した場合の対応に関する教育が非常に重要であることを指摘しています。
行政通達では、労働者に対する労働衛生教育が確実に実施されるよう、高温多湿作業場所 における作業を管理する者(熱中症予防管理者)に対しては、労働衛生教育を行う(事業者が自ら当該教育を行うことが困難な場合には、関係団体が行う教育を活用する)こととされています(平成28年2月29日基安発0229第1号)。
そして、作業者に対する教育は、熱中症予防管理者など、熱中症予防対策に詳しい管理者を各現場において選任し、その者が中心となって実施することが望ましいとしています。
罰則
事業主が、職場における熱中症対策を怠ったことにより、法令に違反した場合には、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(労働安全衛生法第119条)。
参考法令
労働安全衛生規則第612条の2
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。