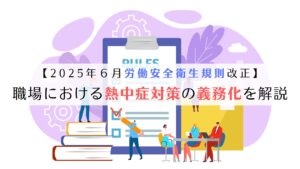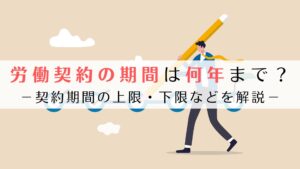「シフト制」とは?シフトを「一方的に決める」「変更する」「減らす」ことはできるかなど、労務管理の疑問をQ&A形式で解説
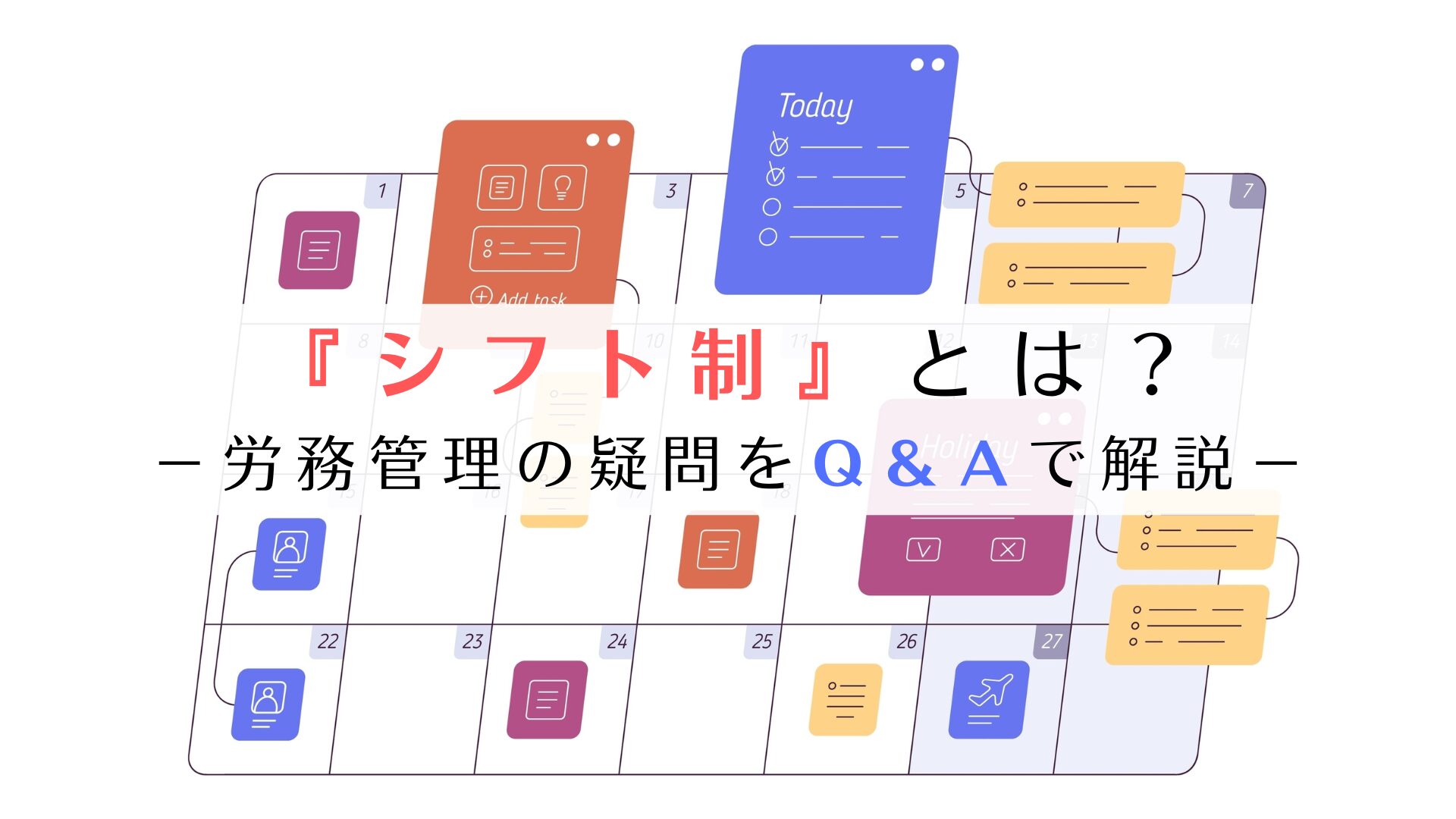
「シフト制」とは?
【質問1】
「シフト制」とは、一般に、どのような制度なのでしょうか。
【回答1】
労務管理において、「シフト制」とは、一般に、労働契約の締結時点では、具体的な労働日、労働時間、労働時間帯などが確定的には決まっておらず、会社が業務の都合に応じて、従業員の労働日と労働時間を割り当てることによって(シフトを組むことによって)、はじめて具体的な労働日と労働時間が確定する勤務形態をいいます。
労働基準法などの労働関連法令には、「シフト制」に関する規制は特にありません。
したがって、いつ、どのようにシフトを組むのかなど、「シフト制」をどのように運用するかは、会社と従業員との間の個別の労働契約によって決まります。
「シフト制」では、法律による規制がないために、会社の都合により、決められた労働日や労働時間がほとんど設けられていなかったり、従業員の意向に反してシフトが多く(または少なく)組まれたりするなどのトラブルが生じることがあります。
「シフト制」と労働基準法の適用
【質問2】
「シフト制」であれば、会社が自由に労働日や労働時間などを決めることができるのでしょうか。
【回答2】
労働基準法では、「シフト制」に関する規制は特にありませんが、当然ながら、「シフト制」において、労働日、労働時間、休日などを決定する際には、労働基準法が定める法定労働時間、法定休日などの規制が適用されます。
労働基準法では、労働時間について、原則として、1日8時間および1週40時間の法定労働時間を定めています(労働基準法第32条)。
また、原則として、毎週少なくとも1日の休日を与えなければならないとする法定休日を定めています(労働基準法第35条第1項)。
したがって、会社は、原則として、法定労働時間や法定休日にかかる規制の範囲内で、各日・各週のシフトを組む必要があります。
「シフト制」と1ヵ月単位の変形労働時間制
【質問3】
「シフト制」と、「1ヵ月単位の変形労働時間制」とは、どのような違いがあるのでしょうか。
【回答3】
【回答2】のとおり、「シフト制」においてシフトを組む際には、原則として、法定労働時間の制約を受けます。
ただし、労働基準法では、法定労働時間制の例外として、1ヵ月単位の変形労働時間制を設けています。
「1ヵ月単位の変形労働時間制」とは、制度について就業規則に定めるなど所定の手続を行うことにより、特定された日または週においては、法定労働時間を超えて所定労働時間を定めることができる制度です。
例えば、変形労働時間制を導入することにより、1日10時間とするシフトを組むことができ、このとき、10時間を超えるまでは割増賃金を支払う必要がないというメリットがあります。
ただし、1ヵ月単位の変形労働時間制に基づき、月ごとにシフトを組む場合には、すべての始業・終業時刻のパターンや組み合わせ、シフト表を作成する際の手続きなどを事前に定めておく必要があるなど、厳格な運用が求められます(昭和63年3月14日基発150号)。
会社が業務の都合によって、随時シフトを変更するような場合は、変形労働時間制として認められません(平成11年3月31日基発168号)。
1ヵ月単位の変形労働時間制の詳細については、次の記事をご覧ください。
「1ヵ月単位の変形労働時間制」とは?制度の内容・手続などを詳しく解説
会社がシフトを「一方的に決定・変更する」ことは認められるか?
【質問4】
パート・アルバイトなどについて、例えば、「具体的な出勤日、出勤時間などは、シフト表によって1ヵ月ごとに定める」など、抽象的に取り決めをしている場合において、会社がシフトを一方的に決定し、または変更することは認められるのでしょうか。
【回答4】
例えば、労働契約において、「出勤日は月・水・金の3日間とし、各日の労働時間は9時から15時までの6時間とする」など、シフトを限定する合意がある場合には、それが労働契約の内容となりますので、基本的に、会社の裁量によってこれを変更することはできません(変更について、別に取り決めがある場合を除きます)。
一方、出勤日・労働時間などについて限定されておらず(抽象的に定められており)、シフトに委ねられている場合には、「会社の人事権がどこまで及ぶか」の範囲の問題となります。
一般に、降格・配置転換などを含む人事権の行使は、基本的に会社の経営上の裁量判断に属しており、社会通念上著しく妥当性を欠き、権利の濫用と認められない限り、違法とはいえないと解されています(医療法人財団東京厚生会事件/東京地方裁判所平成9年11月18日判決)。
そして、裁量判断を逸脱しているか否かを判断するにあたっては、会社における業務上の必要性の有無、従業員の受ける不利益の性質およびその程度などが総合考慮されると解されます。
そして、シフトの決定・変更についても、基本的に、上記の考え方に基づき、人事権を行使することとなります。
シフトの決定・変更にかかる人事権の範囲について、明確に示した裁判例は特にありませんが、配転命令にかかる人事権の範囲について争われた判例法理が当てはまると解されます。
裁判例では、配転命令について、就業規則に、会社が業務上の都合により配転を命ずることができる旨の規定があり、実際にもそれらの規定に従い配転が頻繁に行われ、採用時に勤務場所・職種等を限定する合意がなされていなかった場合には、会社は従業員の個別的同意なしに配転を命ずることができるとしています(東亜ペイント事件/最高裁判所昭和61年7月14日判決)。
上記の裁判例を、「シフト制」におけるシフトの決定・変更に当てはめると、①就業規則または雇用契約書などに、「会社が業務上の都合によりシフトの変更を命じることができる」旨の規定があり、②実際にも、その規定に従い変更が行われ、③採用時にシフト等を限定する合意がなされていなかった場合には、会社は従業員の個別の同意を得ることなく、その裁量によってシフトを決定・変更することができると解されます。
会社がシフトを「一方的に減らす」ことは認められるか?
【質問5】
例えば、勤務態度が悪く、何度注意や指導をしても改善しない従業員について、会社がシフトを大幅に減らすことはできるのでしょうか。
【回答5】
まず、労働契約によって、「週に4日以上勤務」など、一定の労働日数が保障されている場合には、会社が一方的に大幅にシフトを減らすことは、労働契約に違反する可能性が高いといえます。
そして、労働契約において、週の最低労働日数や労働時間が保障されていない場合には、シフトを大幅に削減することについて合理的な理由があれば、可能であると解されます。
シフトの削減を有効と判断した裁判例としては、品位を欠く勤務態度等の従業員のシフトを削減した事案で、複数回にわたり始末書の提出を求めて反省を促し、勤務場所を変えるなどして雇用維持の努力をしたものの、勤務態度が改善しなかったとして勤務日数を減らしたことには合理的な理由があると判断されました(東京シーエスピー事件/東京地方裁判所平成22年2月2日判決)。
一方、シフトの削減を違法と判断した裁判例としては、それまで月間15日程度であったシフトを、月に1日、翌月は0日に減らした事案において、裁判所は、シフト制で勤務する従業員にとって、シフトの大幅な削減は収入に直結するものであり、従業員の不利益が著しいことから、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用に当たり違法になることを示した上で、本事案では合理的な理由が認められなかったことから、シフトの削減を違法と判断しました(シルバーハート事件/東京地方裁判所令和2年11月25日判決)。
「シフト制」の運用で留意すべき事項
【質問6】
「シフト制」の運用にあたり、労務管理で留意しておくことはありますか。
【回答6】
厚生労働省は、『いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和4年1月7日)』(以下、「留意事項」といいます)を公表しています。
本留意事項は、法的な拘束力はないものの、実務上参考になります。
本留意事項では、特に「シフト制」の労働契約では、トラブルを防止するために、以下の点に留意すべきとしています。
| 項目 | 留意事項 |
| 始業・終業時刻 | 労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、労働条件通知書などに単に「シフトによる」と記載するだけでは不足であり、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて従業員に交付する必要がある |
| 休日 | 具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記する必要がある |
| 作成 | シフト作成時のルールとして、以下の内容についてあらかじめ合意することが考えられる ・シフトの作成時に、事前に従業員の意見を聞くこと ・シフトの通知期限(「毎月〇日までに通知する」など) ・シフトの通知方法(「電子メールで通知する」など) |
| 変更 | シフト変更時のルールとして、以下の内容についてあらかじめ合意することが考えられる ・一旦確定したシフトの労働日、労働時間をシフト期間開始前に変更する場合に、会社や従業員が申出を行う場合の期限や手続 ・シフト期間開始後、確定していた労働日、労働時間をキャンセル、変更する場合の期限や手続 なお、一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、会社と従業員双方の合意が必要である点に留意する |
| 設定 | シフト作成・変更のルールに加えて、従業員の希望に応じて、以下の内容についてあらかじめ合意することが考えられる ・一定の期間中に労働日が設定される最大の日数、時間数、時間帯 (「毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する」など) ・一定の期間中の目安となる労働日数、労働時間数(「1ヵ月〇日程度勤務」、「1週間あたり平均〇時間勤務」など) ・一定の期間において最低限労働する日数、時間数など(「1ヵ月〇日以上勤務」、「少なくとも毎週月曜日はシフトに入る」など) |