労働基準法が定める「罰則(拘禁刑または罰金)」全種類をまとめて解説
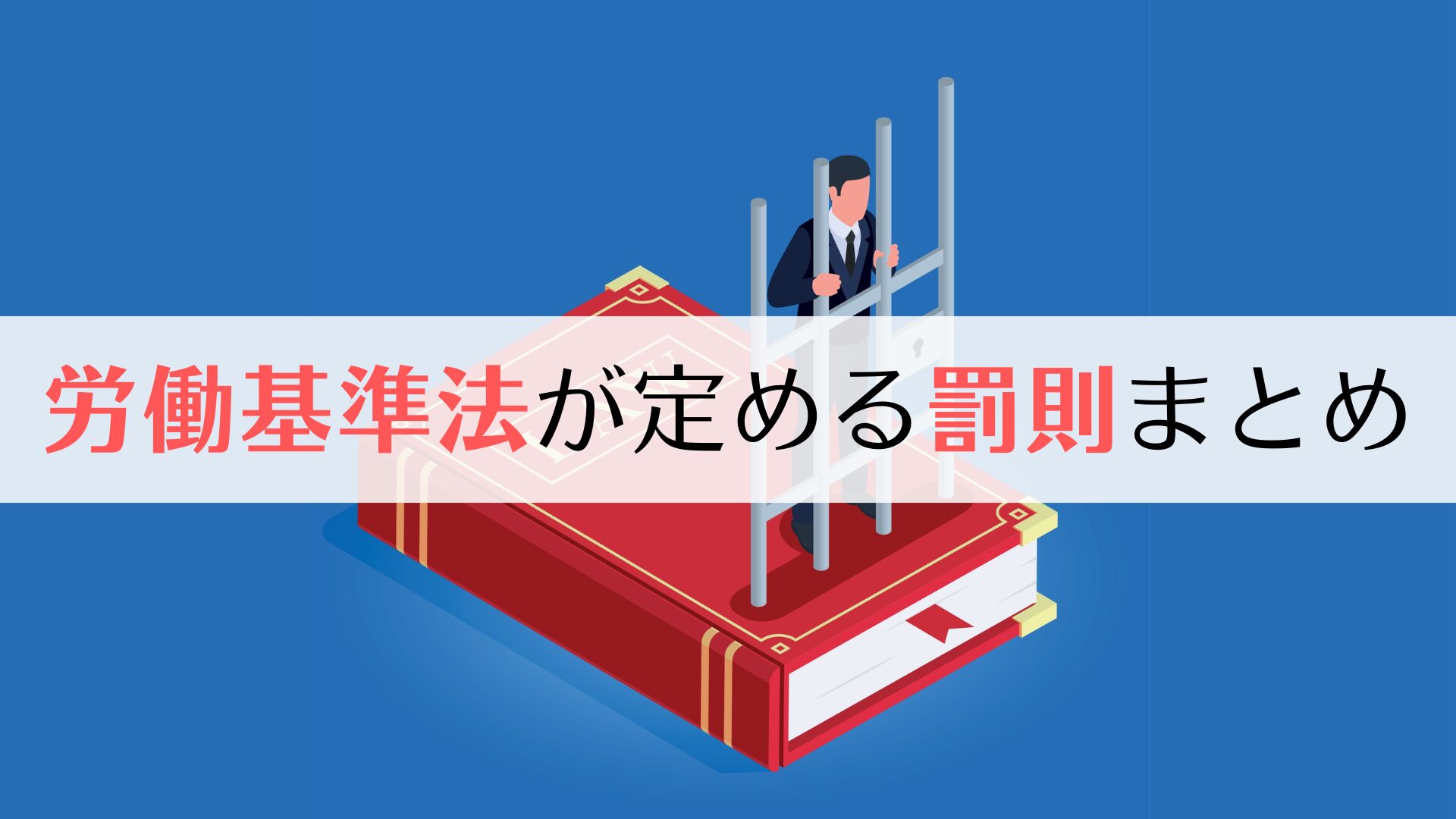
- 1. はじめに
- 2. 1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金
- 2.1.1. 強制労働の禁止
- 3. 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 3.1.1. 中間搾取の排除
- 3.1.2. 最低年齢
- 3.1.3. 年少者の坑内労働の禁止
- 3.1.4. 妊産婦等の坑内業務の就業制限
- 3.1.5. 職業訓練に関する特例
- 4. 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
- 4.1.1. 均等待遇
- 4.1.2. 男女同一賃金の原則
- 4.1.3. 公民権行使の保障
- 4.1.4. 賠償予定の禁止
- 4.1.5. 前借金相殺の禁止
- 4.1.6. 強制貯金
- 4.1.7. 解雇制限
- 4.1.8. 解雇の予告
- 4.1.9. 通信等の禁止
- 4.1.10. 法定労働時間
- 4.1.11. 休憩時間
- 4.1.12. 法定休日
- 4.1.13. 時間外労働の上限規制
- 4.1.14. 時間外・休日・深夜労働の割増賃金
- 4.1.15. 年次有給休暇
- 4.1.16. 年少者の深夜労働
- 4.1.17. 年少者の危険有害業務の就業制限
- 4.1.18. 妊産婦の危険有害業務の就業制限
- 4.1.19. 産前産後休業
- 4.1.20. 妊産婦の時間外労働などの制限
- 4.1.21. 育児時間
- 4.1.22. 災害補償
- 4.1.23. 寄宿舎
- 4.1.24. 監督機関に対する申告
- 4.1.25. 行政官庁による命令違反
- 5. 30万円以下の罰金
- 5.1.1. 契約期間等
- 5.1.2. 労働条件の明示
- 5.1.3. 強制貯金
- 5.1.4. 退職時等の証明書
- 5.1.5. 金品の返還
- 5.1.6. 賃金の支払い
- 5.1.7. 非常時払
- 5.1.8. 休業手当
- 5.1.9. 出来高払制の保障給
- 5.1.10. 変形労働時間制にかかる労使協定の届出
- 5.1.11. 1週間単位変形における各日の労働時間通知
- 5.1.12. 臨時の必要がある場合の時間外労働等の届出
- 5.1.13. 事業場外労働・専門業務型裁量労働にかかる労使協定の届出
- 5.1.14. 年次有給休暇の取得義務
- 5.1.15. 年少者の証明書
- 5.1.16. 未成年者の労働契約
- 5.1.17. 帰郷旅費
- 5.1.18. 生理休暇
- 5.1.19. 就業規則の作成・届出義務
- 5.1.20. 就業規則にかかる意見聴取
- 5.1.21. 制裁規定の制限
- 5.1.22. 寄宿舎規則の作成・届出義務
- 5.1.23. 寄宿舎にかかる届出
- 5.1.24. 労働基準監督官の義務
- 5.1.25. 法令等の周知義務
- 5.1.26. 労働者名簿
- 5.1.27. 賃金台帳
- 5.1.28. 記録の保存
- 5.1.29. 行政官庁による命令違反
- 5.1.30. 臨検の拒否
- 5.1.31. 報告違反
- 6. 両罰規定
はじめに
労働基準法第13章では、労働基準法に違反した場合の罰則を定めています。
本稿では、罰則が定められている労働基準法の規定を、罰則ごとに整理して解説します。
1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金
次の規定に違反した者は、1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金が定められています(第117条)。
本罰則は、労働基準法上、最も重い罰則とされています。
強制労働の禁止
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならないとされています(第5条)。
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
次の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(第118条)。
中間搾取の排除
何人も、法律に基いて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとされています(第6条)。
最低年齢
使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者(児童)を、使用してはならないとされています(第56条)。
年少者の坑内労働の禁止
使用者は、満18歳に満たない者(年少者)を坑内で労働させてはならないとされています(第63条)。
妊産婦等の坑内業務の就業制限
使用者は、妊娠中の女性および使用者に申し出た産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならないとされています(第64条の2第一号)。
また、上記以外の満18歳以上の女性についても、坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務などに就かせてはならないとされています(第64条の2第二号)。
職業訓練に関する特例
年少者(第63条)または妊産婦(第64条の2)の規定については、職業訓練を受ける労働者にかかる厚生労働省令に違反した場合にも、各条違反と同じ罰則が適用されます(第118条第2項)。
6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
次の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(第119条)。
均等待遇
使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的な取り扱いをしてはならないとされています(第3条)。
男女同一賃金の原則
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取り扱いをしてはならないとされています(第4条)。
公民権行使の保障
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合は、拒んではならないとされています(第7条)。
賠償予定の禁止
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされています(第16条)。
前借金相殺の禁止
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないとされています(第17条)。
強制貯金
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならないとされています(第18条第1項)。
解雇制限
使用者は、原則として、業務上の負傷・疾病による療養休業期間およびその後30日間、産前産後休業期間およびその後30日間は、労働者を解雇してはならないとされています(第19条)。
解雇の予告
使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしないときは、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています(第20条)。
通信等の禁止
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分などに関する通信をし、または退職時の証明書(第22条第1項)・解雇理由の証明書(第22条第2項)に秘密の記号を記入してはならないとされています(第22条第4項)。
法定労働時間
使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間につき40時間を超え、1日につき8時間を超えて労働させてはならないとされています(第32条)。
休憩時間
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないとされています(第34条)。
なお、労働時間および休憩の特例にかかる厚生労働省令に違反した者についても、各条違反と同じ罰則が適用されます(第40条、第119条第三号)。
法定休日
使用者は、労働者に対し、原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされています(第35条)。
時間外労働の上限規制
使用者は、労使協定に基づき、労働時間を延長して労働させ、または休日労働をさせる場合であっても、延長時間について1ヵ月100時間未満であること、1ヵ月当たりの平均時間が80時間を超えないことなどの要件を満たさなければならないとされています(第36条第6項)。
時間外・休日・深夜労働の割増賃金
使用者は、時間外労働、休日労働、または深夜労働させた場合には、その時間またはその日の労働については、政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています(第37条)。
年次有給休暇
使用者は、雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないとされています(第39条(第7項を除く))。
なお、職業訓練を受ける未成年者の年次有給休暇にかかる特例に違反した者についても、同条違反と同じ罰則が適用されます(第72条)。
年少者の深夜労働
使用者は、原則として、満18歳に満たない者(年少者)を、深夜(午後10時から午前5時まで)の時間帯に使用してはならないとされています(第61条)。
年少者の危険有害業務の就業制限
使用者は、満18歳に満たない者(年少者)を、動力によるクレーンの運転など危険な業務に就かせ、または重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとされています(第62条)。
妊産婦の危険有害業務の就業制限
使用者は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、重量物を取り扱う業務など、妊産婦の妊娠、出産、哺(ほ)育等に有害な業務に就かせてはならないとされています(第64条の3)。
なお、年少者(第62条)または妊産婦(第64条の3)の規定については、職業訓練を受ける労働者にかかる厚生労働省令に違反した場合にも、各条違反と同じ罰則が適用されます(第70条、第119条第四号)。
産前産後休業
使用者は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはならず、かつ、産後8週間を経過しない女性を原則として就業させてはならないとされています(第65条)。
妊産婦の時間外労働などの制限
使用者は、妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制にかかる規定にかかわらず、法定労働時間を超えて労働させてはならないとされています(第66条)。
育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができるとされています(第67条)。
災害補償
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合には、使用者は、必要に応じて、療養補償(第75条)、休業補償(第76条)、障害補償(第77条)、遺族補償(第79条)、葬祭料(第80条)を支払わなければならないとされています。
寄宿舎
使用者は、寄宿舎生活の自治に必要な役員(寮長、室長など)の選任に干渉してはならないとされています(第94条第2項)。
また、使用者は、事業の附属寄宿舎について、労働者の健康、風紀および生命の保持に必要な措置を講じなければならないとされています(第96条)。
監督機関に対する申告
使用者は、労働者が監督機関に申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとされています(第104条第2項)。
行政官庁による命令違反
災害等による臨時の必要に基づく時間外労働等の届出があった場合における休憩・休日の取得命令(第33条第2項)、寄宿舎にかかる工事の着手の差し止め・計画の変更命令(第96条の2第2項)、寄宿舎にかかる使用停止・変更命令に違反した使用者に対する罰則が定められています(第96条の3第1項)(第119条第二号)。
30万円以下の罰金
次の規定に違反した者は、30万円以下の罰金が定められています(第120条)。
契約期間等
労働契約の期間を定める場合は、原則として、3年(高度の専門的知識等を有する者との労働契約などは5年)を超える期間について締結してはならないとされています(第14条)。
職業訓練にかかる厚生労働省令に違反した者についても、同条違反と同じ罰則が適用されます(第70条、第120条第二号)。
労働条件の明示
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(第15条第1項)。
また、明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができ、この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は、必要な旅費を負担しなければならないとされています(第15条第3項)。
強制貯金
行政官庁は、貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができ、この場合、使用者は、遅滞なくその管理にかかる貯蓄金を労働者に返還しなければならないとされています(第18条第7項)。
退職時等の証明書
労働者が退職する場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないとされています(第22条第1項から第3項まで)。
金品の返還
使用者は、労働者が死亡または退職した際に、権利者の請求があった場合は、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないとされています(第23条)。
賃金の支払い
賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされています(第24条)。
非常時払
使用者は、労働者が出産、疾病、災害など非常の場合の費用に充てるために請求した場合は、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないとされています(第25条)。
休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、使用者は、休業期間中、労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないとされています(第26条)。
出来高払制の保障給
使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ、一定額の賃金の保障をしなければならないとされています(第27条)。
変形労働時間制にかかる労使協定の届出
使用者は、1ヵ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制にかかる労使協定を締結した場合には、当該協定を行政官庁に届け出なければならないとされています(第32条の2第2項、第32条の3第4項、第32条の4第4項、第32条の5第3項)。
1週間単位変形における各日の労働時間通知
使用者は、労働者を1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、1週間の各日の労働時間を、あらかじめ労働者に通知しなければならないとされています(第32条の5第2項)。
臨時の必要がある場合の時間外労働等の届出
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、使用者は、行政官庁の許可を受けて、時間外労働・休日労働をさせることができます。
このとき、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされています(第33条第1項ただし書)。
事業場外労働・専門業務型裁量労働にかかる労使協定の届出
使用者は、事業場外労働、専門業務型裁量労働にかかる労使協定を締結した場合には、当該協定を行政官庁に届け出なければならないとされています(第38条の2第3項、第38条の3第2項)。
年次有給休暇の取得義務
使用者は、付与される年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者については、そのうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより年次有給休暇を与えなければならないとされています(第39条第7項)。
年少者の証明書
使用者は、18歳未満の者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないとされています(第57条)。
未成年者の労働契約
親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならないとされています(第58条)。
また、未成年者は、独立して賃金を請求することができ、親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないとされています(第59条)。
帰郷旅費
使用者は、18歳未満の者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、必要な旅費を負担しなければならないとされています(第64条)。
生理休暇
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないとされています(第68条)。
就業規則の作成・届出義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとされています(第89条)。
就業規則にかかる意見聴取
使用者は、就業規則の作成または変更については、当該事業場の過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとされています(第90条第1項)。
制裁規定の制限
労働者に対する減給の制裁は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされています(第91条)。
寄宿舎規則の作成・届出義務
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとされています(95条第1項、第2項)。
寄宿舎にかかる届出
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置・移転・変更しようとする場合は、その計画を、工事着手の14日前までに、行政官庁に届け出なければならないとされています(第96条の2第1項)。
労働基準監督官の義務
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならないとされており、労働基準監督官を退官した後においても同様とされています(第100条第3項、第105条)。
法令等の周知義務
使用者は、労働基準法およびこれに基づく命令の要旨、就業規則、その他法律で定める事項を、常時各作業場の見やすい場所への掲示・備え付け・書面交付などの方法によって、労働者に周知しなければならないとされています(第106条)。
労働者名簿
使用者は、事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調製し、厚生労働省令で定める事項を記入しなければならないとされています(第107条)。
賃金台帳
使用者は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならないとされています(第108条)。
記録の保存
使用者は、労働者名簿、賃金台帳および雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならないとされています(第109条)。
行政官庁による命令違反
行政官庁による、法令または労働協約に牴触する就業規則の変更命令(第92条第2項)、寄宿舎にかかる安全および衛生に関する命令(第96条の3第2項)に違反した場合の罰則が定められています(第120条第三号)。
臨検の拒否
第101条(第100条第3項において準用する場合を含む)の規定による労働基準監督官等の臨検の拒否、帳簿書類の不提出または虚偽記載などをした者に対する罰則が定められています(第101条、第120条第四号)。
報告違反
行政官庁による第104条の2の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または出頭しなかった者に対する罰則が定められています(第104条の2、第120条第五号)。
両罰規定
労働基準法違反の行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合には、事業主に対しても罰金刑を科するとされています(第121条第1項)。
ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りではありません。
また、事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合、または違反を教唆した場合には、事業主も行為者として罰するとされています(第121条第2項)。


