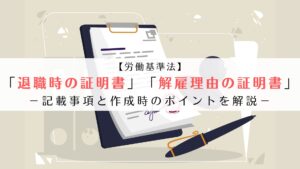法律上の設置義務がある「相談窓口」を7つ解説(ハラスメント・育児・介護など)
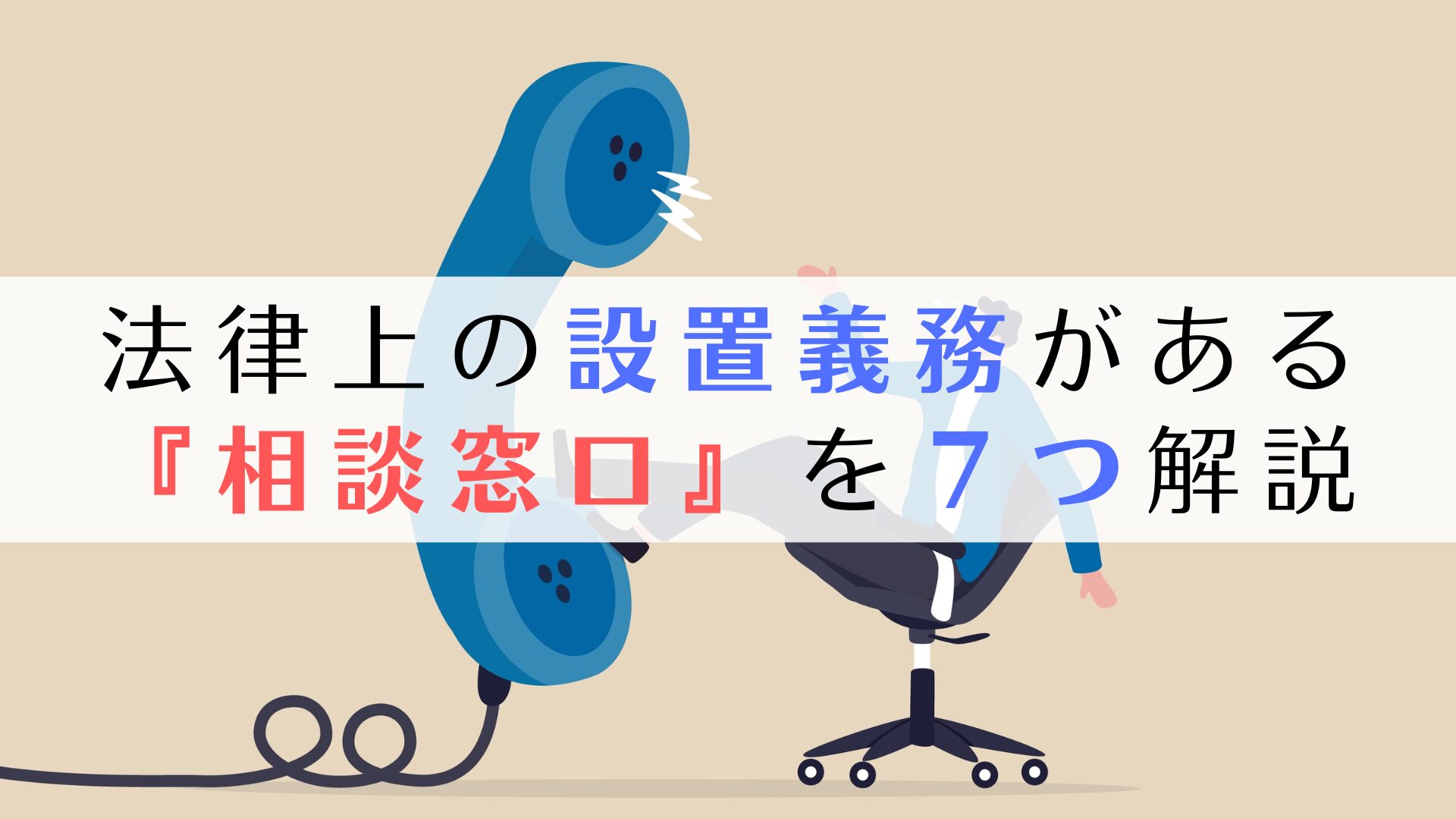
- 1. はじめに
- 2. まとめ
- 3. 1.パワーハラスメントに関する相談窓口【労働施策総合推進法】
- 3.1. 相談窓口の設置義務
- 3.2. セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントにかかる相談窓口
- 4. 2.ハラスメントに関する相談窓口(フリーランス)【フリーランス・事業者間取引適正化等法】
- 5. 3.健康・メンタルヘルスに関する相談窓口【労働安全衛生法】
- 5.1. 健康保持増進指針
- 5.2. メンタルヘルス指針
- 6. 4.育児・介護休業等に関する相談窓口【育児・介護休業法】
- 6.1. 育児休業等に関する相談窓口
- 6.2. 介護休業等に関する相談窓口
- 7. 5.雇用管理の改善に関する相談窓口【パートタイム・有期雇用労働法】
- 8. 6.合理的配慮等に関する相談窓口【障害者雇用促進法】
- 9. 7.内部公益通報の受付窓口【公益通報者保護法】
はじめに
労務管理においては、法律により、事業主に対し、労働者からの相談を受け付けるための「相談窓口」を設置することが義務付けられていることがあります。
本稿では、労務管理において、法律によって相談窓口の設置が義務付けられているものを7つ(努力義務を含みます)、まとめて解説します。
まとめ
| 相談窓口の内容 | 法律 | |
| 1 | パワーハラスメントに関する相談窓口 | 労働施策総合推進法 |
| 2 | ハラスメントに関する相談窓口(フリーランス) | フリーランス・事業者間取引適正化等法 |
| 3 | 健康・メンタルヘルスに関する相談窓口 | 労働安全衛生法 |
| 4 | 育児・介護休業等に関する相談窓口 | 育児・介護休業法 |
| 5 | 雇用管理の改善に関する相談窓口 | パートタイム・有期雇用労働法 |
| 6 | 合理的配慮等に関する相談窓口 | 障害者雇用促進法 |
| 7 | 内部公益通報の受付窓口 | 公益通報者保護法 |
1.パワーハラスメントに関する相談窓口【労働施策総合推進法】
相談窓口の設置義務
労働施策総合推進法では、事業主は、職場におけるパワーハラスメントのないように、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないとされています(労働施策総合推進法第30条の2第1項)。
「職場におけるパワーハラスメント」とは、職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものをいいます(令和2年厚生労働省告示第5号)。
事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じて、適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、次の措置を講じなければならないとされています。
相談窓口の設置
- 相談への対応のための窓口(相談窓口)をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 1.の相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
1.について、相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例としては、①相談に対応する担当者をあらかじめ定めること、②相談に対応するための制度を設けること、③外部の機関(弁護士など)に相談への対応を委託することなどが挙げられます。
2.について、相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例としては、①相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること、②相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること、③相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うことなどが挙げられます。
セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントにかかる相談窓口
職場におけるパワーハラスメントは、セクシュアルハラスメント(平成18年厚生労働省告示第615号)、妊娠、出産等に関するハラスメント(平成28年厚生労働省告示第312号)、育児休業等に関するハラスメント(平成21年厚生労働省告示第509号)、その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、事業主は、例えば、セクシュアルハラスメントなどの相談窓口と一体的に(相談窓口を兼ねて)、職場におけるパワーハラスメントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいとされています。
2.ハラスメントに関する相談窓口(フリーランス)【フリーランス・事業者間取引適正化等法】
発注事業者(特定業務委託事業者)は、業務委託を行うフリーランス(特定受託事業者)に対し、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどにより就業環境を害することのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないとされています(フリーランス・事業者間取引適正化等法第14条第1項)。
発注事業者は、フリーランスからの相談に対し、その内容や状況に応じて適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、①相談への対応のための窓口をあらかじめ定め(相談に対応する担当者をあらかじめ定める、外部機関に相談への対応を委託するなど)、かつ、②フリーランスに対して周知することが必要です。
周知の方法としては、業務委託契約にかかる書面やメールなどに、ハラスメントの相談窓口の連絡先を記載すること、フリーランスが定期的に閲覧するイントラネットなどにおいて、ハラスメントの相談窓口について掲載することなどが挙げられます。
また、相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じて適切に対応できるようにすることも必要であり、例えば、①相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門や契約担当部門とが連携を図ることができる仕組みとすること、②相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること、③相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うことなどが挙げられます(令和6年5月31日厚生労働省告示第212号)。
3.健康・メンタルヘルスに関する相談窓口【労働安全衛生法】
事業者は、労働者に対する健康教育、健康相談、その他労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置を、継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない(努力義務)とされています(労働安全衛生法第69条第1項)。
これを受けて、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(健康保持増進指針)」および「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」が定められています(労働安全衛生法第70条の2第1項)。
健康保持増進指針
事業者は、健康診断などにより労働者の健康状態を把握し、その結果に基づき、ストレスに対する気付きへの援助、メンタルヘルスケアなどの健康指導を実施する必要があるとされています。
また、事業者は、希望する労働者に対しては、個別に健康相談などを行うように努めることとされています。
メンタルヘルス指針
事業者は、各事業場の実態に即した形で、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましいとされています。
メンタルヘルスケアにおいて、メンタルヘルス不調に陥る労働者が発生した場合は、その早期発見と適切な対応を図る必要があるため、事業者は、個人情報の保護に十分留意しつつ、労働者、管理監督者、家族などからの相談に対して、適切に対応できる体制を整備することとされています。
さらに、相談により把握した情報をもとに、労働者に対して必要な配慮を行うこと、および必要に応じて産業医や医療機関に繋いでいくネットワークを整備するように努めることとされています。
4.育児・介護休業等に関する相談窓口【育児・介護休業法】
育児休業等に関する相談窓口
育児休業の申出などが円滑に行われるようにするために、事業主に対し、次の措置のうち、いずれか1つ以上の措置を選択して講じることが義務付けられています(育児・介護休業法第22条第1項、同法施行規則第71条の2)。
育児にかかる雇用環境整備
- 育児休業に関する研修の実施
- 育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
- 育児休業の取得に関する事例の収集および当該事例の提供
- 育児休業制度と、育児休業の取得の促進に関する方針の周知
介護休業等に関する相談窓口
介護に関する制度を利用しやすい職場環境を整備し、制度利用の申出が円滑に行われるようにするために、事業主に対し、次の措置のうち、いずれか1つ以上の措置を選択して講じることが義務付けられています(育児・介護休業法第22条第2項、同条第4項、同法施行規則第71条の2、第71条の4)。
介護にかかる雇用環境整備
- 介護休業および介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業および介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
- 介護休業および介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集および当該事例の提供
- 介護休業に関する制度・介護両立支援制度等、および、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の促進に関する方針の周知
なお、育児休業について、同様の内容で雇用環境の整備が義務付けられていることから、例えば、事業主が育児休業に関する相談窓口を設置している場合には、同じ窓口において、介護休業および介護両立支援制度等に関する相談を受け付けるように体制を整えることなどが考えられます。
5.雇用管理の改善に関する相談窓口【パートタイム・有期雇用労働法】
事業主は、短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善などに関する事項に関して、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないとされています(パートタイム・有期雇用労働法第16条)。
また、事業主は、短時間労働者または有期雇用労働者を雇い入れる場合(契約の更新時を含む)には、「短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善などに関する事項にかかる相談窓口」について、労働条件通知書などによって明示することが義務付けられています(パートタイム・有期雇用労働法第6条第1項、同法施行規則第2条第1項第四号)。
なお、事業主は、常時10人以上の短時間労働者および有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、その雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努める必要があることから、当該管理者を選任している場合には、その者が相談窓口の担当者となることが考えられます(パートタイム・有期雇用労働法第17条、同法施行規則第6条)。
6.合理的配慮等に関する相談窓口【障害者雇用促進法】
事業主は、その雇用する障害者である労働者について、障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならないとされており、そのために、事業主は、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないとされています(障害者雇用促進法第36条の3、第36条の4第2項)。
具体的には、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備として、①相談への対応のための窓口(相談窓口)をあらかじめ定め、②労働者に対して周知することが必要であり、①としては、例えば、相談に対応する担当者・部署をあらかじめ定めること、外部の機関に相談への対応を委託することなどが挙げられます(平成27年厚生労働省告示第117号)。
また、相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や相談者の状況に応じて、適切に対応できるよう必要な措置を講ずることも必要とされています。
7.内部公益通報の受付窓口【公益通報者保護法】
事業主は、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならないとされています(公益通報者保護法第11条第2項)。
なお、常時使用する労働者の数が300人以下の事業主については、上記の措置は努力義務とされています(公益通報者保護法第11条第3項)。