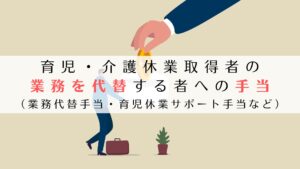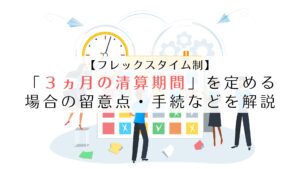【フレックスタイム制】「完全週休2日制の特例」を解説(特例の内容、手続など)

はじめに
完全週休2日制の下で、フレックスタイム制を導入する場合には、特例を適用することにより、法定労働時間の総枠を延長することが認められています。
本稿では、フレックスタイム制における「完全週休2日制の特例」について、特例の内容、特例を適用する際の手続(労使協定)などを解説します。
なお、フレックスタイム制の基本的な制度内容については、次の記事をご覧ください。
「フレックスタイム制」とは?制度の内容・導入手続(就業規則・労使協定)をわかりやすく解説
【原則】フレックスタイム制における「法定労働時間の総枠」
法定労働時間の総枠
「フレックスタイム制」とは、一定の期間(最大3ヵ月とし、これを「清算期間」といいます)の総労働時間をあらかじめ定めておき、従業員がその範囲内で、日々の始業・終業時刻を自ら決定して働くことができる制度をいいます(労働基準法第32条の3)。
清算期間における総労働時間(後述)は、法定労働時間に基づいて算出された労働時間の限度(以下、「法定労働時間の総枠」といいます)に収める必要があります。
清算期間における法定労働時間の総枠は、次の計算によって算出します。
清算期間における法定労働時間の総枠
1週間の法定労働時間×清算期間の暦日数÷7日
「1週間の法定労働時間」は、原則として、40時間となります(労働基準法第32条第1項)。
「清算期間の暦日数」は、暦月1ヵ月を清算期間とする場合には、28日から31日までの日数となります。
例えば、4月(暦日30日)を清算期間とする場合には、法定労働時間の総枠は、171.4時間(40時間×30日÷7日)となります。
【図】法定労働時間の総枠
| 清算期間(1ヵ月)の暦日数 | 法定労働時間の総枠 |
| 31日 | 177.1時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 28日 | 160.0時間 |
清算期間における総労働時間(所定労働時間)
フレックスタイム制を運用する場合には、清算期間ごとに「総労働時間」を定める必要があります。
清算期間における「総労働時間」とは、労働契約に基づき、清算期間において労働すべき時間として定められた、所定労働時間をいいます。
そして、所定労働時間は、法定労働時間を超えて定めることはできないことから、総労働時間(所定労働時間)は、法定労働時間の総枠を超えて定めることはできません。
例えば、4月(暦日30日)を清算期間とする場合、前述のとおり、法定労働時間の総枠は177.1時間ですが、当該清算期間における総労働時間(所定労働時間)は、177.1時間以内に収める必要があるということです。
法定労働時間の総枠と、総労働時間(所定労働時間)の関係
法定労働時間の総枠≧総労働時間(所定労働時間)
なお、清算期間における総労働時間(所定労働時間)の定め方としては、例えば、「1ヵ月160時間」などと各清算期間を通じて一律の総労働時間を定める場合のほか、各清算期間における所定労働日に、標準となる1日の労働時間(1日あたり8時間など)を乗じて総労働時間を定める場合などがあります。
【特例】「完全週休2日制の特例」とは
「完全週休2日制」とは、一般に、毎週必ず2日の所定休日が定められていること(週の所定労働日数が5日以下であること)をいいます。
完全週休2日制の下でフレックスタイム制を導入した場合には、1日8時間相当の労働をした場合でも、曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまうことがあります。
例えば、土曜日・日曜日を所定休日とする完全週休2日制の事業場において、次のようなカレンダーとなる月(暦日31日)があったとします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
原則(完全週休2日制の特例を適用しない場合)
このとき、原則として、法定労働時間の総枠は、「177.1時間」(40時間×31日÷7日)となります。
この場合において、清算期間における総労働時間を、標準となる1日の労働時間(仮に8時間とします)に、清算期間における所定労働日数を乗じて算出すると、清算期間における総労働時間は、「184時間」(8時間×23日)となります。
ところが、このケースでは、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えている(184時間>177.1時間)ことから、総労働時間を177.1時間以内に収めなければならず、かつ、177.1時間を超える労働時間については、36協定を締結した上で、割増賃金を支払う義務が生じることとなります。
しかし、もともと、完全週休2日制の下では、1日8時間以内の所定労働時間を定めておけば、常に1週40時間(1日8時間×週5日)に収まり、所定労働時間が法定労働時間を超えることはあり得ません。
これに対し、フレックスタイム制を適用した場合に、1日8時間相当の所定労働時間を定めているにも関わらず、曜日の巡りによって、法定労働時間の総枠を超えてしまい、それによって36協定の締結や割増賃金の支払いが必要になるという不都合が生じることとなります。
完全週休2日制の特例
上記の不都合を避けるために、完全週休2日制の下で、フレックスタイム制を運用する場合には、法定労働時間の総枠について、次のように計算し、法定労働時間の総枠を延長する特例が認められています。
完全週休2日制の特例
法定労働時間の総枠=清算期間内の所定労働日数×8時間
上記のカレンダーの場合には、特例の適用により、法定労働時間の総枠は、清算期間内の所定労働日数である23日に8時間を乗じた184時間となります。
これによって、特例を適用しない場合の法定労働時間の総枠(177.1時間)に関わらず、184時間を限度として総労働時間(所定労働時間)を定めることができるようになります。
また、36協定の締結と割増賃金の支払いが必要となるのは、延長された法定労働時間の総枠である184時間を超えて労働した場合となります(177.1時間ではありません)。
完全週休2日制の特例を適用する場合の手続
完全週休2日制の特例を適用するためには、労使協定を締結する必要があります(労働基準法第32条の3第3項)。
もともと、フレックスタイム制を適用する場合には、使用者は、制度について就業規則に定めるとともに、労働者の過半数代表者との間で労使協定を締結する必要があります(なお、清算期間が1ヵ月以内の場合は、所轄労働基準監督署への届出は不要です)。
この労使協定の中に、完全週休2日制の特例の適用に関する定めを設けることにより、特例を適用することができます。
労使協定の規定例(記載例)は、次のとおりです。
労使協定の規定例(記載例)
(清算期間における総労働時間)
清算期間における総労働時間は、1日の標準労働時間に、清算期間における所定労働日数を乗じて得た時間とする。
(1日の標準労働時間)
1日の標準労働時間は、8時間とする。
(完全週休2日制の特例の適用)
完全週休2日制の下で働く従業員(1週間の所定労働日数が5日以下の従業員をいう)については、労働基準法第32条の3第3項に基づき、清算期間における総労働時間の限度を、清算期間における所定労働日数に8時間(※)を乗じて得た時間数とすることができる。
(※)「8時間」とは、単に労働基準法が定める法定労働時間であり、標準となる1日の労働時間は必ずしも8時間としなければならないものではありません。
例えば、標準となる1日の労働時間が7時間45分などの場合においても、特例を適用することができます。
まとめ
フレックスタイム制における完全週休2日制の特例をまとめると、次のとおりです。
完全週休2日制の特例のまとめ
【要件】
- 完全週休2日制(週の所定労働日数が5日以内)の事業場であること
- 特例の適用について労使協定を締結すること
【効果】
「清算期間内の所定労働日数×8時間」まで、法定労働時間の総枠(総労働時間の限度)を延長することができる