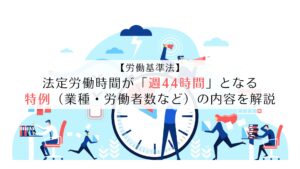【健康保険】「被扶養者」の認定要件(被扶養者の範囲・収入要件など)を解説
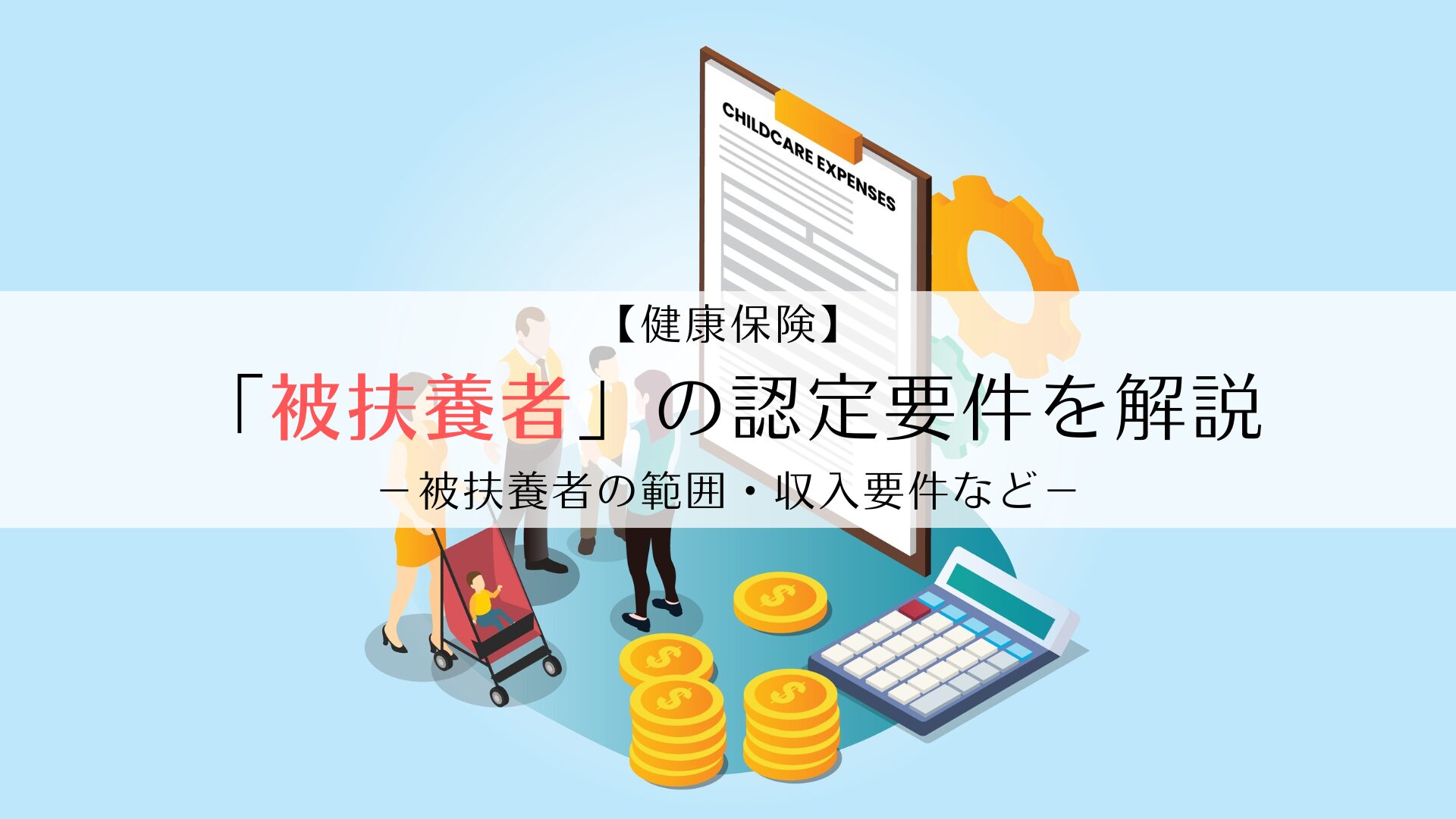
健康保険と被扶養者
健康保険(国民健康保険を除く)では、被保険者と、その被扶養者の病気、けが、出産などに対して保険給付が行われます。
健康保険において、被保険者の親族であって、収入要件など一定の要件を満たす場合には、保険者の認定を受けることによって、被保険者の被扶養者として健康保険に加入することが認められています。
被扶養者となることによって、健康保険料を負担することなく、被保険者と同じ健康保険に加入することができ、被扶養者としての給付(家族療養費、家族出産育児一時金など)を受けることができます。
被扶養者の認定要件
健康保険法において、被扶養者として認定されるための要件は、原則として、日本国内に住所を有する、被保険者と三親等内の親族であって【要件1】、かつ、主として被保険者の収入によって生計を維持されていること【要件2】とされています(健康保険法第3条第7項)。
ただし、後期高齢者医療の被保険者である者は除きます。
【要件1】被扶養者の範囲
被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は、同居の有無によって、次の親族が該当します(健康保険法第3条第7項第一号から第四号)。
【図】被扶養者の範囲
| 被保険者と別居していても認定される親族 | 被保険者と同居している場合のみ認定される親族 |
| ・直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)(※1) ・配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む) ・子(※2) ・孫 ・兄弟姉妹 | ・三親等内の親族(左欄の者を除く)(※3) ・配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係にある者の父母・子 ・上記の配偶者の死亡後におけるその父母・子 |
(※1)
養父母は父母に含まれますが、継父母は父母に含まれません(昭和32年9月2日保発第123号)。
(※2)
民法上の実子および養子をいい、継子は含まれません。
(※3)
「三親等内の親族」とは、三親等内の血族および三親等内の姻族をいいます。
継父母および継子は、父母および子に含まれませんが、三親等内の親族に含まれます(姻族一親等にあたります)(昭和32年9月2日保発第123号)。
被扶養者の国内居住要件
被扶養者は、原則として、日本国内に住所を有する者である必要があります(健康保険法第3条第7項)(2020(令和2)年4月1日改正)。
日本国内に住所を有するかどうかは、住民票によって判断します。
例えば、日本で働く外国人労働者が、国外に居住する家族を被扶養者とすることは、原則として認められません。
ただし、例外として、日本国内に住所を有しない場合であっても、渡航目的その他の事情を考慮して、日本国内に生活の基礎があると認められる場合(外国において留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する者など)は、被扶養者として認定されることがあります(健康保険法施行規則第37条の2)。
【要件2】被扶養者の収入要件
被扶養者の認定要件のうち、主として被保険者の収入によって生計を維持されているか否かの判定は、行政通達に基づき、主に年間収入と被保険者との関連における生活の実態によって判断することとされています(昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号)。
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(※1)(認定対象者が60歳以上の者または一定の障害者(※2)である場合は180万円未満)であること
- 被保険者(扶養者)の年間収入の2分の1未満であること
ただし、上記2.の要件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者または一定の障害者である場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものと認定されることがあります。
(※1)
19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)については、2025(令和7)年10月1日以降に被扶養者の認定を受ける者の年間収入にかかる要件は「150万円未満」となります(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)。
被扶養者の年齢(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢をもって判定されます。
なお、被扶養者が学生であることは、要件とされていません。
年齢と年間収入要件(N年(暦年)に19歳の誕生日を迎える場合)
- N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は「130万円未満」
- N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は「150万円未満」
- N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は「130万円未満」
(※2)
「一定の障害者」とは、概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある者をいいます。
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
- 認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上の者または一定の障害者である場合は180万円未満)であること
- 被保険者(扶養者)からの援助による収入額(仕送り額)より少ないこと
「年間収入」とは
被扶養者の認定における「年間収入」とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降に見込まれる年間の収入額をいい、過去の収入額ではないことに留意する必要があります。
なお、所得税では、1月1日から12月31日までに支給されることが確定した給与をもって所得控除などを判断する点で異なります。
給与収入の場合には、月額108,333円(年間収入に換算すると、1,299,996円)以下であることが、130万円未満となるための目安となります。
「収入」には、給与収入の他、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金および出産手当金なども含まれます。
扶養認定における収入
- 給与収入…税金控除前の総収入額
- 公的年金収入…税金控除前の総収入額
- 自営業者の収入…総収入から必要経費を差し引いた所得額
- 雇用保険の失業等給付…給付日額×360日
- 健康保険の傷病手当金…給付日額×360日
- その他継続性のある収入…税金控除前の総収入額
「同一世帯」とは
「同一世帯」とは、住居および家計を共にしている状況をいいます。
なお、必ずしも同一戸籍内にあることを要せず、被保険者が世帯主であることも要しません(昭和27年6月23日保文発第3533号)。
「住居を共にする(同一住居)」とは、同じ屋根の下に住んでいる場合が最も典型的なものといえます。
ただし、入院している場合は、現実には別居であるものの、退院すればまた自宅に戻るため、別居は一時的なものとして住居を共にしていると解されます。
「家計を共にする(同一家計)」とは、家計を家庭生活における1つの経済単位をもつものと捉え、例えば、同じ屋根の下に兄夫婦と弟夫婦が住んでいて、それぞれの夫の収入で独立して生活をしている場合、それは各々別の家計であると解されます。
また、入院している者または一時的別居の者は、同一家計にあると解されます。
夫婦が共同して扶養している場合の被扶養者の認定
夫婦が共同して扶養している場合の被扶養者の認定は、原則として、被扶養者とすべき者の員数に関わらず、年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い方の被扶養者とします(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)。
なお、夫婦双方の年間収入が同程度である場合(夫婦双方の年間収入の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合)は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。