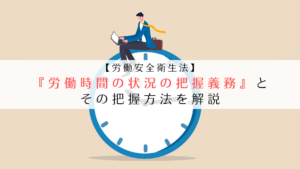法定労働時間が「週44時間」となる「特例措置対象事業場」とは?特例の内容(業種・労働者数など)を解説【労働基準法】
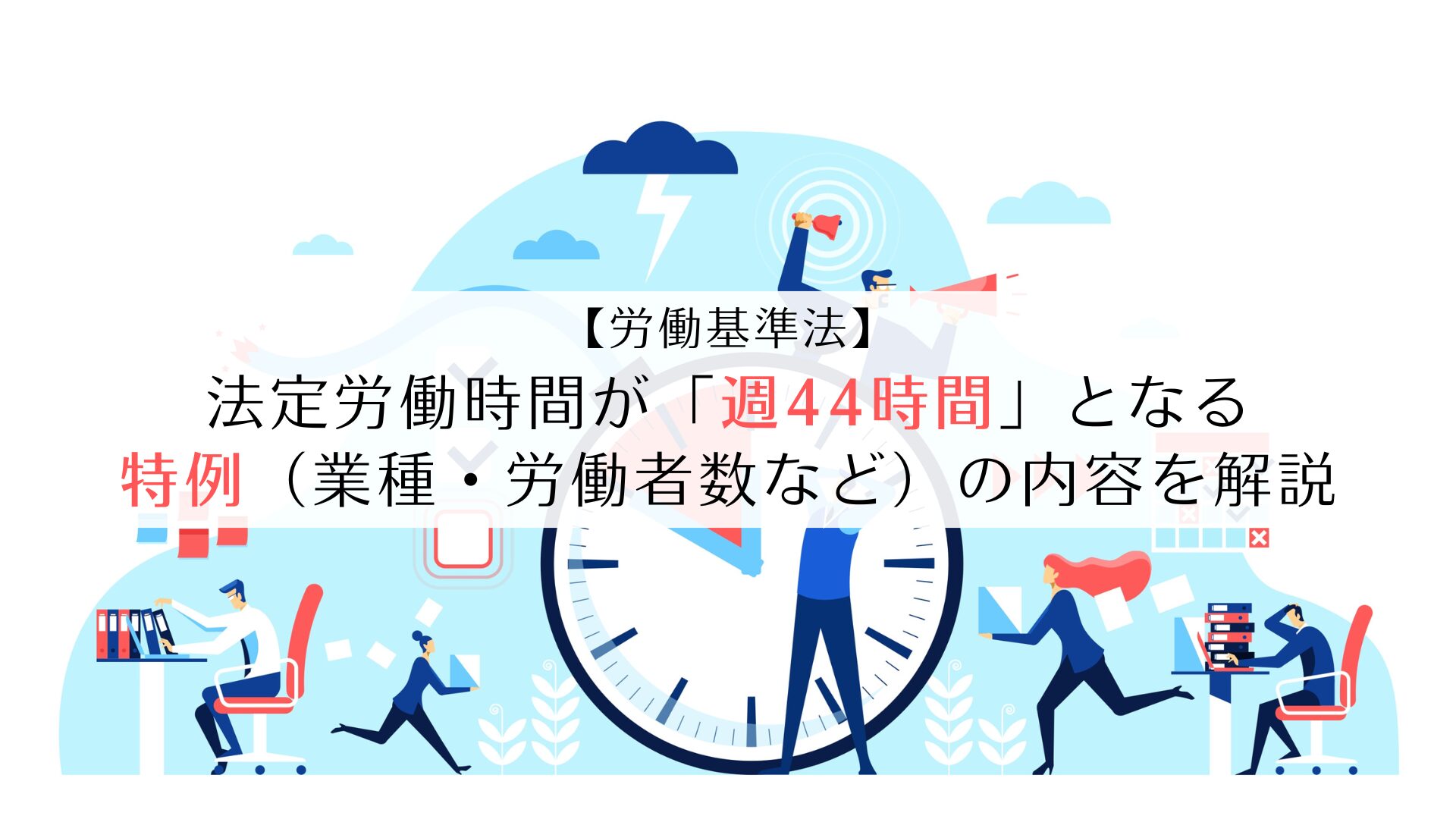
法定労働時間(原則)
労働基準法では、法定労働時間として次の2つの時間を定めており、使用者は、原則として、法定労働時間を超えて労働者を働かせてはならないとされています(労働基準法第32条)。
法定労働時間(休憩時間を除く)
- 1日8時間
- 1週40時間
特例措置対象事業場
原則として、週の法定労働時間は1週40時間とされていますが、次の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場(以下、「特例措置対象事業場」といいます)においては、労働時間の特例が適用されることによって、法定労働時間は「1週44時間」となります(労働基準法第40条、労働基準法施行規則第25条の2)。
一方、1日の法定労働時間については、特例はありませんので、原則と同じく、1日8時間となります。
なお、特例を適用するために、届出や申請などの手続きは必要ありません。
特例措置対象事業場
常時10人未満の労働者を使用する、下記の事業を行う事業場
- 商業 ・映画
- 演劇業(映画製作業を除く)
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
商業
「商業」とは、「物品の販売、配給、保管もしくは賃貸または理容の事業」をいいます(法別表第1第8号)。
例えば、卸売業、小売業、倉庫業、理美容業などが該当します。
映画・演劇業
「映画・演劇業」とは、「映画の映写、演劇その他興行の事業」をいいます(法別表第1第10号)。
なお、「映画製作業」は、特例の対象となりません。
保健衛生業
「保健衛生業」とは、「病者または虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業」をいいます(法別表第1第13号)。
例えば、病院、診療所、社会福祉施設などが該当します。
接客娯楽業
「接客娯楽業」とは、「旅館、料理店、飲食店、接客業または娯楽場の事業」をいいます(法別表第1第14号)。
【表】別表第一と特例の適用関係
| 事業の内容 | 週40時間 | 週44時間 | |
| 1 | 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊もしくは解体または材料の変造の事業(電気、ガスまたは各種動力の発生、変更もしくは伝導の事業及び水道の事業を含む) | 〇 | × |
| 2 | 鉱業、石切り業その他土石または鉱物採取の事業 | 〇 | × |
| 3 | 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業 | 〇 | × |
| 4 | 道路、鉄道、軌道、索道、船舶または航空機による旅客または貨物の運送の事業 | 〇 | × |
| 5 | ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場または倉庫における貨物の取扱いの事業 | 〇 | × |
| 6 | 土地の耕作もしくは開墾または植物の栽植、栽培、採取もしくは伐採の事業その他農林の事業 | 〇 | × |
| 7 | 動物の飼育または水産動植物の採捕もしくは養殖の事業その他の畜産、養蚕または水産の事業 | 〇 | × |
| 8 | 物品の販売、配給、保管もしくは賃貸または理容の事業 | 〇 | 〇 |
| 9 | 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内または広告の事業 | 〇 | × |
| 10 | 映画の製作または映写、演劇その他興行の事業 | 〇 | 〇 |
| 11 | 郵便、信書便または電気通信の事業 | 〇 | × |
| 12 | 教育、研究または調査の事業 | 〇 | × |
| 13 | 病者または虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 | 〇 | 〇 |
| 14 | 旅館、料理店、飲食店、接客業または娯楽場の事業 | 〇 | 〇 |
| 15 | 焼却、清掃またはと畜場の事業 | 〇 | × |
「常時10人未満」の判断
特例の適用要件とされる労働者数(10人未満)は、「常時」とされていることから、どのような状況をもって「常時」といえるのか、労働者の数え方を理解しておく必要があります。
労働者数が一時的に変化する場合
労働者数が10人のボーダーライン上にある事業において、例えば、2、3ヵ月の期間雇用者を新たに雇用することにより、労働者数が一時的に10人以上となる場合があります。
このとき、労働者数が変化する場合における労働者数の判断は、行政通達により、当該事業場の通常の状況によって判断するものであり、臨時的に労働者を雇い入れた場合や欠員が生じた場合については、労働者数の変更があったものとして取り扱わないこととされています(昭和63年3月14日基発150号、平成6年3月31日基発181号、平成9年3月25日基発195号)。
したがって、基本的には、事業場の通常の状況における労働者数で判断することから、一時的・臨時的に雇用した労働者は、労働者に含めずに数えます。
ただし、同行政通達では、ボーダーラインにあるような事業場については、できる限り、週の所定労働時間を40時間以下とすることが望ましいとされています。
労働日数が少ない労働者の取り扱い
例えば、パート・アルバイトなど、フルタイムよりも労働時間や労働日数が少ない労働者(例えば、週に2日勤務する労働者)を、事業場の労働者数に含めるべきか否かについては、行政通達により、継続的に当該事業場で労働している労働者は、労働者数に含めるべきものとされています(昭和63年3月14日基発150号)。
したがって、労働時間や労働日数が少ない労働者であっても、特例の適用に当たっては、一人の労働者として数える必要があります。
「事業場」とは
労働基準法は、事業場単位で適用されるため、特例の適用対象となる労働者数(10人未満)についても、事業場単位で判断します。
「事業場」とは、工場、事務所、店舗など、一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいいます(必ずしも法人単位、組織単位とはなりません)。
一つの事業場であるかどうかは、主として場所的観念によって決定すべきものであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場と判断します(昭和47年9月18日発基91号)。
したがって、特例の適用は、事業場ごとに判断するものであり、法人単位で判断するのではないことに留意する必要があります。
例えば、商業を営む法人が、複数の店舗を営んでいる場合、法人全体でみると労働者数が10人以上であっても、店舗単位(事業場単位)で10人未満であれば、その店舗は、特例措置対象事業場として、週の法定労働時間を44時間とすることができます。
変形労働時間制における取り扱い
事業場で変形労働時間制を運用する場合には、制度によって、週44時間の特例を適用できるか否かが異なります。
【図】変形労働時間制と週44時間の特例(〇:適用できる/×:適用できない)
| 制度 | 週40時間 | 週44時間(特例) |
| 1ヵ月単位の変形労働時間制 | 〇 | 〇 |
| 1年単位の変形労働時間制 | 〇 | × |
| フレックスタイム制 (清算期間1ヵ月以内) | 〇 | 〇 |
| フレックスタイム制 (清算期間1ヵ月超3ヵ月以内) | 〇 | × |
| 1週間単位の非定型的変形労働時間制 | 〇 | × |
1ヵ月単位の変形労働時間制
1ヵ月単位の変形労働時間制では、特例措置対象事業場において、週44時間の特例を適用することが認められています。
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制では、特例措置対象事業場であっても、週44時間の特例を適用することが認められていません(労働基準法施行規則第25条の2第4項)。
フレックスタイム制
フレックスタイム制では、1ヵ月以内の清算期間を定める場合には、特例措置対象事業場において、週44時間の特例を適用することが認められています。
一方、清算期間が1ヵ月を超える場合には、特例措置対象事業場であっても、週44時間の特例を適用することが認められていません(労働基準法施行規則第25条の2第4項)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制では、特例措置対象事業場であっても、週44時間の特例を適用することが認められていません(労働基準法施行規則第25条の2第4項)。
年少者への適用
年少者(満18歳未満の者)を保護する観点から、年少者については、労働基準法が定める労働時間の原則である法定労働時間(労働時間を1日8時間・1週40時間以内とする)と、休憩時間の原則である一斉休憩(事業場の労働者について、一斉に休憩を与える)を守って労働させる必要があります(労働基準法第60条第1項)。
したがって、特例措置対象事業場であっても、年少者に対しては、週44時間の特例は適用されません。