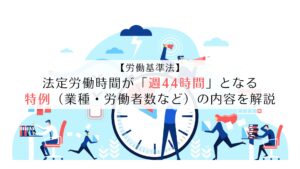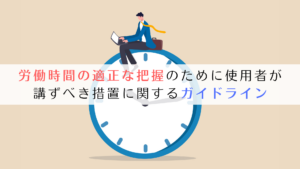「労働時間の状況の把握義務」と、その把握方法を解説【労働安全衛生法】
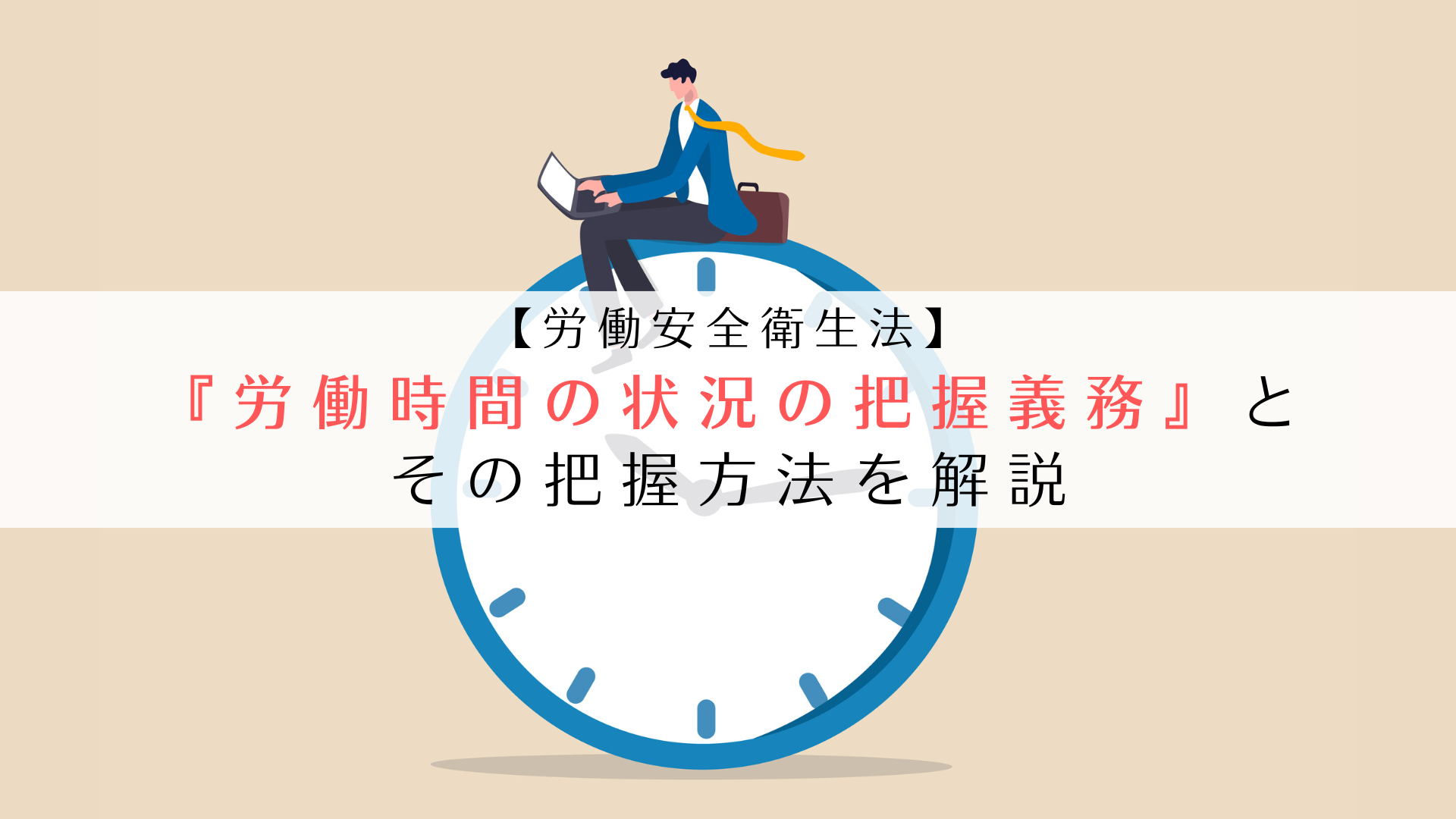
はじめに
労働安全衛生法は、事業者に対し、労働者の労働時間の状況を把握することを義務付けています(2019(令和元)年4月1日施行)。
これにより、事業者は、原則として、タイムカードやパソコンの使用時間などの客観的な方法によって、労働時間の状況を記録・保存する必要があります。
本稿では、労働安全衛生法が定める労働時間の状況の把握義務と、その把握方法を解説します。
労働安全衛生法の定め
労働安全衛生法では、労働時間の状況の把握について、次のとおり定められています(2019(令和元)年4月1日施行)。
労働安全衛生法第66条の8の3
事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第1項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
条文上は、同法が定める面接指導を適切に実施するための前提として、労働者の労働時間の状況を把握することを義務付けています。
「面接指導」とは、医師が問診などの方法によって、労働者の心身の状況を把握し、その状況に応じて、面接によって必要な指導を行うことをいいます。
事業者は、一定時間の時間外労働をした労働者から申し出があった場合には、医師による面接指導を行わなければならないとされています(労働安全衛生法第66条の8第1項)。
面接指導について、詳細は、次の記事をご覧ください。
面接指導とは?長時間労働(月80時間)をした場合の医師の面接指導の実施義務について解説
労働時間の状況を把握すべき労働者の範囲
労働安全衛生法は、基本的にすべての労働者を対象としていることから、原則として、事業場内におけるすべての労働者について労働時間の状況を把握する必要があります。
ただし、例外として、高度プロフェッショナル制度の適用者のみ、対象から除かれています。
行政通達によると、労働時間の状況を把握すべき労働者の範囲は、次のとおりとされています(平成30年12月28日基発1228第16号)。
労働時間の状況を把握すべき労働者の範囲
- 研究開発業務従事者
- 事業場外労働のみなし労働時間制の適用者
- 裁量労働制の適用者
- 管理監督者
- 派遣労働者
- 短時間労働者
- 有期契約労働者
- 上記を含めたすべての労働者
「労働時間の状況の把握」とは
労働安全衛生法が定める「労働時間の状況の把握」とは、行政通達では、労働者の健康確保措置を適切に実施する観点から、労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握するものであるとしています。
「労働時間の状況」は、出勤時刻から退勤時刻までの時間帯において、どの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握するものであって、単に始業・終業時刻から休憩時間を除いた「労働時間」とは異なります。
これによって、例えば、管理監督者や裁量労働制の適用者などであって、その性質上、労働時間を厳密に把握することが困難な場合であっても、事業者は、これらの者が労務を提供し得る状態にあった時間帯などを把握し、その状況から、健康確保のための措置を講じる必要があります。
労働時間の状況を把握する方法
労働安全衛生法では、「厚生労働省令で定める方法」により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないと定めており、これを受けて、厚生労働省令では、次の3つの方法を定めています(労働安全衛生規則第52条の7の3)。
労働時間の状況を把握する方法
- タイムカード、ICカードなどによる記録
- パソコンなどの電子計算機の使用時間の記録
- その他の適切な方法
2.は、業務で利用するパソコンの使用時間の記録によって、労働時間の状況を把握する方法ですが、行政通達では、ここでいう「使用時間」とは、ログインからログアウトまでの時間とされています。
パソコン上の勤怠管理システムなどを用いている場合でも、労働者が自ら手入力した始業・終業時刻のみによる労働時間の状況の把握は、客観的であるとは評価されにくいため、パソコンを使用していたすべての時間によって管理する必要があるとしています。
また、行政通達では、3.に定める方法の具体例として、事業者(事業者から労働時間の状況を管理する権限を委譲された者を含む)による現認を挙げています。
「現認」とは、労働者の出退社時刻などを、その上司などが実際にその目で見て確認した時刻を記録することをいいます。
自己申告制による管理【例外】
労働時間の状況を把握する方法として、問題になりやすいのは、自己申告制による方法です。
「自己申告制」とは、一般に、労働者本人が申告または記録した時刻を、そのまま労働時間として認定することをいいます。
自己申告制は、不適切な運用をすると、本来の労働時間よりも過少に申告することが起こりやすく、長時間労働の温床になりかねません。
したがって、行政通達では、労働時間の状況について、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合【要件1】であって、下記の各措置をすべて講じる場合【要件2】に限り、例外的に、労働者の自己申告による把握を認めることとしています。
【要件1】やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合
「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」とは、例えば、労働者が事業場外において行う業務に直行・直帰する場合など、事業者の現認を含め、労働時間の状況を客観的に把握する手段がない場合をいいます。
したがって、例えば、事業場外からでも勤怠システムにアクセスし、客観的に労働時間を記録することができる場合には、これに該当せず、自己申告制による把握は認められないものと解されます。
また、タイムカードによる出退勤時刻・入退室時刻の記録や、パソコンの使用時間の記録などのデータを有する場合、もしくは事業者の現認により労働者の労働時間を把握できる場合であるにも関わらず、自己申告による把握のみにより労働時間の状況を把握することは、認められません。
【要件2】自己申告制による場合に講ずべき措置
行政通達では、自己申告制による場合には、次の措置をすべて講じる必要があるとしています。
自己申告制による場合に講じるべき措置の内容
- 自己申告制の対象となる労働者に対して、労働時間の状況の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと
- 実際に労働時間の状況を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、講ずべき措置について十分な説明を行うこと
- 自己申告により把握した労働時間の状況が、実際の労働時間の状況と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、両者に乖離がある場合には、所要の補正をすること
- 自己申告した労働時間の状況を超えて事業場内にいる時間、または事業場外において労務を提供し得る状態であった時間について、その理由などを労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。その際に、休憩や自主的な研修・教育訓練・学習などであるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、事業者の指示により業務に従事しているなど、事業者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間の状況として扱わなければならないこと
- 事業者は、労働者が自己申告できる労働時間の状況に上限を設け、上限を超える申告を認めないなど、労働者による労働時間の状況の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと
- 時間外労働の削減のための社内通達や、割増賃金の定額払いなど、労働時間にかかる事業場の措置が、労働者の労働時間の状況の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認すること(阻害する要因となっている場合には、改善のための措置を講ずること)
- 36協定によって定められた時間外労働の延長時間数について、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにも関わらず、記録上はこれを守っているようにすることが、実際に労働時間の管理者や労働者などにおいて、慣習的に行われていないかについて確認すること
記録の頻度・保存期間
記録の頻度
行政通達では、労働時間の状況に関する記録の頻度について、労働時間の状況を自己申告により把握する場合には、その日の労働時間の状況を翌労働日までに自己申告させる方法が適当であるとしています。
なお、労働者が宿泊を伴う出張を行っているなど、労働時間の状況を労働日ごとに自己申告により把握することが困難な場合には、後日一括して、それぞれの日の労働時間の状況を自己申告させることとしても差し支えありません。
保存期間
事業者は、把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存しなければならないとされています(労働安全衛生規則第52条の7の3第2項)。
記録および保存は、紙媒体で出力することによる記録の他、磁気ディスクなどに記録・保存することでも差支えありません。