「時間単位年休」の残日数(残時間)管理と、繰り越し方法(端数の取り扱い)について解説【労働基準法】
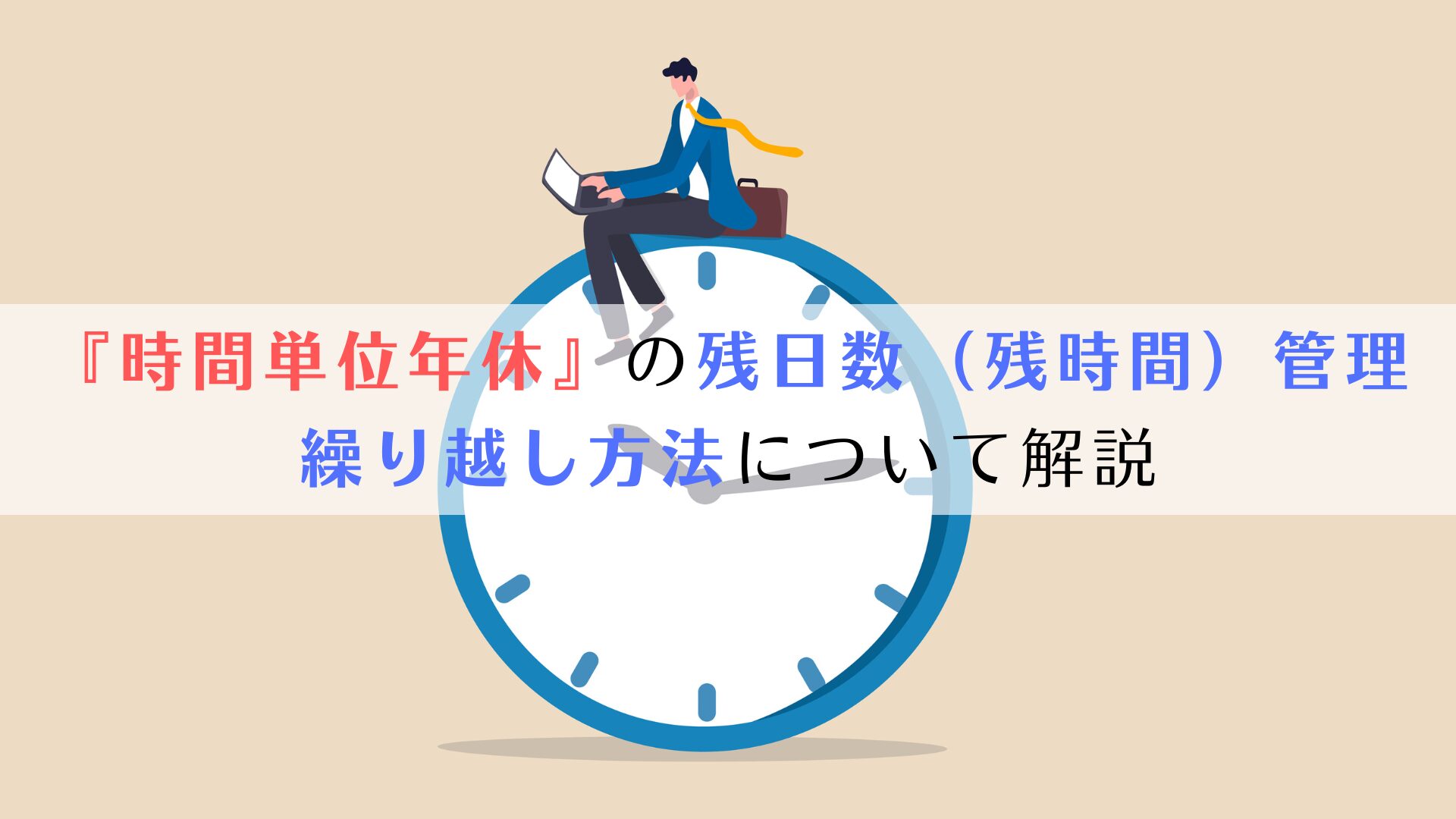
はじめに
労働基準法では、年次有給休暇の取得の促進を図るために活用できる制度として、1時間単位で年次有給休暇を取得することができる制度(以下、「時間単位年休」といいます)が定められています。
年次有給休暇の取得単位が細かくなることに伴って、年次有給休暇の残日数(残時間)について、実務上、どのように残日数(残時間)を管理し、繰り越しをしていくのか、判断に迷うことがあります。
本稿では、時間単位年休の残日数(残時間)管理と、繰り越し方法について、解説します。
なお、時間単位年休の基本的な制度内容については、次の記事をご覧ください。
1時間単位の有給休暇(時間単位年休)とは?制度の内容・労使協定の記載例を解説
時間単位年休の残日数(残時間)の管理方法
時間単位年休を運用する際に、実務上、どのように残日数(残時間)を管理するのか、判断に迷うことがあります。
残日数(残時間)管理の方法としては、時間単位年休の枠(最大5日)について、【A】「日数+時間数」によって管理するべきか、または、【B】「時間数」によって管理するべきかが問題となります。
事例1
- 所定労働時間…1日8時間
- 年次有給休暇…20日(うち時間単位年休5日)
- 4月1日に、3時間の時間単位年休を取得した
上記の事例において、次の管理方法が考えられます。
管理方法
【A】「日数+時間数」によって管理する方法…年次有給休暇は労働日(日数)によって管理することが原則であることから、3時間の時間単位年休を取得したのであれば、年次有給休暇の残日数(残時間)は「19日と5時間」、うち時間単位年休の残日数(残時間)は「4日と5時間」である
【B】「時間数」によって管理する方法…年次有給休暇20日のうち、時間単位年休の枠として40時間(8時間×5日)あるものと捉え、40時間のうち3時間を取得したのであれば、時間単位年休の残日数(残時間)は「37時間」である
法律上、年次有給休暇は1労働日単位で与えられ、原則として1日単位で取得するものであることから、時間単位年休を導入している場合であっても、「労働日(日数)単位」で管理することが基本であると解されます。
また、時間単位年休を取得できる部分の日数であっても、最終的には、1日単位で取得するか、または時間単位で取得するかは、取得時における従業員本人の意思によるものです。
したがって、時間単位年休を導入している場合において、残日数(残時間)の管理は、原則として【A】の「日数+時間数」で行うべきものと解されます。
【年次有給休暇取得簿の例①(「日数+時間数」による管理)】
| 取得日 | 取得日数または時間 | 残日数・残時間 (うち時間単位年休) |
| 4月1日 | 3時間 | 19日と5時間 (4日と5時間) |
いずれの管理方法によるかによって、直ちに問題が生じるものではありませんが、後述する時間単位年休の繰り越しを適切に行うためには、まずは原則的な管理方法を理解する必要があります。
半日単位の年次有給休暇(半日年休)を取得する場合
労働基準法では、行政通達に基づき、年次有給休暇を半日単位で取得すること(以下、「半日年休」といいます)を認めています。
例えば、次の事例のように半日年休を取得した場合、【C】半日年休を労働日(日数)単位で管理するべきか、または、【D】半日年休を(時間単位年休と同様に)時間換算して管理するべきかが問題となります。
事例2
(事例1の続き)
- 年次有給休暇の残日数(残時間)は、19日と5時間である
- 4月2日に、半日年休(4時間)を取得した
上記の事例において、次の管理方法が考えられます。
管理方法
【C】半日年休を労働日(日数)単位で残日数(残時間)を管理する方法…残日数(残時間)「19日と5時間」のうち、半日年休として0.5日分取得したものと捉え、残日数(残時間)は「18.5日と5時間」(時間単位年休の残日数(残時間)は「4日と5時間」のまま)である
【D】半日年休を時間換算して残日数(残時間)を管理する方法…残日数(残時間)の「19日と5時間」のうち、半日年休として4時間分取得したものと捉え、残日数(残時間)は「19日と1時間」である
前述のとおり、法律上、年次有給休暇は労働日(日数)単位で与えられるものであることから、残日数の管理も、原則として【C】のとおり、「労働日(日数)単位」で行うべきものと解されます。
半日年休は、あくまでも労働日単位による年次有給休暇の特例であることから、「労働日(日数)単位(0.5日単位)」で管理すべきであり、時間換算して時間単位年休と混同して管理することは適切ではないと解されます。
ただし、半日年休を取得した場合の年次有給休暇の日数(時間数)の取り扱いについて、労使協定でこれと異なる取り扱いを定めることは、法律を下回らない限り、問題ないものと解されます。
【年次有給休暇取得簿の例②(半日年休を取得した場合)】
| 取得日 | 取得日数または時間 | 残日数・残時間 (うち時間単位年休) |
| 4月1日(事例1) | 3時間 | 19日と5時間 (4日と5時間) |
| 4月2日(事例2) | 0.5日 | 18.5日と5時間 (4日と5時間) |
時間単位年休の繰り越し(繰り越した際の端数の取り扱い)
基本的な考え方
時間単位年休の取得日数の上限は、「年に5日間まで」とされています。
5日を超える分については、原則どおり1日単位の有給休暇を取得する必要があります。
例えば、1日の所定労働時間が8時間の会社の場合、従業員が時間単位年休を取得できる上限時間は、40時間(8時間×5日)となります。
年度内に取得されなかった年次有給休暇は、翌年度に限り、繰り越されますので、時間単位年休についても、取得されなかった残余の時間について、翌年度に繰り越されることとなります。
そして、翌年度における時間単位年休の日数(時間)は、前年度から繰り越された日数(時間)がある場合には、その日数(時間)を含めて、5日の範囲内とする必要があります(平成21年5月29日基発第0529001号)。
したがって、翌年度は、「繰り越した日数(時間)+5日」が取得の上限になるのではない、ということに留意する必要があります。
事例
事例3
- 所定労働時間…1日8時間
- 年次有給休暇…20日(うち時間単位年休5日)
- 年度内に、時間単位年休として、11時間を取得した。
上記の事例において、翌年度に繰り越される年次有給休暇の日数は、「日数+時間数」で管理する方法(前述の【A】)によれば、「20日-(1日と3時間)=18日と5時間」になります。
ここでは、前述のとおり、日数で把握できるものは、通常の年次有給休暇として、1日単位で繰り越します。
つまり、時間単位年休の取得時間が8時間に達したときは、1日の年次有給休暇を取得したものとして取り扱う(1日に繰り上げる)ことから、翌年度に時間単位で繰り越されるのは、常に、8時間未満の時間ということになります。
事例では、40時間から11時間を差し引いた、29時間の時間単位年休が繰り越される、と捉えるべきではなく、11時間の時間単位年休を、「1日と3時間」と捉えた上で、時間単位年休として翌年に繰り越すのは「5時間」となります。
事例4
(事例3の続き)
- 前年度から繰り越された年次有給休暇…18日と5時間
- 翌年度の年次有給休暇…20日
翌年度においては、繰り越された年次有給休暇と併せて、「38日と5時間」(18日と5時間+20日)の年次有給休暇をもつことになります。
そして、前述のとおり、時間単位年休の日数は、前年度の繰り越し分の日数がある場合には、その日数を含めて、5日の範囲内とする必要がありますので、時間単位年休を行使できる5日(40時間)の内訳は、「前年度から繰り越された5時間+翌年度で新たに付与された年次有給休暇20日のうち、35時間(4日と3時間)」となります。
繰り越しによって生じた端数の取り扱い
事例4において、前年度から5時間の時間単位年休が繰り越されると、翌年度に付与される年次有給休暇20日のうち、5時間分が端数となり、理論上、取得できないこととなります。
この端数が取得できない点については、法律上、5日を超えて時間単位年休を取得させてはならないと定められている以上、たとえ従業員から請求されても、与えることはできず、会社が与えないとしても、違法ではないと解されます。
このとき、時間単位年休を繰り越した結果として生じる端数の取り扱いについては、次のように処理することが考えられます。
1日未満の端数が残った場合の処理
- 翌年度に繰り越す
- 端数を1日単位に切り上げて、1日として与える
端数を翌年に繰り越す
法律上、取得することができない端数については、そのまま時効を迎えるのではなく、翌年度に新たな年次有給休暇が与えられる際に、繰り越されることとなります。
つまり、翌年度の時間単位年休の枠(40時間)の枠の中に、端数の5時間が繰り越される結果、翌年度における時間単位年休として取得できるようになることから、従業員にとって不利益になるものではないと解されます。
端数を1日に切り上げて、1日の年次有給休暇として与える
時間単位年休の繰り越しによって、端数が生じた場合、それを1日に切り上げて、1日単位で年次有給休暇を取得できるようにすることも考えられます。
このとき、従業員には法律を上回る権利が付与されることから、不利益が生じることはありません。
また、この処理は、例えば、従業員が退職する際に、残りすべての年次有給休暇を取得する場合など、端数を翌年度に繰り越すことができない状況において、限定的に適用することが考えられます。


