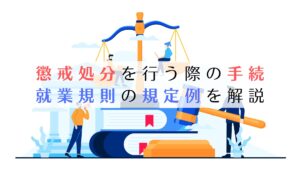懲戒処分を行う前の「自宅待機命令」について解説
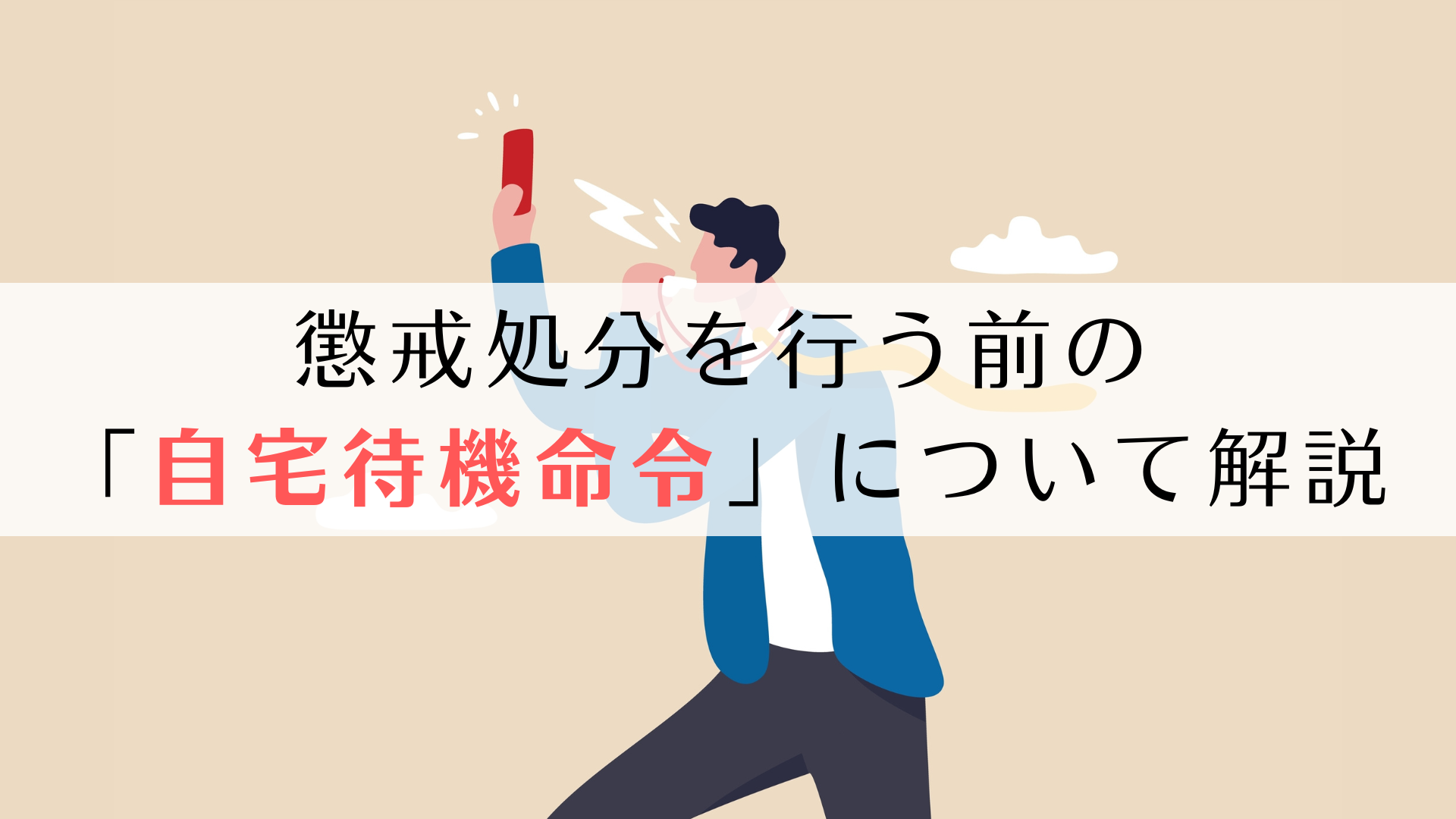
はじめに
労働者による就業規則上の懲戒事由に該当する行為(以下、「違反行為」といいます)が発覚した場合において、使用者がその事実関係を調査し、懲戒処分を検討するまでの間、労働者に対して自宅待機を命じることがあります。
本稿では、懲戒処分に関連して行われる「自宅待機命令」について解説します。
なお、懲戒処分を行う際の一連の手続(調査、弁明の付与、懲戒委員会など)については、次の記事をご覧ください。
懲戒処分を行う際の手続(調査・弁明の付与・懲戒委員会など)を流れに沿って解説
「自宅待機命令」とは
「自宅待機命令」とは、一般に、労働者による違反行為が発覚した後、懲戒処分を決定するまでの間において、労働者を引き続き就労させることが不適当である場合に、使用者が労働者に対して自宅待機を命じることをいいます。
自宅待機命令は、例えば、次のような目的で行われることがあります。
自宅待機命令の目的(例)
- 労働者が出社することにより、調査に支障が生じることを防止するため
- 労働者による違反行為の証拠の隠滅(証拠物を処分するなど)を防止するため
- 他の労働者への口封じを防止するため
- 不正行為の再発を防止するため
- 職場の秩序に混乱が生じることを防止するため(職場秩序の維持のため)
自宅待機命令を行う法的根拠
自宅待機命令を行う法的根拠
自宅待機命令は、労働契約上の指揮命令権に基づき、一種の業務命令として行うものであると解されます。
裁判例では、自宅待機命令の性質について、「自宅謹慎は、それ自体として懲戒的性質を有するものではなく、当面の職場秩序維持の観点から執られる一種の職務命令とみるべき」と示しています(日通名古屋製鉄作業株式会社事件/名古屋地方裁判所平成3年7月22日判決)。
したがって、自宅待機命令の後に懲戒処分を行う場合であっても、二重処罰(同じ行為に対して、二重に処罰すること)には該当しないと解されます。
就業規則上の根拠の必要性
労働者は、労働契約に基づき労務を提供する義務を負っていますが、使用者に対して就労することを求める権利(就労請求権)は有していないと解されるため、使用者が労働者の就労を拒否することは、賃金を支払う限り、違法ではないと解されます。
したがって、自宅待機期間中の賃金を支払う限りは、就業規則の規定(例えば、違反行為が判明した者に対し、処分が確定するまでの間、就業を禁止する旨の規定)がない場合であっても、業務命令として自宅待機を命じることは可能と解されます。
ただし、労務管理上は、自宅待機命令について就業規則に定め、労働契約の内容として明確にしておく方が望ましいと考えます。
自宅待機命令の期間の長さ
裁判例では、「業務上の必要から、自宅待機を命ずることも、雇用契約上の労務指揮権に基づく業務命令として許される」としたうえで、2年にわたる長期の自宅待機命令を違法ではないと判断した事案があります(ネッスル事件/静岡地方裁判所平成2年3月23日判決)。
ただし、同裁判例では、その前提条件として、「業務命令として自宅待機を命ずることができるとしても、労働関係上要請される信義則に照らし、合理的な制約に服すると解され、業務上の必要性が希薄であるにもかかわらず、自宅待機を命じあるいはその期間が不当に長期にわたる等の場合には、自宅待機命令は、違法性を有するものというべきである」と示しています。
したがって、いかなる場合でも当然に自宅待機命令が認められるものではなく、必要以上に長期にわたる自宅待機命令は違法となり得ることから、自宅待機を命じる理由に応じて、適切な期間に留める必要があります。
なお、他の裁判例では、航空機の上級整備士が、勤務中に旅客機内で誤って少量のシャンパンを口にしたという違反行為に対して自宅待機が命じられた事案について、少なくとも自宅待機期間が約7ヵ月に及んだ後の時点では、「正当な理由を欠く違法なものといわざるを得ない」と判断したものがあります(ノースウェスト航空整備士シャンパン誤飲事件/千葉地方裁判所平成5年9月24日判決)。
自宅待機期間中の労働者の義務
調査のための出社命令・禁止事項など
自宅待機期間においては、労働者に対し、就業時間中は自宅で待機しておき、使用者から事情聴取などのために出勤を命じられれば、直ちにこれに応じることができる態勢に整えておくことを命じることが一般的です。
また、必要性に応じて、他の労働者や取引先との接触を禁止することもあります。
使用者の調査権限の有無
使用者が違反行為に関する調査を行う権限があるかどうかについて、裁判例では、「企業秩序に違反する行為があった場合には、その違反行為の内容、態様、程度等を明らかにして、乱された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し、または違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができることは、当然のことといわなければならない」として、使用者による調査権限を認めています(富士重工業事件/最高裁判所昭和52年12月13日判決)。
労働者の調査協力義務の有無
裁判例では、労働者が調査に応じる義務を負うかどうかについては、「企業が企業秩序違反事件について調査をすることができるということから直ちに、労働者が、これに対応して、いつ、いかなる場合にも、当然に、企業の行う調査に協力すべき義務を負っているものと解することはできない」とした上で、労働者が調査協力義務を負うのは、原則として、次のいずれかに該当する場合であることを示しました(富士重工業事件/最高裁判所昭和52年12月13日判決)。
労働者が調査協力義務を負う場合
- 当該労働者が他の労働者に対する指導、監督ないし企業秩序の維持などを職責とする者であって、調査に協力することがその職務の内容となっている場合
- 調査対象である違反行為の性質、内容、当該労働者の違反行為の見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無など、諸般の事情から総合的に判断して、調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的である場合
出勤停止処分との関係性
「出勤停止(処分)」とは、一般に、労働者の就労を一定期間禁止する懲戒処分をいいます。
出勤停止の期間については、法律による制限はありませんので、事案に応じて、使用者の判断によって決めることになります。
出勤停止の処分を受けている期間は、労働者に対してその間の賃金は支給されないことが一般的です。
使用者が懲戒処分を行う場合において、同じ行為に対して、二重に処罰すること(二重処罰)は禁じられています。
そこで、自宅待機命令が、懲戒処分としての出勤停止に該当するかどうかが問題となりますが、この点、裁判例では、自宅待機命令は、懲戒処分としての出勤停止には該当しないと示しています(中央公論社事件/東京地方裁判所昭和54年3月30日判決)。
したがって、自宅待機命令の後、懲戒処分を行う場合であっても、二重処罰には該当しないと解されます。
待機期間中の賃金
待機期間中の賃金について、前述のとおり、自宅待機は使用者の業務命令に基づくものであり、これをもって労働者の労務提供義務は尽くされていると解されることから、使用者は、原則として、自宅待機期間中の賃金を支払う義務を負います。
裁判例では、「自宅謹慎は、それ自体として懲戒的性質を有するものではなく、当面の職場秩序維持の観点から執られる一種の職務命令とみるべきものであるから、使用者は当然にその間の賃金支払い義務を免れるものではない」として、自宅待機期間中の賃金の請求を全額認めたものがあります(日通名古屋製鉄作業株式会社事件/名古屋地方裁判所平成3年7月22日判決)。
そして、使用者が賃金支払義務を免れるためには、「当該労働者を就労させないことにつき、不正行為の再発、証拠隠滅のおそれなどの緊急かつ合理的な理由が存するか、またはこれを実質的な出勤停止処分に転化させる懲戒規定上の根拠が存在することを要すると解すべきであり、単なる労使慣行あるいは組合との間の口頭了解の存在では足りないと解すべきである」と示しています。
自宅待機命令に関する就業規則の規定例(記載例)
自宅待機命令に関する就業規則の規定例(記載例)は、次のとおりです。
自宅待機命令に関する就業規則の規定例(記載例)
(自宅待機命令)
第●条 会社は、本規則に定める懲戒事由に該当する行為をしたことが発覚し、またはその疑いがある従業員に対して、その調査を行い、処分を決定するまでに必要な期間について、自宅待機を命じることがある。
2 自宅待機期間中の賃金は、原則として支給する。ただし、従業員の行為が諭旨解雇もしくは懲戒解雇事由に該当し、または該当する疑いがある場合であって、自宅待機を命じる理由が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、自宅待機期間中の賃金を支給しない。【注1】
一、不正行為の再発のおそれがある場合
二、証拠隠滅のおそれがある場合
三、前各号の他、緊急かつ合理的な理由がある場合
3 会社は、前項に基づき自宅待機を命じる場合は、対象従業員に対して「自宅待機命令書」を交付する。【注2】
【注1】賃金を支給しない場合の規定
規定例では、賃金を支給しないことの有効性を基礎づけるため、出勤停止を超える懲戒処分である、諭旨解雇または懲戒解雇に相当する重大な非違行為があった場合に限定しています。
なお、第一号から第三号までの事由は、前掲の裁判例(日通名古屋製鉄作業株式会社事件/名古屋地方裁判所平成3年7月22日判決)で示された事由を参考にしています。
【注2】自宅待機命令書
自宅命令を命じる際において、法律上は書面の交付が求められるものではありませんが、自宅待機の期間や、自宅待機中における指示事項(出社の禁止、取引先などとの接触禁止、調査への協力義務など)を明らかにするためにも、これらを記載した書面を交付することが望ましいと考えます。