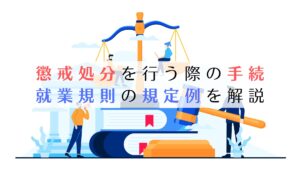懲戒処分を行う際の基本原則(明確性の原則、不遡及の原則、一時不再理の原則など)を解説

はじめに
一般に、会社の就業規則には、服務規律に違反した従業員への懲戒処分に関する規定が定められています。
懲戒処分は、いわば会社における刑罰としての位置づけにあり、従業員にとっては、その地位や賃金に影響を及ぼし、場合によっては解雇されることもあり得る、人事上の重大な措置です。
それだけに、懲戒処分は、訴訟などの労務トラブルに発展しやすく、懲戒処分を行うにあたっては、法的なリスクが生じることのないよう、慎重な対応を要します。
本稿では、懲戒処分を行う際の、基本となる原則を解説します。
懲戒処分とは
「懲戒処分」とは、一般に、会社組織において、社内の秩序を維持するために、組織のルールに違反した従業員に対して、制裁として行われる人事上の措置をいいます。
会社が従業員に対して懲戒処分をすることができる法的な根拠は、会社に「懲戒権」があると解されるためです。
裁判例では、「使用者の懲戒権の行使は、企業秩序維持の観点から労働契約関係に基づく使用者の権能として行われるものである」として、懲戒権の行使を認めています(ネスレ日本事件/平成18年10月6日最高裁判所判決)。
懲戒処分には、処分の程度が比較的軽いものとして戒告・譴責(けん責)があり、最も重いものとして懲戒解雇があります。
懲戒処分の種類については、次の記事をご覧ください。
懲戒処分とは?懲戒処分の種類や具体例、留意点などをわかりやすく解説
懲戒処分を行う際の基本原則
懲戒処分を行う際において、基本となる原則は、次のとおりです。
これらの原則は、労働基準法などの法令に明記されているものではなく、裁判例や法令の解釈から導かれるものです。
懲戒処分を行う際の基本原則
- 明確性の原則
- 不遡及の原則
- 一時不再理の原則(二重処分の禁止)
- 比例原則(相当性の原則)
- 公平取り扱いの原則(平等原則)
- 適正手続の実施
以下、順に解説します。
明確性の原則
懲戒処分は、会社が定めたルールに違反する行為に対する制裁であり、罰として不利益をもたらすという点で、国家が犯罪と定めた行為をした者に対して刑罰を科す、刑事手続と類似しています。
そこで、刑罰を科すにあたって重要な原則とされている、「罪刑法定主義」の考え方が、懲戒処分においても妥当すると解されています。
「罪刑法定主義」とは、「事前に犯罪として法律に定められた行為だけが、犯罪として処罰することができる」という刑事手続上の考え方をいい、罪刑法定主義から派生する原則として、「あらかじめ刑罰の内容が法律で明確にされていなければならない」という、「明確性の原則」があります。
明確性の原則を懲戒処分に当てはめると、会社が従業員に懲戒処分を行う場合には、あらかじめ就業規則において、懲戒処分の対象となる行為(懲戒事由)と、それに対する懲戒処分の内容を定めておく必要があります。
なお、就業規則が法的な効力を生じるためには、その内容を従業員に周知する必要があるとされていますので、単に就業規則に懲戒事由を定めるだけでなく、その内容を従業員に周知して初めて就業規則の効力が生じることに留意する必要があります。
不遡及の原則
「不遡及の原則」とは、懲戒処分の根拠規定は、従業員が行為をした時点で存在することが必要であり、新たに(後から)設けた懲戒処分の根拠規定を、規定を設ける以前の行為に遡って適用することはできないとする考え方です。
したがって、行為の当時、懲戒事由に該当しなかった行為については、改定後の就業規則に基づいて懲戒処分を行うことはできません。
裁判例では、就業規則の改定前後の実施期間にまたがる従業員の行為について、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」と示し、改定前の従業員の行為について、懲戒事由を遡及して適用することを否定しました(フジ興産事件/最高裁判所平成15年10月10日判決)。
また、別の裁判例では、会社が改定後の新しい就業規則の懲戒事由に基づき従業員を解雇した事案について、「本件解雇の事由の最も重要な部分ともいうべき犯行行為は、旧規則が施行、適用されている当時になされたものであるから、その懲戒権の存否は本来旧規則の規定によって決せられるべきである」と示しています(理想社事件/東京地方裁判所昭和57年3月19日判決)。
一時不再理の原則(二重処分の禁止)
「一時不再理の原則(二重処分の禁止)」とは、過去に一度懲戒処分の対象となった行為については、重ねて懲戒処分を行うことはできないとする考え方です。
これは、日本国憲法第39条の「何人も、(略)同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」という定めに基づく考え方です。
同じ行為について重ねて処分をされると、従業員にとって予想外の不利益となり、また、後から再度処分される可能性が残るというのは、従業員の地位を不安定にするためです。
ただし、新たな行為に対する懲戒処分の際に、過去に同様の行為により懲戒処分を受けた実績(問題行為を繰り返していること)を考慮することは、特に禁止されません。
裁判例では、「懲戒処分は、使用者が労働者のした企業秩序違反行為に対してする一種の制裁罰であるから、一事不再理の法理は就業規則の懲戒条項にも該当し、過去にある懲戒処分の対象となった行為について重ねて懲戒することはできないし、過去に懲戒処分の対象となった行為について反省の態度が見受けられないことだけを理由として懲戒することもできない」として、一時不再理の原則(二重処分の禁止)が懲戒処分についても適用されることを示しています(平和自動車交通事件/東京地方裁判所平成10年2月6日決定)。
比例原則(相当性の原則)
「比例原則(相当性の原則)」とは、懲戒処分は、懲戒処分の対象とされている行為の性質や態様などに照らして、相当なものでなければならないとする考え方です。
懲戒事由に該当する従業員の行為と、それに対する懲戒処分との均衡が取れていない場合(行為に照らして懲戒処分が重すぎる場合)は、懲戒処分は無効と解されます。
労働契約法第15条では、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定められています。
公平取り扱いの原則(平等原則)
「公平取り扱いの原則(平等原則)」とは、懲戒処分の規定は、従業員に平等に適用されなければならず、同じような事案には、それに対する懲戒処分も同じ程度でなければならないとする考え方です。
したがって、会社は、懲戒処分を行った際には、その事例を記録しておき、懲戒処分を行うにあたっては、過去の事例についてどの程度の処分がなされたのかを勘案する必要があります。
もし、過去の同様の事例よりも重い処分を行う場合には、なぜ重い処分とせざるを得ないのか、その理由を明確にしておく必要があります。
裁判例では、出張先への移動手段を偽り、100回にわたり旅費を不正受給したなどとして懲戒解雇した事案において、非違行為の態様は停職3ヵ月とされた他の従業員と同程度であり、処分の均衡を失するとして無効と判断したものがあります(なお、原告の方が不正受給額は大きい(原告は約54万円、他の従業員は約28万円)ものの、期間や回数は少ない(原告は1年半で100回、他の従業員は3年半で247回)状況でした)(日本郵便(地位確認等請求)事件/札幌高等裁判所令和3年11月17日判決)。
適正手続の実施
労働基準法などの労働関連法令には、懲戒処分を行う際の手続について、特に定められていません。
しかし、懲戒処分は、刑事罰に類似したものであることから、手続面においても、刑事手続と同様に、適正手続が担保されることが求められると解されます。
したがって、懲戒処分について手続的な相当性を欠く場合には、社会通念上相当なものと認められず、懲戒権の濫用となる場合があります(弁明の機会を付与せず懲戒解雇をした事案として、学校法人千代田学園教員懲戒解雇事件/東京地方裁判所平成15年10月9日判決)。
懲戒処分を行う際の手続としては、例えば、従業員への弁明の機会の付与、懲戒委員会の設置、労働組合との協議を行うことなどが挙げられます。
懲戒処分を行う際の手続については、次の記事をご覧ください。
懲戒処分を行う際の手続(調査・弁明の付与・懲戒委員会など)を流れに沿って解説