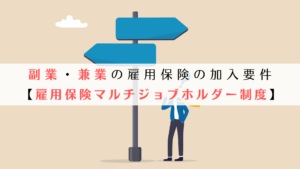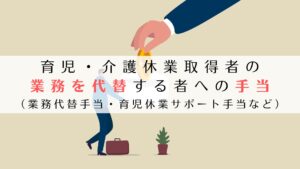長時間労働による過労死の労災認定基準(過労死ライン)を解説

はじめに
厚生労働省は、労働者が、過重労働に起因する脳・心臓疾患によって死亡した場合において、労災認定のための基準(以下、「過労死の認定基準」といいます)を定めています。
本稿では、過労死の認定基準について、その内容を解説します。
労災保険と過労死の認定基準
労災保険とは
労働者が業務に起因して負傷し、または疾病を発症した場合には、労働者を保護するために、労災保険による給付が行われます。
「労災保険(労働者災害補償保険)」は、労働者の業務上の負傷・疾病(労災)に対し、医療費の補償(療養補償給付)、休業中の生活費の補償(休業補償給付)、死亡した場合における遺族への補償(遺族補償年金)などの給付を行う社会保険をいいます。
労災の認定は、労災保険を管掌する労働基準監督署によって行われます。
労災保険と過労死の認定基準
労災として認定され、労災保険の給付が行われるためには、業務と負傷・疾病との間に因果関係があることが必要です。
しかし、特に過労死が疑われる脳・心臓疾患については、加齢や生活習慣などによって自然経過をたどって発症することもあることから、それが業務の負荷によって発症したものであるかどうかを判断することが困難です。
そこで、厚生労働省は、過重労働による発症が疑われる脳血管疾患と心疾患のための労災認定基準として、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和5年10月18日基発1018第1号)」を定めており、当該基準に従って、労災認定を行うこととしています。
過労死の認定基準の内容
対象となる疾病
過労死の認定基準では、次の疾病を認定の対象としています。
対象疾病
- 脳血管疾患(脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症)
- 虚血性心疾患等(心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、重篤な心不全、大動脈解離)
認定要件
過労死の認定基準では、上記の対象疾病が、次の要因によって発症した場合には、業務上の疾病として取り扱うこととしています。
業務上の疾病として取り扱う場合
- 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(長期間の過重業務)に就労したこと
- 発症に近接した時期において、特に過重な業務(短期間の過重業務)に就労したこと
- 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的・場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと
過労死の認定基準では、過労死が疑われる事案では、長期間、短期間および発症日の直前(前日)における事情を勘案し、疲労の蓄積度合いを判断します。
1.の「発症前の長期間」とは、発症前のおおむね6ヵ月間をいいます。
特に、長時間労働が長期間にわたって行われた場合に、どの程度の労働時間であれば、過重な業務に該当するかの目安を示すものとして、後述の「過労死ライン」があります。
2.の「短期間」とは、発症前のおおむね1週間において、特に過重な業務が認められることをいいます。
3.の「異常な出来事」とは、極度の緊張、興奮、恐怖、驚がくなど、強度の精神的負荷を引き起こす突発的または予測困難な事態(生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合)や、急激で著しい作業環境の変化をいいます。
時間外労働と過労死ライン
過労死ラインとは
発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす過重な業務に該当すると判断される時間外労働の目安を、「過労死ライン」ということがあります。
過労死ラインは、長期間にわたって長時間の時間外労働が行われた事実をもって、疲労の蓄積をもたらす過重な業務があったとして、業務上の疾病と認めるものです。
具体的には、労働者の時間外労働が、次の要件に該当する場合には、業務と疾病との関連性が「強い」ものと評価されます。
業務と疾病との関連性が「強い」とされる場合
- 発症前の直近1ヵ月の時間外労働が100時間を超える
- 発症前の2ヵ月ないし6ヵ月間の時間外労働が月80時間を超える
時間外労働とは
過労死の認定基準における時間外労働とは、1週間あたり40時間(労働基準法が定める法定労働時間)を超えて労働した時間数をいいます。
なお、休日のない連続勤務が長く続くほど、業務と発症との関連性をより強めるものであり、反対に、休日が十分確保されている場合は、疲労は回復ないし回復傾向を示すため、業務と発症との関連性を弱めるとされています。
また、時間外労働が月80時間に達しない場合で、発症前1ヵ月ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月あたり、おおむね45時間を超える時間外労働が行われていない場合には、業務と発症との関連性が「弱い」と判断されます。
さらに、発症前1ヵ月ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月あたり、おおむね45時間を超えて行われた時間外労働が長くなると、それに応じて、業務と発症との関連性が「徐々に強まる」と判断されます。
時間外労働の時間数と、業務と発症との関連性をまとめると、次のとおりです。
【図】時間外労働の時間数と、業務と発症との関連性
| 1ヵ月あたりの時間外労働 | 業務と発症との関連性 |
| 45時間まで | 弱い |
| 45時間を超える | 徐々に強まる |
| 発症前2ヵ月ないし6ヵ月に80時間を超える | 強い |
| 発症前1ヵ月に100時間を超える | 強い |
(参考)過労死ラインの根拠
発症前の1ヵ月あたり100時間の時間外労働が労災認定の基準の1つとされたのは、時間外労働を100時間近く行う状況が、平均睡眠時間が5時間以下になるライフスタイルに該当しやすく、統計上、この睡眠時間での脳・心臓疾患のリスクが高率に認められるためです。
なお、4時間程度の睡眠を1週間続けると、ホルモン分泌異常や血糖値上昇が生じ、さらに4~6時間程度の睡眠を2週間継続すると、記憶力・認知能力・問題処理能力などの高次精神機能は2日間眠っていない人と同じレベルにまで低下するといわれています。
長時間労働以外の要因の評価
認定基準が定める時間外労働の時間数には至らないものの、これに近い労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、 業務と発症との関連性が強いと評価されることがあります。
具体的には、労働時間のほか、次の要因についても総合的に評価し、負荷の程度と疲労の蓄積度合いを判断することとしています。
労働時間以外の要因
- 不規則な勤務時間
- 事業場外における移動を伴う業務
- 心理的負荷を伴う業務
- 身体的負荷を伴う業務
- 作業環境
1.不規則な勤務時間
不規則な勤務時間とは、例えば、拘束時間(始業から終業までの時間)が長い勤務、休日のない連続勤務(連続勤務が長く続くほど、業務と発症との関連性をより強める)、勤務間インターバル(就業から始業までの時間)が短い勤務(睡眠時間の確保の観点から、インターバルが11時間未満の勤務の有無を評価する)、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務(予定された始業または終業時刻が相当程度、深夜の時間帯におよび、夜間に十分な睡眠を取ることが困難なもの)をいいます。
2.事業場外における移動を伴う業務
出張の多い業務については、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、出張が連続する程度、出張期間、交通手段、移動時間および移動時間中の状況、移動距離、出張先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容などの観点から検討し、あわせて出張による疲労の回復状況なども踏まえて評価することとされています。
3.心理的負荷を伴う業務
日常的に心理的負荷を伴う業務(常に自分あるいは他人の生命、財産が脅かされる危険性を有する業務など)、または心理的負荷を伴う具体的出来事(業務に関連して悲惨な事故や災害の体験・目撃をした、多額の損失を発生させるなど仕事上のミスをしたなど)について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされています。
4.身体的負荷を伴う業務
身体的負荷を伴う業務については、業務内容のうち重量物の運搬作業、人力での掘削作業などの身体的負荷が大きい作業の種類、作業強度、作業量、作業時間、歩行や立位を伴う状況などのほか、当該業務が日常業務と質的に著しく異なる場合にはその程度(事務職の労働者が激しい肉体労働を行うなど)の観点から検討し、評価することとされています。
5.作業環境
長期間の過重業務の判断にあたっては、作業環境を付加的に評価することとされています。
作業環境としては、湿度環境と騒音が評価されます。
「温度環境」については、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状況、一連続作業時間中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度、水分補給の状況などの観点から検討し、評価することとされています。
「騒音」については、おおむね80 dB(デシベル)を超える騒音の程度、そのばく露時間・ 期間、防音保護具の着用の状況などの観点から検討し、評価することとされています。