有期労働契約の「不更新条項」とは?不更新条項によって更新をしない(雇止めをする)場合の留意点を解説
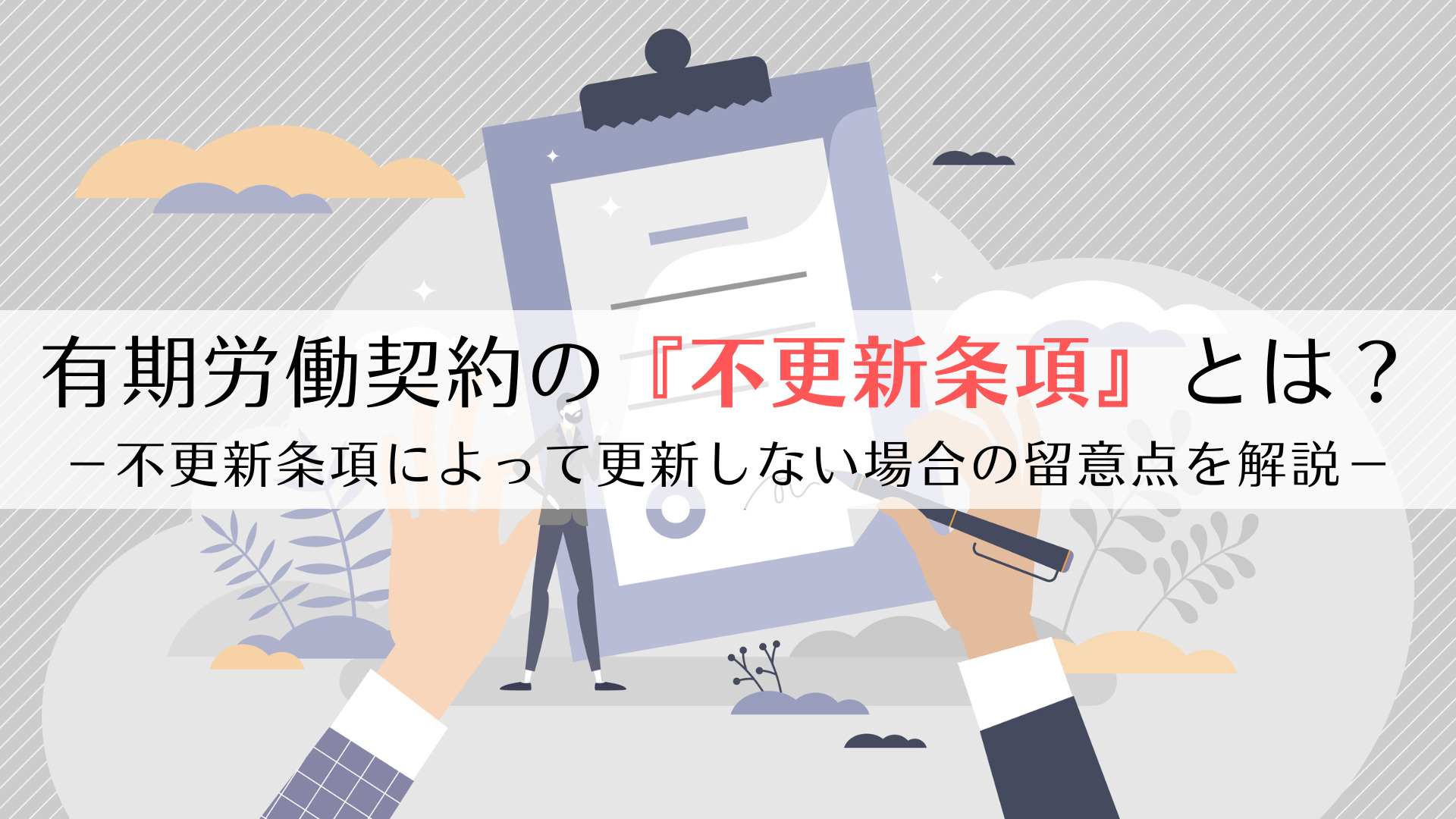
はじめに
会社が、パート・アルバイトなどの従業員を、契約期間を定めて雇用する場合、契約期間の満了後、その契約の更新の有無をめぐってトラブルになることがあります。
会社としては、更新時のトラブルを回避するために、初回の契約時に契約年数の上限や更新回数の上限を契約書に定めたり、または更新時において「次回で契約を更新せず、終了する」旨を定めることがあり、これを一般に「不更新条項」といいます。
この記事では、「不更新条項」について、どのような場合に法律上有効と認められるのか、裁判例をもとに解説します。
「不更新条項」とは
会社は、法律により、従業員との間で、期間の定めのある労働契約(以下、「有期労働契約」といいます)を締結する際には、従業員に対して、当該契約期間の満了後における「契約の更新の有無」を明示しなければならないと定められています(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第1条)。
このとき、契約書において、「契約を更新しない」旨を明示する記載事項のことを、一般に「不更新条項」といいます。
不更新条項は、広い意味では、契約期間や更新回数の上限を定めることも含まれます。
「雇止め」とは
従業員が契約の更新を望んでおり、更新の申込をしたにも関わらず、会社が有期労働契約を更新せず(申込を拒絶し)、契約を終了させることを、一般に「雇止め」といいます。
法律では、従業員が、有期労働契約の契約期間の満了時において、その有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合には、会社は、雇止めをすることに客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められない限り、雇止めをすることは認められないとされています(労働契約法第19条第2号)。
これを「雇止めの法理」といい、従業員が契約の更新について「合理的な期待」を抱いていると認められる場合には、雇止めについて「解雇」(正社員など、期間の定めのない労働契約を一方的に解約すること)と同視して、解雇に関する法理を類推すべきとする理論に基づいています(日立メディコ事件/最高裁判所昭和61年12月4日判決など)。
不更新条項と雇止めの有効性
有期労働契約の更新時において、会社が契約書に不更新条項を設けて、今回限りの更新で契約を終了すること、あるいは更新年数や更新回数の上限を通知したとしても、それによって、当然に、雇止めが適法となるものではなく、雇止めの有効性(適法性)が争われる可能性があります。
有期労働契約における「合理的な期待」の有無は、最初の有期労働契約の締結時から、雇止めされた有期労働契約の満了時までの間における、あらゆる事情を総合的に勘案して判断されます。
したがって、従業員がすでに雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、契約期間の満了前になって、会社が更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって法律上有効に雇止めをしたことにはならないと解されます(平成24年8月10日基発0810第2号)。
例えば、従業員が雇用継続を希望していることが明らかな場合には、従業員が単に不更新条項を含む契約書に署名・押印しただけでは、雇止めに対する合意が認められないとする裁判例があります(ダイフク事件/名古屋地方裁判所平成7年3月24日判決)。
無期転換ルールと不更新条項
「無期転換ルール」とは、会社と従業員との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、従業員からの申し込みによって、当該有期労働契約が無期労働契約(期間の定めがない労働契約)に転換されるルールのことをいいます(労働契約法第18条第1項)。
そこで、会社としては、無期労働契約への転換を阻止するために、不更新条項を契約書に定めることより、通算5年をもって雇止めをする場合があります。
ただし、雇止めによって無期転換を阻止することにより、従業員から無期労働契約への転換を申し込むことはできなくなりますが、一方で、会社による雇止めが法的に有効であるかどうかは、別の問題として残ることに留意する必要があります。
つまり、無期転換を阻止する目的で、通算契約期間が5年を間近に控えた時期になって、唐突に契約書に不更新条項を盛り込むような運用は、雇止めの有効性をめぐって争われるリスクがあります。
無期転換ルールの詳細については、次の記事をご覧ください。
無期転換ルール(5年)とは?有期労働契約の「無期転換申込権」をわかりやすく解説
不更新条項によって雇止めをする際の留意点
前述のとおり、不更新条項を設けたからといって、必ずしも雇止めが有効になるものではありません。
会社が不更新条項を設けて契約を更新しない場合に、少しでも雇止めのリスクを減らすためには、少なくとも次の点に留意する必要があります。
不更新条項を設ける際の留意点
- できる限り有期労働契約の早い段階(できれば最初)から、不更新条項を設ける
- 従業員に対し、個別面談や説明会により、会社側の事情を丁寧に説明する
- 従業員に熟慮期間を与え、自らの意志で契約を締結させる
以下、上記3つの留意点について順に解説します。
【留意点1】早い段階(できれば最初)から、不更新条項を設ける
基本的な考え方
会社と従業員との間で、有期労働契約を締結する「最初」の段階から、更新年数・更新回数に上限を設けていた場合(例えば、「契約期間の上限を3年とする」、「契約期間を1年とし、更新回数は2回を上限とする」など)には、上限年数・上限回数を超えて更新されることに対して、従業員が「合理的な期待」を抱くことは通常想定されない(合理的な期待を抱く前の段階での契約である)ことから、上限年数・上限回数に達したことをもって雇止めをすることは、基本的に問題ないといえます(日本通運(川崎・雇止め)事件/横浜地方裁判所令和3年3月30日判決、北陽電機事件/大阪地方裁判所昭和62年9月11日決定など)。
また、最初の段階であれば、契約を締結するかどうか自体、従業員の自由な意思で決めることができるため、会社が優位な立場から契約書への押印を迫ったなどと判断されるリスクもありません。
つまり、有期労働契約においては、できる限り早い段階(できれば最初)から不更新条項を設けておくことが望ましく、不更新条項を設けるタイミングが雇止めの間近であるほど、従業員の更新への期待はすでに高まっており、会社による雇止めが認められないリスクが高まるといえます。
雇止めと判断されるケース
有期労働契約を締結する最初の段階から、更新年数・更新回数に上限を設けていたとしても、実際にはそのとおりに運用がなされておらず、結果的に、当該上限を超えて再度契約が締結されているといった事情がある場合には、雇止めが違法と判断される場合があります。
裁判例①
外国航空会社の客室乗務員について、5年を上限とする契約を締結した後、再び5年の契約書を締結し、雇止めをした事案において、裁判所は、形式的な同意書面が整えられたからといって、従業員が5年で雇止めをされるような地位にあることを予想していたものとは考えられないというべきであり、正社員と同様に雇用関係が継続されるものとの期待、信頼を抱いていたものと評価して、従業員が勝訴しました(カンタス航空事件/東京高等裁判所平成13年6月27日判決)。
裁判例②
社団法人との間で、数年間、業務職員として有期労働契約を締結した後、管理員として最長5年の有期労働契約を締結した事例では、業務職員としての業務と、管理員としての業務が同一で、管理員であった者が業務職員として雇用を継続された例もあることなどの事情から、管理員として雇用契約を締結する際に最長5年であると告げられていても、当該雇用契約が5年で終了した後に、業務職員として雇用契約が更新されると期待することには合理性が認められ、社団法人が業務職員としての雇用契約の締結を拒否したことは、雇止めと同様の効果を有し、権利の濫用に当たると判断した裁判例があります(近畿建設協会事件/京都地方裁判所平成18年4月13日判決)。
【留意点2】個別面談や説明会により、会社側の事情を丁寧に説明する
会社が個別面談や説明会を実施して、従業員に対して丁寧な説明をすることが、不更新条項の合意に至るプロセスとして重要な意味を持つことがあります。
従業員の理解を得られるように、会社が雇用契約の更新に先立って、説明会を開催し、雇止めの必要性(会社の経営が厳しい状況であり、雇止めがやむを得ないこと)を事前に説明したうえで、契約書に不更新条項を入れ、従業員(1年ないし3年の有期労働契約が約11年間更新)がそれを理解したうえで受け入れたという経緯が評価され、雇止めを「有効」と判断した裁判例があります(本田技研工業事件/東京高等裁判所平成24年9月20日判決)。
この裁判例では、会社が説明会を開催し、従業員も雇止めはやむを得ないものとして受け入れていた経緯から、雇用継続に対する期待利益を確定的に放棄したと認められると判断しています。
なお、雇止めの有効性の判断においては、会社側の経営上の理由から、どの程度、雇止めの必要性があったのかが影響することがあります。
例えば、従業員(3ヵ月の有期労働契約が19年間更新)が労働契約を終了させる明確な意思を有していたといえないものの、合理化施策や事業構造改革を実施したこと、同改革により正社員が約半数に減少したこと、事業所閉鎖が告げられていたことなどの事情から、雇止めを「有効」と判断した裁判例があります(東芝ライテック事件/横浜地方裁判所平成25年4月25日判決)。
【留意点3】従業員に熟慮期間を与え、自らの意志で契約を締結させる
会社の立場の優位性
不更新条項を含む契約書に従業員が押印をしたからといって、それをもって直ちに有効な「合意」があったとは認められないことがあります。
会社が従業員に対して、不更新条項を含む契約書への押印を求めた場合、従業員にとって、契約書への押印を拒否すれば、その時点で契約が終了してしまうことを意味するため、それならば、多少納得がいかなくても、少しでも長い間働くことのできるよう、不更新条項を受諾せざるを得ない立場に置かれることがあるためです。
つまり、有期労働契約の更新時においては、一般に、会社の方が、従業員よりも立場が優位になりやすいことから、合意それ自体が、従業員の真意によってなされたものではない(合意の意志表示に錯誤や脅迫があった)として、争われることがあります。
例えば、従業員が不本意ながら、不更新条項を含む労働契約を締結せざるを得ない状況にあったと認められる事案では、解雇権の濫用法理が類推適用されています(明石書店事件/東京地方裁判所平成22年7月30日決定)。
会社の対応における留意点
合意の有効性について、後に争いが生じることを避けるためには、不更新条項を含む契約の更新時においては、できる限り前もって(例えば、契約期間満了日の2~3ヵ月以上前までには)、契約内容を説明し、従業員が熟慮する期間を与えることが必要です。
その際、契約不更新条項に合意することの代償として、退職金を支払うなど、合意をすることによる従業員側のメリットを併せて提示することができれば、従業員が自らの意思で任意に(強制されることなく)契約したことを裏付ける一事情となるといえます。
例えば、不更新条項を含む契約書に本人の署名・押印があるだけでなく、退職餞別金の通知を受けていること、契約期間満了前に有給休暇を取得していること、契約更新前に説明会を開いたこと、会社に対して事前に不更新条項について反対の意思を表明していないことなどから、不更新の合意は存在すると判断した裁判例があります(近畿コカ・コーラボトリング事件/大阪地方裁判所平成17年1月13日判決)。
また、複数回の面談を行い、その中で会社が従業員に対して労働契約を更新しない旨を明確に告げていたなどの事情から、従業員が事態をよく理解したうえで任意に意思決定をしていることが推認され、会社が脅迫・詐欺により不更新条項に同意させ、または従業員に錯誤があったとはいえないと判断した裁判例があります(日立製作所事件/東京地方裁判所平成20年6月17日判決)。


